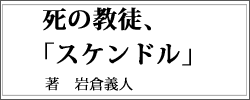3 クーネミュール学者ヨーカラインダー・ヘッザの日記
光暦780年9月15日
また、彼女に会える時が来た。私はこのときを心待ちにしている気さえしたが、今日になってみると、恐ろしく感じた。
今日の接見はかなりの成果がみられた。一般的な意味での意思疎通は無理だったが、彼女は診察することを許してくれた。それは十分に彼女の犯罪的生物である由縁を明らかにした。
彼女たちは永遠に妊娠している。
彼女たちは死の子供を腹の中に宿しているのだ。それは彼女たちにとっての神、スケンドルだった。
スケンドルはどんなに待っても外の世界に産み出される事はない。腹にそれを宿している彼女たちが死ぬことがあっても、出てこようともしない。それが永遠の妊娠という訳だ。
私の役割は彼女を解剖し、スケンドルを取り出して、その標本を光量子の教徒の最高神官である、カリフに献上することだった。また、スケンドルを妊娠する事と彼女の頭骨がむき出しになっていることの因果関係も調べなければならなかった。
これまでの間は私たちクーネミュール学者がいくら申請しても、調べることを許されずに、彼女たちは捕まるとすぐに何の裁判もなしに光量子の炉の中に放り込まれて焼き殺され続けてきた。
しかし、カリフは教徒たちの信心を維持するためにはクーネミュール学がどれほど有意義であるかをやっと理解したのだ。
だがここで、最も根本的な問題が生じた。私が彼女が殺されるのを耐えられそうもないということだ。こんなことはばからしくて、仲間に言うことは出来そうにもない。それが分かっただけでも、学会の中心から追っ払われてしまうだろう。私は彼女が妊娠している死のスケンドルの子供が、私自身の子供のように感じ始めた。私は彼女を診察して帰るとき彼女の手をそっと握った。すると彼女はやさしく握り返してくれさえしたのだ。
*この恐ろしい告白から不思議なことにスケンドル教徒の話は全く日記には書かれなくなる。やはり何かしらの葛藤が彼の胸の内で起こっていたのだろう。しかし、当たり障りのない日々の雑事の中に彼の思っていることが密かに現れている。
彼は何度も日記の中にK・S・T協会に問い合わせの手紙を書いたことを残している。その手紙の内容は不明だが、K・S・T協会とはいったい何を指しているのだろうか。それは多分カスク・エティウス・ティ(臓器と神の庭)のことだろう。
そのことは彼のこの後の日記の記述を見れば容易に推測できる。
そのカスク・エティウス・ティ協会の主な業務のことは調べれば、今でも分かる。それは人工臓器を配布している慈善団体だった。そこから何度も彼はカタログを取り寄せていた。
「光り輝く神の分身の中から人工の臓器を取り出す。血は滴ることはもはやない。」
そう粗雑な印刷のカタログには書かれていた。
人工臓器はクーネミュール学に少なからぬ関係を持っているとはいえ、その興味は異常なほどであったといえるかもしれない。
なお、彼はこの密かな趣味について、同僚には一切何も漏らしてはいない。スケンドル教徒の事だって、ほとんど話さなかった。彼はそのために組織された調査チームを自分の権限でほぼ解体し、研究は頓挫しているかのように見えた。少なくとも表面上はそう見えていた。
だが、彼はスケンドル教徒が殺されないように調査申請書をカリフに出し続けていたし、一向に調査が進んでいないにも関わらず、カリフはスケンドル教徒の処刑を延期し続けた。ヨーカラインダーとカリフの間には何らかの約束ごとがあったのだろうということを推測するのは容易だ。
事実はただ、カリフがヨーカラインダーを好いていたということだけかもしれないが。彼の日記の話に戻るが、その謎のK・S・T協会からの手紙が届いたとかの記述はつまらないので抜きにして、彼がまたスケンドル教徒そのものについて饒舌に語り始めるところから、引用を始めたいと思う。それは彼の中である重大な決心が着きつつあるを示しているのではないだろうか。彼がもう学会の座には興味を持たぬことを、またそれ以上の意味を示しているとさえいえるだろう。