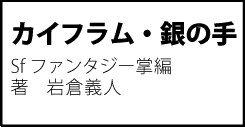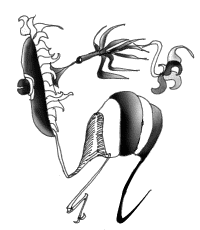
1
私はカイフラムを助けるためにその場所でずっと待っていた。
カイフラムを見分けるための唯一の方法は、彼の手のひらを見ることだった。彼の手には未だ、赤くて暖かい血がこびりついているはずだ。
とくとくと流れ続ける、暖かな花びらを彼は隠して生き延びようとしているらしかった。私はあいにく、そんな彼を許せるぐらいの優しさというものを持ちあわせていなかった。
カイフラム。私は何度その不思議な名前を夢の中で口ずさんだだろうか。
彼の手はもともとは銀色に輝いていた。だから、彼は私たちの間では銀の手とも呼ばれていた。彼は幾度もなく、私達の打ち出した弾丸を素手で受け止めてきた。
それでも、彼の手は傷一つ負う事もなかった。いかによく切れる剣であったとしても、また、いかに強力な銃であったとしても、彼の手は吸い着けるようにして、それを受け止めたのだ。そのせいで、彼の仲間たち、呪われた者たちはいつも生き延び続けてきた。
私は彼の手の事ははっきり覚えているのにどうしても、彼の他の特徴を思い出す事が出きなかった。私が彼を見た時、彼は様々違う恰好をしていた。彼はいつも変装しているらしかった。
そもそも、私たちがなぜ、彼であると断言できるのだろうか。
それは、やはり、銀の手が流した血を採取出来たから、分かったという事が出来るのだが、本当はそれよりもずっと前に私にだけは分かっていた。彼が男であるという事が。
別にそんな事はどうだっていいと思う人もいるだろう。それなら、もうちょっとましな話をしてやろう。彼らが起してきた事件のことなんてどうだろうか。また、まず、私が銀の手に初めて会ったときのことを話そうと思う。
彼らの名前をここでは仮にケフェラートとでもしておこう。なぜなら彼らは決して名前を名乗らないからだ。むしろ、彼らは名前を捨てたと言ってよいだろう。ケフェラートたちは固有名詞を憎んでいるのだ。
そして、驚くべき事に彼らは文字というものを知らない。別に読み書きできなくたってかまわないかもしれない。しかし、私がそのことを驚くべきだと言った、もっともな理由がちゃんとある。
それを納得するためには捕まえられた、ケフェラートたちの口の中を覗いてみればすぐに分る。
彼らは舌を持っていないのだ。しかし舌の根っこの所にはかすかにその痕跡が残っている。小さくていじけた、女の小指の先っぽのような濡れたかたまり。私が彼らをケフェラートと呼んだ理由はそこにある。つまり、ケフェラートとはズラフ語で「縮れた舌」と言う意味なのだ。それで私は一人で勝手にそう心の中で呼ぶことにした。他の人たちは彼らのことを唖(おし)の教団などと呼んでいたが、私はそう呼ぶのが嫌でしかたがなかった。また単に灰色のマント達と言う人もいたが、その方がずっと一般的だとも思う。
その美しい舌を持つ、ケフェラートたちは言葉が音として発っせられることにさえ嫌悪感を抱いているのだろうか。
私は過去に一度だけ彼らがコミュニケーションを取りあっている姿を見たことがある。まるで、その若い男二人は恋人どうしの様に手を握り合っていた。そして、見つめ合いながら、互いの手のひらを優しくなでたり、ゆっくり指をつまんだりしていた。
彼らはそうやって、本当に静かに、次の生贄になるべき人間は誰にするべきかといったことや、どのようにそれを成し遂げるかといったような、極めて残忍な事を話しあっているのだ。
その指を握りあう、ちょっとした動きや強さが一つ一つ単語になっているらしかった。
私は長い間、追い続けて来た、その若い男たちの姿をずっと見詰め続けていたかったが、そうとも言っていられなかった。
私は彼らの事を捕まえるか、殺すかしなければならなかった。そうしなければ、ケフェラートの一人一人がまた何十人も人を殺すのが目に見えていた。つい昨日も恐しい姿をした死体が見つかった。その二人の死体は元は恋人同士であるらしかった。
一見したところ、彼らの死因は全く、殺人者の手に掛かったもののようには見えなかった。ほとんど自然死であるようにさえ見えた。しかし、解剖した結果、想像を絶する奇妙なことが分かった。舌が交換されていたのだ。つまり、もとは男の方に付いていた舌が女の物となり、またもとは女の舌は今は男の口の中に収まっているという具合だった。
その舌のそれぞれの付け根の部分はまったくと言っていいほど、自然で、もちろん縫い目も無かった。
二人の舌は生きているうちに交換されたらしかった。それで、彼らの体は突然舌を取り替えられたことを拒絶しようと思ったのだろうか、激しく歯で食いついたのだ。最後に、呪われた舌はなんとか食い千切られることから逃れようとして、歯から遠い所へ、喉の奥へと、身を隠そうとした。そうして、彼らは息を詰らせて死んでしまったのだった。
検死官スイ・ダフは最初から彼らの舌がおかしいのを気付いていた。彼らの喉の奥に絡まりついていた、舌を引っぱりだすと、丹念にその長さを計った。男の舌は彼のがっちりした頭蓋骨や、長身の割にとても短かかったし、女の方に付いていた舌はあまりにも長すぎた。
女の舌を引っぱり出したあと、口を閉じようとしても、舌が口の中に収まりきれずに外に溢れた。そのなにかを舐めとろうとして、出されたかのような舌を眺めながら、検死官は即座に彼らの遺伝子検査を要求した。彼らの体と舌の両方から、サンプルを取るように彼は指示した。
しかし、出た結果に一番驚いたのはダフだった。彼はこの二人に行なわれたのは間違いなく殺人であると言う事をどうやって証明すれば良いのか悩んだ。
舌を取り替える事がなぜ死に継がるのかということを立証しなければならなかった。
だが、ダフの懸念をよそに、捜査は進められていた。人間に対する尋常ではない操作が行なわれたのだけは確かだったので、それ自体も重大な犯罪であるとこの国の元首である、「ナミフラの目」は判断したのだった。
もしかすると、ナミフラの目は殺人よりもそのことに生理的な嫌悪感を覚えたのかもしれなかった。
ナミフラの目はかねてから、ケフェラートたちを排斥するための理由を探していたのだろう。
「ナミフラの目の子供」はその時私を呼びつけてこう言った。
それは唯一のナミフラと直接接触でき、彼の言葉を伝える者だった。
「ナミフラは泣いています。嘆いています。紫の涙を流して。」
その時のナミフラの目の子供は若い女だった。白い目と白い肌をしていた。ナミフラの子供はいつでもそんなだ。元は普通の色をしていたのに、毎日ナミフラに触れられているうちに、そんな色に変ってしまうのだ。
ナミフラの子供はその後ずっと、静かに話し続けていたが、私にはうまく聞き取れなかった。それは私の耳が良くないとか、彼女の声が小さすぎるという意味で言っている訳ではない。
ナミフラの子供の声はどういう訳か意識の中に残りにくかった。水の中に頭を沈めて、遠くからする声が耳の中で反響している状態とそれは似ていた。違うところがあるとすれば、ナミフラの子供の話の内容は記憶の中にだけはしっかり刻みこまれるということだった。あとから思い出す事だけはできるのだ。
私はナミフラの子供の話が終ったあと、二人の被害者にそのような恐しいことをした犯人をなんとしても捕まえなければならないと決心せざるを得なかった。だが、ナミフラの目がそこまで嫌悪するものとは一体何であるのかその時は全く分らなかった。
その後何日かして、ついにダフは被害者のカップルの舌の中から、殺人の証拠となる物質を見付けた。舌を移植したあと、強制的に拒絶反応を起こさせる物質を。その物質、カッファリン酸がたっぷりと注射された舌を移植された彼らの体は、全く違う異物を発見し、驚きのあまり、その異物を飲み込んで、自分と一体化して安心を得ようとしてしまうのだった。まるで生きていた時に彼らがキスし合って感じていた味をもう一度確認しようとしているかの様だった。
しかし、その事が逆に仇となって、息を詰まらせて死んでしまったのである。
その傷跡を一切残さず、舌を取り替えた方法はまったく分からなかったが、警察の評議会にダフはその事を話した。ナミフラの目はそういった事を聞いても怯えて何も答えなかったが、操作は続行された。ナミフラの怯えだけで十分な答えであるともいえた。
しばらくして、不審な二人連れがカップルが姿をくらませた数日前から、彼らの事を嗅ぎ回っていたことが分かって来た。彼らは灰色のマントを着ていて、その裾から覗かせていた、青白い手をひらひらと動かせていたという。
彼らは手話で話していたのだろう。教団でも位の低い者は手話を使う。また指の関節を静かに握って会話をするのだった。もっと位の上の者になると、言葉を伝える手段を何も持っていなかった。
もっとも彼らぐらいになると、人に伝えようとすること自体、無意味になってしまうのかもしれなかった。そういったことは教団のことがやっと分かりつつある、今になったからこそ言えることだったが。
彼らの移植する手腕は驚くべき物だったが、誘拐の仕方自体は素人そのものだった。
それで、私は彼らが良く現れるとされる、デラフ街で待ち構えることにした。
その時私の目の前にいた、灰色のマントの二人連れは今度は手話をせずに、互いの手を握り合っていた。その姿はいかにも優しげに見えたが、捜査を続ける一月ぐらいの間にまた何件も同様の手口で殺人事件が発生していたのだ。ナミフラの目はまた彼らがやったに違いないと断言した。
私は彼らを眺めながら、なぜ彼らはそんなおかしな方法で人を殺すのだろうと考えていた。彼らは普通に生きている人間を憎んでいるのだろうか、それとも逆に、普通の人を望ましい方向性に向かわせてやっているのだから、感謝すべきだとでも言うのだろうか。
多分彼らは人間に黙れ!と叫びたいのだ。誰だって、このやかましい街中にいたら、そう思うさ。
私はそうやって彼らに多少同情しながら、上着の下にある重たい銃を手で引っぱり出した。
そうして、彼らのすぐ近くにそっと近寄ると、銃口をマントの影にある、男のこめかみに押し付けた。その若い男のブロンドの髪は汗でにじみ始めた。彼は相手の男の手を握り続けていた。
彼はゆっくり私の方を振り返ると、驚きもせず、不思議なものを見るような目で見詰めていた。私はそれを見て、彼の瞳がいかにも純真そうだったので、自分がしようとしている事に思わず違和感を覚えた。
それでも、私はいつも通り、低くつぶやいた。
「お前たちを逮捕する。殺人容疑だ。私はナミフラの目の力によってお前たちを拘束する。お前たちはナミフラの目に許しを乞う事もできる。さもなければ、死だ。」
そう、私が、逮捕の時の決まり文句を言っても、彼らは黙ったままだった。私が銃を突き付けていない方の男も逃げる気配すら全く見せなかった。彼もうす緑色した奇妙な目付きで私を見ていた。微笑んでさえいるようだった。
私は左手を挙げて、仲間の警官に合図を送った。しかし、何秒待っても返事がなかった。さすがにいらいらして、振り返ろうとすると、私の真横に灰色をした大きな影が立っていた。
その影の中からゆっくりと手が伸ばされて来た。その手の平はうっすらと銀色に輝いていた。
私は驚いて、その手に向かって銃を撃った。だが、弾は発射されなかったようだ。奇妙だった。私の手には銃を撃った時のいつもの振動がちゃんと残っていた。それなのに、何か違っていた。そうだ。何も音がしなかったのだ。
私がそう考えていると、銀色の手の平の上に、私の撃ち出した弾丸が乗っているのが見えた。その手から、黒いいじけた弾丸がポトリと地面に落ちた。
それから、その手はだんだんと私の首のところまで伸ばされて来て、強く締め付け始めた。
私はそれきり、意識を失なってしまった。
それが、「銀の手」と私との最初の出会いだった。
私はまだ運が良かったのか、三日後に目を覚ましたが、他の一緒に張り込んでいた5人の仲間はそうはならなかった。全員、銀の手に締め殺されたのだ。彼らは不思議な事に仲間が首を締められているのを、目前にしながら、助けようともしなかった。いや、たぶん、助けることが出来なかったのだろう。
私と同じように。私も銀の手が差しだされているのを見てもどうすることも出来なかった。
彼の手を見ていると、意識がぼやけて、体は麻痺したように全く動けなくなってしまうのだった。
それでも、病院のベッドに眠る、私の頭の中に何度も反響する言葉があった。
「カイフラム」
私はその言葉を一度、呟いてみた。その瞬間、それが、銀の手の名前であることが分った。
私はそれらの事をナミフラの目の子供に伝えた。
彼女は何が起っているのか信じたくないようすだった。