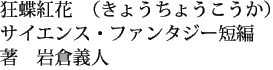6 灰の鳥の歌
「灰を着た鳥、
赤き熱砂の中を飛び立って、
白き闇に消える。
空中に身を投げ出した鳥の、
次に地面に降りるときは死。」
ダクエは森の中を歩きながら、灰の鳥の歌を静かに歌った。
その歌は狂蝶紅花にそっくりな気がした。蝶のお腹の中には汚い爆弾が詰まっていて、それで地面を汚すの。そしてその血を吸って木の芽が育つんだわ。
そこまでつぶやくと突然、銃を口に突っ込まれてうろたえている、青白いペニの顔を思い出した。口からは透明なよだれがあふれてきらきら光っていた。それは水あめのようでとてもきれいだった。キスして少しなめとっておけばよかった。
でも私はなぜペニのことを殺そうとしたのだろう。それにどうして彼は逃げようともしなかったのか。
彼女は自分がコートの下に隠していた銃がなくなっていることに気づいていなかった。ダクエは森に落ちた銀の花びらのような落ち葉を踏みしめながら、月が出ていて良かったと思った。
「そうか。大事なのはなぜ殺そうとしたかではなくて、なぜ殺さなかったかと言うことだった。私が引き金を引こうとしたとき、とても不思議な感じがした。私が蝶を撃ち殺したときとはちょうど逆の感じだった。だから、彼を殺さなくていいことがわかったのかもしれない。多分、私が彼に渡そうとした狂蝶紅花の死は本当は私自身のものだってのに違いがないわ。だから今私の中には白い花びらが見える。
それは狂蝶紅花が新しく生まれ変わろうとしている姿。
ペニはそれを与えられる資格なんて初めから持っていなかったの。
私はそれをペニでなくて私が殺してしまった狂蝶紅花に返さないといけない。
そのことを私の中の蝶が教えてくれたから、私はペニを殺さなくて済んだ。」
もしかすると、そんなふうに彼女の中の蝶が教えてくれていたのか、彼女は狂蝶紅花の木があるところまで行くのに全く迷わずに済んだ。
歩きながらもうペニには二度と会いたくないと思った。多分会ったら彼はまた馬鹿面をしてあくびでもするような大きな口を開けるのだろう。「そうしたら、私はまた頭に来て銃を口の中に突っ込まなくてはいけなくなるかもしれない。」
そんな風になるのなら死んだほうがましだった。彼だって同じように思うに違いない。
それに今こうやって狂蝶紅花に向かって歩いている事だってきっと彼のためになると思えて仕方がなかった。彼がした過ちを私が正そうとしているのだから。
彼女が最後の真っ黒な藪を潜り抜けると、狂蝶紅花の木が立っていた
その木は今日の夕方見たときとは何か違っていた。そうだ、花が全部無いんだ。
すべての蝶が飛び立った後だった。多分彼らはどこかでもう死んでいるだろう。
そう思うと突然、ダクエはその木の存在自体が誤りであることに気がついた。なんて不潔で、気持ちが悪い木。かわいそうな蝶たちを殺して、そうやってしか生き延びられないなんて。私が殺すべきなのは、無意味なペニなんかじゃなくて、この木なのかもしれない。ダクエはそっと木に近づいて行った。木が逃げるはずないのだから、気にしなくてもいいのかもしれなかったが、そうしないと木に何かされそうな気がしたのだ。
長い時間をかけて手が触れられるぐらいの所まで近づいてみると、木の幹が奇妙にねじくれあっているのが見えた。その表面は恥ずかしそうに汗で覆われていた。
思ったより華奢な幹だった。ちょうど女のすねぐらいの感じだった。これだったら私だって折れるかもしれない。そのとき彼女は自分のコートのすその中をまさぐって、やっと自分が銃を持っていないことに気がついた。銃で幹を撃ってみようと思ったのだ。
しばらく、ダクエは自分の薄っぺらな爪を眺めていたが、一つため息をつくと、幹に手をついて力を入れた。
驚いたことに幹の皮はとても柔らかくて動物の皮膚で出来ているみたいだった。そして彼女の手が触れた瞬間、ねじくれている幹の皮の隙間が開いてそこの中に指が自然ともぐりこんでいった。ダクエはびっくりして手を引っ込めようとしたのだがうまくいかなかった。手は冷たい木の幹の中に吸い込まれて行った。
中は凍り付いているみたいに冷たかった。こんな中に蝶たちが生きていると言うこと自体信じられなかった。そうか、彼女たちは植物でもあるのだから、眠らされてこの中で飼われている。だから、こんなに冷たいんだ。彼女たちは仮死状態のまま大人になるのだ。
なんだ、それだったら人間だってそっくりじゃないか。だからこの木は私を中に入れて自分の物にしたいと思っているのだろう。
ダクエはおかしなぐらい憎悪を感じた。そして、なんとか指を動かすと握りこぶしの形に変えた。すると手のひらの中に暖かいものが握られたのを感じた。それはやけどしそうなぐらい熱かった。
ダクエは叫び声をあげて何とか手を引き抜こうと地面に踏ん張った。しかし、今度はそうする必要もないくらいあっけなく手は木の幹から引き抜かれた。こんどははじき出された感じさえした。
一体この木はどういうつもりなのだろう。ダクエは頭に来てぶつぶつ文句を言いながら、自分のてのひらに握られているものをそっと開いて見た。
それはしわくちゃにつぶれた花びらの塊みたいだった。その真っ白なものは彼女の手のひらの中でもぞもぞ動き始めた。彼女は幹の中からまだ目覚める準備が出来ていない若い蝶を引っ張り出してしまったのだ。「だめ、まだ今は目を覚ましちゃ。」ダクエはそれをどうしたら幹の中に戻せるのだろうかと考えた。しかし、蝶のお腹のところをよく見ると、赤い傷が出来ていた。そして、蝶が身震いをするたび、その中から赤い血が滴り落ちた。彼女の手の中でだんだんと白い蝶は真っ赤に染まり始めた。
「いいわ。あなた。そんなに急いで体を赤くしなくったって。もうそんな必要ないもの。どうせあなたは胎児のまま外に出された赤ん坊と同じだもの。そんなふうに苦しまないようにしてあげるわ。」小さな蝶の頭に彼女は唇を触れた。
するとその瞬間、唇を火傷しながら彼女は理解した。その蝶は一度自分が殺したものであることを。蝶から銃の火薬の匂いがしたのだ。
「そう、あなたは死んだと思っていたけどやっぱり死ねなかったのね。だから木の中に戻って怪我を治そうとした。それでも、あなたは無理だと思ったのね。あなたたちは花になってちゃんと飛び立てないと死ぬことすら出来ない。
あなたたちは木に死を与えてもらわないと死ぬことすら出来ないのね。だから、私のことを呼んだ。私の中のあなたの死をちゃんと返すわ。」
ダクエは今度はそっと歯を突き出して蝶の頭に触れると、その先っぽをかじり取った。そして、蝶がちっぽけな頭を突然失って痙攣しているのを満足そうに眺めてから、彼女は蝶の体を地面に捨てた。
ダクエが口の中にかすかに残る甘い蜜の香りを楽しんでいると、何時の間にか蝶の体は静かに燃え始めた。透明なオレンジ色の炎は最初はすごく小さかったが、地面に落ちた枯葉をどんどん飲み込んで成長を続けた。そして最後には狂蝶紅花の木に燃え移ってしまった。
ダクエはその木の中から小さな蝶の悲鳴を無数に聞いた。
しかし、自分が殺した蝶がそれを望んでいることを知っていたから、彼女は火を止めようとは思わなかった。
しばらくしてダクエは森を出た。
家の近くまでたどり着いたときにはすでに、夜明けに近かった。そのうっすらと光り始めた空の中にオレンジ色の瞬きがあるのを感じた。ちょうど自分の家の前のところだった。二台の真っ黒な車が止まっていてその天辺からその光は出ているらしかった。
パトカーに違いなかった。ペニが呼んだのだろう。いかにも彼らしいとさえ思えた。ダクエはその光の方にゆっくりと近づきながら自分もその光に焼かれて死ぬのだろうかと思った。もしそうであったとしても別に躊躇するつもりはなかった。
もうすでに自分の中の死は蝶にあげてしまったのだから。
彼女はずっと自分の口の中に残っていた蝶の頭のひとかけらを、いとおしそうに静かに飲み干すと蝶に話しかけた。
「あなたのお腹の種はきっと新しい芽を出すわ。それは今までとは違うものになるはずよ。もしそうだったら、私があなたを殺したかいがあったのかもしれない。」
車のドアを開けて乗り込むと、中にいた警官は驚いて叫び声も出せなかった。
「私があなたたちの探していたダクエ・コーマネールよ。私の銃はペニの家に忘れてきたけど。たぶん彼が大事に預かってくれているわ。
私は殺人未遂容疑なんでしょ?」
狂蝶紅花 終わり