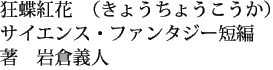3 狂蝶紅花の森
しかし、ダクエの予想は全く外れていた。
ペニは薄暗くなりかけてきた郊外の森の中を、くるぶしまで埋まる枯葉でがさがさいわせながら言った。
「僕にはその狂蝶紅花という生き物がとても生意気に感じたんだ。だってそうだろ、奴らが目を覚ます瞬間は枝から離れた時で、地面に降りる間までしか生きられない。
なんてふざけた生き物なんだろう。
自分たちの生きる美しさで僕らのことを馬鹿にしているみたいじゃないか。
だから、僕は奴らのことを侮辱してやることにしたんだ。
そのために背中に銃をしょってきたのさ。
狂蝶紅花を殺すために。」
ダクエは立ち止まると彼の細長い背中に向かって、呪いの言葉を吐きかけてやろうとした。しかしあまりに今の話がばかげていたのでなんと言っていいのかすぐには思いつけそうになかったのが残念だった。
ペニは後ろに続いていた枯葉を踏みしめる足音が途切れたのに気づくと、ゆっくり振り返った。そうすることで、ダクエが逃げ出せなくなることを彼は知っていたのだ。
ダクエは二、三秒目をつぶってからまた歩き出した。
彼女は自分が逃げ出さないのは、自分でも狂蝶紅花のことを見たくて仕方がないのからだと自分に言い聞かせながら歩いた。
しばらくしてペニが言った。「おい、あれを見ろ。」
地面に赤い小鳥のようなものが死んでいるのが見えた。ただ、それはうすい透明な膜で何重にも覆われていて、口ばしも羽毛もなかった。さらによく見てみるとその真っ赤な腹には割れ目が出来ていて、そこから奇妙な緑色の芽が顔を覗かせていた。
「これが狂蝶紅花の死体らしい。全く虫には見えないが、かといって何か知っている動物に似ているわけでもないしな。小さな天使か悪魔といったところだろうか。」
そう言って、ペニはしゃがみ込むと何枚も突き出た翼に手を触れた。彼は触れた瞬間驚いて叫んだ。指には赤い物がべったりついていた。
「ペニ、あなたの血なの?」
「馬鹿なこと言うなよ。僕は怪我なんかしてない。それにこれはこの虫の血でもない。これは鱗粉だよ。」
ペニはうっとおしそうにそれをはたいた。赤い粉がふわふわと森の中を漂うのが見えた。
「この粉、不思議な香りがするのね。もう少し行けばこの子達が生きているところが見られる。ペニ、早く行きましょう。」
彼はしばらくしゃがみ込んだまま、ふらふらと歩き出した彼女のことを見ていたが、うれしそうに立ち上がると急いで後を追った。
森の中の赤い霧が集まっている辺りを歩いていくと、その霧がどんどん濃くなっていく場所があった。その近くに狂蝶紅花の木があるのだろう。
ダクエが藪の中から顔を覗かせると、何か小さなかたまりがすばやく彼女の前を横切った。彼女は無意識のうちにそれを手で払いのけてしまった。
それは思いもしなかった一撃を受けて、よろめいて地面に落ちた。
その塊りは地面に落ちる瞬間に焼け焦げるような激しい音を出してはじけてしまった。本当に燃えているようにも見えた。狂蝶紅花にとって地面は安らげる場所ではないのだ。
ペニはその様子を見てあきれて言った。
「あーあ。もう殺しちゃったよ。
何のために銃を持ってきたのか、わからなくなってしまった。
でも。良いや、まだまだ、あんなに蝶が飛んでる。」
ダクエはペニが指差した方向をはっとして見ると、小さくてつやつやした濃い緑の葉のところに蝶の形をした花がたくさんついているのが見えた。そして、風がその蝶を枝から引き剥がすとすぐに空中で目を覚まして、少し痙攣してから羽ばたき始めた。
「さっき君が殺した蝶は厳密には空中で死んだわけではなかった。地面に焼かれて死んだらしい。と言うことはまだ実験を続ける余地があると言うことだ。」
ペニは銃を背中から下ろすと袋から出してダクエの方に差し出してきた。
「君が撃ってくれ。僕の腕では当たりっこないもの。僕が撃ったら蝶でなくて君のことを撃ってしまうかもしれない。」
ダクエはもし自分が撃たなかったら、彼女の事を撃ち殺すとペニが脅しているような気がして少し苦笑してしまった。この男は蝶が死ぬところを見てみたいなどと言いながら、実際にやってみる勇気を持ち合わせていないらしい。ほんとに下らない奴だ。
そう思いながらダクエは銃を受け取った。
彼女はもう何もかもさっさと終わらせて家に帰って熱いシャワーでも浴びたかった。
「かわいそうな小さな蝶たち、地面に焼かれて死ぬのと銃で撃ち殺されるのとどちらが幸せなんだろう。きっとたいした違いなんてないはずだわ。彼らは木に捕らわれて生きているだけ。」
そうつぶやくように言うと、ダクエは銃を構えて、近くにいた蝶を一撃でしとめた。蝶は内臓をはじけ飛ばせてから、ぽとりと地面に落ちた。今度は不思議なことに地面に落ちた瞬間には焼けただれる音がしなかった。
ダクエはその死体に近づいてしゃがみ込んで見ていたが、いつまで経っても木の芽は腹の中から出てこなかった。弾丸で種が破壊されてしまったのだろうか。それとも、彼らが地面に落ちて焼かれないと芽が出ない仕組みなのかもしれなかった。
どちらにせよ、彼女が蝶の息の根を止めたことに間違いなかった。
ダクエは銃をボトリとその場に落とすとペニの方を振り返りもせず、真っ暗になった森の中にすごい勢いで走って行った。ダクエは走りながら、こんな恐ろしくて悲しいことをしてしまった自分を責め続けたが、不思議と涙は出なかった。
何度も見えない切り株に引っかかって倒れたりしながら長い時間をかけて森を出たとき初めて、彼女は後ろを見た。しかし、どこにもペニの姿はなかった。彼の姿がなくてほっとしたのはこれがはじめてだった。