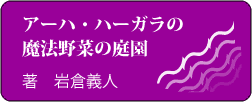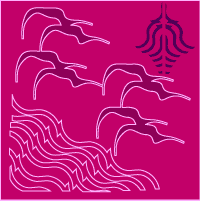6 魔法の子宮
日影の魔法使いは待ちわびていた。土の中からマーメイドが姿を現すのを。
日影の魔法使いはその時まで、穴を掘ってマーメイドを掘り出す必要があるものとばかり思い込んでいた。しかし、その必要がないことが分かってほっとしていた。
クイル・ソーダヌスはハーガラの命令を受けると自然と泳いで出てくるのだった。土の中から。どうやって土の中を泳ぐことが出来るのだろう。
多分彼女たちにとっては水も、またそれ以外の物質でも、例えば岩の塊であったとしても、泳ぐことが出来る特別な仕組みが隠されているのに違いない。多分自分の周りの空間をコントロールすることが出来るといったような。
しかし、そんな驚くべきことができるのをマーメイド自身は知っていないのに違いない。そうでなければ、彼女たちが山の岩の塊の中を泳ぎ渡っている姿が今までの間に誰かに目撃されているはずだ。
だから、クイル・ソーダヌスはハーガラの魔法の鎖につながれているからこそ、その能力を発揮することが出来るのだろう。
そうであるなら、日影の魔法使いにとっても非常に期待できることだった。彼のポケットにしまわれている、眠っている凶暴な悪魔を託したとしても、その強力な空間の制御力の中で静かに力を抑え続けてくれる可能性が高まったのだから。
朝霧のまだ晴れていない、畑の中でハーガラと二人でクイル・ソーダヌスのことを待っていた。少し前にマーメイドに浮かび上がるときに命令するために、ハーガラがしたことはとても奇妙だった。
彼女は畑の真ん中にある何の変哲もない大きな石を曲がった杖を使ってひっくり返すと、石の裏側を食い入るように見つめた。その石には日影の魔法使いが今まで見たこともない、一種の魔法の文様が刻まれていて、その同心円状の線の隙間にはなにやらびっしり文字が書き込まれていた。その文字の埋められていない隙間を探し出すと、ハーガラはポケットからペンとインク壷を取り出して引きつった字を何文字か書いた。
多分そのインクも普通のものではないだろう。どういう種類のものかたとえ聞いても教えてくれないだろうから、日影の魔法使いはおとなしく待っていた。
考えてみれば、彼は最初、ハーガラ婆さんを簡単にコントロール出来るものと高をくくっていた。しかしそれは間違いである気がいまさらながらしてきた。魔法使いの心の中で声がした。
「操作されようとしているのは俺の方かもしれない。奴はいくら今はしょぼしょぼの老いぼれであるとしても、思考操作の専門家だったじゃないか。奴が若いときにガマスル・ファグでしていたことを思い出すんだ。俺はなぜこんなところに来たんだろう。そうだ、きっと騙されたんだ。」
魔法使いは支配するものとされるものの順列が、魔法を使う力のみで決まっているわけではないことに、やっと気づいた。
彼はいつの間にかハーガラの呪いにかかっていたようだ。多分、昨晩こっそりと彼女の小屋でマーメイドの話を野菜たちといっしょに聞いていたときからそれは始まっていたのだ。
若い魔法使いはあまりに油断しすぎていた。そのような魔力を持った老婆の話を面白がって聞きすぎたのだ。
しかし、そのような状態に日影の魔法使いが陥っていても、ハーガラにはたいした関心を引き起こしてはいないようだった。もしかすると、彼女は日影の魔法使いが自分の虜になりかかっていることに気づいていないのかもしれなかった。彼女だってこんなことは久しぶりだったに違いないのだから。
ハーガラはマーメイドが浮かび上がって来てくれるか心配だった。あの男嫌いのマーメイドだからそれは十分考えられることだった。しかし、この男なら大丈夫かもしれない。本当に影のように存在感のない男だ。もしかするとそんな理由のために私のところに遣わされたかもしれん。そう彼女は思った。たいした力もないくせに。あたしに命令しようなんて!
ハーガラは一言文句を言ってやろうと振り返ると、魔法使いはフードの影の中で少し薄笑いをしているようにさえ見えた。
「なるほどな!
あんたそんなところでぼおっと突っ立ってたって、何にもなりゃしない。この役立たずが!
マーメイドが浮かび上がって来たときにじゃまにならないように、さっさとそこの草の塊をどけるんだよ。それから、少しの間だけあんた、向こうに行っててくれ。
あたしゃ、ソーダヌスと話をつけなきゃならん。
それにはあんたがいるとじゃまなんだよ。ソーダヌスはあんたみたいな男が大嫌いなのがまだ分からんのか!」
魔法使いは驚いてうなずくと、茂みの向こう側に隠れようとした。
「おい、あんた逃げ出すんかい。
その前にとっとと絡まりあった草をどけて、土を露出させるんだよ。
あんた、あたしが言ってることをこれっぽっちもわかっとらんのかい。
ガマスル・ファグの魔法院で何を習ったかは知らんが、飛んだ阿呆は治すことは出来なかったらしいな。」
彼は侮辱された事に腹を立てたのか、一瞬腰のナイフに手をやろうとしたが思い直した。「そうだ。今この女を殺す訳にはいかない。そうすれば、すっとするかもしれないが、俺はすぐに目を覚ました悪魔に食い殺されてしまうだろう。悪魔はきっと血の臭いを嗅ぎ取る。
多分これからすることにだって目を覚ます可能性があるのに、無駄な血は多すぎると大変なことを招く。」
彼は心の中で必死に自分を説得した。奴を殺したっていいがそれは全て済んだあとだ。
魔法使いはハーガラと目を合わせないように気を付けながら、地面の草を取り除いた。跡には真っ黒く輝く土が表れた。
それからすぐに彼は茂みに姿を隠した。これ以上ハーガラの機嫌を損ねないために。それにその方が都合がいい気がした。彼にはマーメイドが姿を現す瞬間がなぜかとても恐ろしいものである感じがしたのだった。
何かぬらぬらと粘液に濡れた得体の知れない生き物、それが土を泳いで出てくるのだから、隠れているのが一番だ。もし急に襲われたらどうする。もしかすると、言うことを聞くのはハーガラだけかもしれないじゃないか。
日影の魔法使いは茂みの中で無意識に震えながらハーガラのことを見守っていた。
遠くから見ているとお婆さんは、彼が草をどけた地面の土の感触を確かめるかのように、静かになでていた。まだ、ソーダヌスが姿を現すまで時間が必要らしい。
彼は少しだけほっとして、ポケットの中をまさぐった。大丈夫だちゃんとある。彼は掌にひんやりとした鉄の棒を感じた。それは鋭いメスだった。彼はソーダヌスの中に小さなネズミの姿になった悪魔を押し込もうと考えていた。強い力を持った彼女の子宮の中ならきっと悪魔の力を封印できるに違いない。そう、彼に命令した魔法使いが言っていた。
確かにどんなにおそろしくても彼はそれをしなければならなかった。
うまくいけば、彼はたんまりと金をせしめるこが出来るだろう。それに生き延びることだって。
彼はゆっくりと空を見上げた。太陽はいつの間にか高いところまで登ってきていた。その白くて強い光を見つめていると眩暈を覚えた。
多分深い水の中に閉じ込められて真っ暗な中に差し込む日の光はあんなふうに見えるのではないか。それは弱々しいどころか、返って恐ろしい力を持っているように感じた。なのに、全く熱は感じられない。それが不思議だった。
彼はそれから目を避けると茂みの下に積もっている枯葉の中に顔を埋めた。そうして湿った枯葉の臭いを貪るようにして嗅いだ。そうしてやっと気分が落ち着いてくると奇妙な事に気がついた。耳の中でやさしい、かすかな音がしていた。これまでそんな音は聞いたことがなかった。それは言葉である気がした。すごく透明感があって、それでいて何を言っているのか意識を集中しようとすると、すぐに雪のように溶けてしまう言葉。そんな音が彼の耳の中でしていた。
彼がそっと目を上げると、すぐ近くに何かが横たわっているのが見えた。それは真っ白だったが、ところどころ土にまみれて汚れていた。それは小さなイルカであるようにさえ見えた。だが、しっぽのところは正にイルカにそっくりだったが上半身に目を移して行くと人間の女の姿をしていた。彼はそれがマーメイドであることがやっと分かった。
彼はさっきからマーメイドに話しかけられていたのだ。
不思議だった。そのマーメイドは死んでいるようにしか見えなかった。ぴくりとも動かなかった。それなのにどうやって話しかけてきたのだろう。また、彼女は本当にここまで、土の中を泳いで来たのだろうか。
マーメイドの手首には細い鎖がはめられていた。それがハーガラの言っていた鎖なのだ。彼女の髪の毛は白に近い金髪だった。藪の中でやわらかい光がそれを照らしているのを見て彼はそれに触れたいと思った。しかしなぜか手が動かなかった。
彼がじっとその体を見詰めていると、また耳の中で音がした。さっきの音だ。だが、今度は何を言っているのかが理解出来た。それはこんな意味だった。
「あなたは私のもの。あなたの持っているものを私に早く渡しなさい。それは私の偽物の子供、今の私の食べれる唯一の食べ物。」
彼ははっとして自分のポケットの中に手を突っ込んで、魔法のメスを握り締めようとした。「今、こいつをこれで刺せば助かるかもしれない。その後で目を覚ました悪魔に殺されようがそんなことはどうだっていい!」頭の中でそう自分の叫ぶ声がした。
しかし、彼の手にメスといっしょのポケットに入っている小さな悪魔の毛皮が触れた。それは前よりもずっと暖かくなっていた。彼は小さな悪魔をポケットから出した。その体はかわいらしいネズミのようで、時々ぴくん、ぴくんと微かに震えた。
冬眠が解けようとしている。彼の体は恐怖に震えた。自分のてのひらにある、生き物の力がいかに強大であるのかがやっと実感でき始めた。彼はそれを今そこで捨ててもとても逃げ切れないのを悟った。すぐに目を覚ました悪魔が彼の事を八つ裂きにする感覚が彼の中ではっきりと感じられた。一体どうすればいいのだろう。
だが、安心させるように彼の耳の中でまたやさしい音がした。
「大丈夫よ。それを私ににくれさえすればいい。私にそれをくれれば、そのネズミの力を私が使える。そうすればやっと私は解放される。呪われた鎖と呪われたハーガラから。やっと私は自分のために歌えるの。だから早くそれをちょうだい!
あのハーガラが来る前に。」
彼はその声を聞きながら、マーメイドのすぐ近くに立って見下ろしていた。彼女の声はしていたが、その口は全く動いていなかった。体自体も全く動く気配を見せなかった。しかし、良く見ると彼女の目は見開かれていた。オレンジ色の瞳をしていた。彼はその瞳に映し出された自分の姿を見ていた。それから彼は、そっとマーメイドの手に触れた。
それは彼が彼女の言うことを聞くという合図だったのかもしれない。マーメイドはゆっくりと口を開き始めた。
日影の魔法使いは、まだ目覚めの痙攣をし続けている小さな悪魔をそのマーメイドの唇にそっと押し付けた。彼女は口付けしているようだった。しかし次の瞬間、彼女は鋭い牙を見せると、ネズミの頭を食いちぎった。ネズミの血は静かに滴って彼女の顔を赤く染めた。
もう、力を得始めたのだろうか、彼女は今度は手を伸ばすと魔法使いの手から残った悪魔の体を奪い取った。そしてすばやく噛み砕いて、毛皮もろとも飲み込んでしまった。
すると、彼女は疲れ果ててまた、もとのように寝転んでしまった。死んだかのように。
その口元はまだ悪魔の血で濡れていた。
悪魔はもう死んだのだ。あの、ガマスル・ファグの最高の魔法使いでも殺せなかった悪魔を彼女は食い殺してしまったのだ。日影の魔法使いは余りのことにあっけにとられていた。
「一体何をしたんだい。ああ、なぜ彼女は血に濡れているの?
あんた、一体何をしたの?
私の一番大事な友達に対して。」
いつの間にかハーガラが藪の中に来ていた。
日影の魔法使いはその干からびた肌を冷ややかに見つめながら言った。
「彼女は悪魔を欲しいと言った。彼女はそれを食いたいと言った。
そうすれば、あんたの束縛から逃れられる。
あんたのしてきたことはもう多分終わりだ。
彼女はもう、お前の言うことなんて聞きやしない。」
ハーガラは驚いて彼に詰め寄ってきた。
「あんた、それがどういうことか分かってるのかい!
今まで言うことを聞いているものが、そうでなくなるってことが。
そりゃ、あんたが持ってきた悪魔が目を覚ましたのと同じことじゃないか!」
お婆さんは、藪の中に寝転がっているソーダヌスにちらりと目をやってから、すぐに急いでそこからはなれようとした。逃げ出そうとしているのだ。だが、彼女はあせればあせるほど、ゆっくりとナメクジが這うようにしか動けなかった。
ハーガラ婆さんの前掛けのポケットから、真っ黒な斑点だらけのトマトが一つ転がり落ちた。それはころころと転がってちょうど人魚にぶつかってとまった。
ソーダヌスはそれを拾い上げながら言った。
「あなたの大切な友達を忘れているわよ。
それとも、あなたにはもういらないのかしら。
言うことを聞かない私の事がいらなくなったのとおなじように。
やっと私が私自身のために歌えるようになったんだから、あなたはもう少し喜んだっていいはず。
でも私はうれしいの。だからあなたのために歌ってあげる。」
そう言う彼女の声を聞いてもハーガラは背中を向けたまま逃げようともがいていた。しかし、しばらくして奇妙な音がしているのに気がついた。コポコポとコップの水をこぼす様な。それと同時に静かな歌声もし始めた。