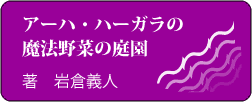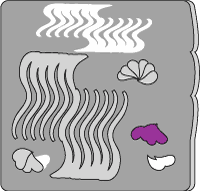3 クイル・ソーダヌスの湖
「そうそう、そうやってうら若き乙女だった、あたしは男たちを引き連れてクイル・ソーダヌスがいるといううわさのある、湖に向かって旅立ったのよ。
なんだか、悲しいようなそれでいて、わくわくするような、不思議な気分だった。
その湖がどこにあるかって?
ここからはずいぶん遠いところ、ガマスル・ファグの町からだって一週間も歩きっぱなしだったわ。」
まだまだ、アーハ・ハーガラ婆さんの野菜たちを前にした独演会は続きがありそうだった。
その時のハーガラは、五人の男たちを連れて、小さな森の中にある、名前もないような小さな湖の近くにたどり着いた。
彼女は望遠鏡で湖の真ん中にある島の辺りを遠くから見た。今は何もいないようだ。遠くの森の中から鳥の声がしていた。
あそこに本当にソーダヌスがいるのだろうか。それには実際に確かめてみるしかないか。分かってはいたけれど。
彼女は二人の男の耳に顔を近づけてささやいた。彼らの名前はヴァスとレントといった。
「ヴァス、私がなんと言ってるか分かった?
もし分かったら「クイル・ソーダヌスは私の物」と言ってみて。」
彼は当惑したような表情を浮かべて、彼女のことを見つめるだけだった。
大丈夫、魔法はまだ切れてない。
彼の耳はわざと聞こえないように加工されていた。とても強い薬を使っていたから、一ヶ月は耳は聞こえるようにならなかっただろう。彼女は満足してうなずくと男たちに折りたたみ式の船を二艘組み立てさせた。
一艘だけをまず、水の上に静かに浮かべた。ハーガラはソイタルを呼んで、彼に最後の確認をした。と言っても、真ん中の島に船でこいで渡るだけのことだったのだが。
あなたはこれで死ぬことになる。それでもいい?ハーガラはそう問いかけそうになった。
だが、必要ない動揺を与えないほうがいい。それにそう言ってしまうと、自分が直接彼の事を殺すことになる気がした。
そう言ってもソイタルは無邪気に笑うだけだっただろうが。その笑顔をハーガラは見たくなかっただけかもしれなかった。
それから彼女たちは岸辺の草むらに身を隠して、ソイタルが湖の真ん中の島の方にゆっくりと漕ぎ渡るの見た。それを見ていると一つの疑問が彼女の中に沸き起こってきた。そういえば、マーメイドの歌だって俘虜の呪文の一種であるに違いない。そうであるなら、自分の今、ソイタルにかけている呪文とかち合ったらどうなるのだろう。
大丈夫、彼にはもともと、弱い俘虜の呪文しか必要としなかったし、その呪文に勝る力をマーメイドが持っていなかったとしたら、そんな力には用はない。
そんなことを考えていると、ソイタルが真ん中の島に到達する前に船を止めたのが分かった。望遠鏡の中に写る、彼の表情は明らかにおかしかった。
恐怖に引きつっているかのようだった。彼が見つめる、水面の近くに小さな影が見えた。
若い女の頭が水面から突き出ていた。
ソイタルはマントの中に隠されたナイフを引き抜くと、水の中に投げ落としてしまった。それはマーメイドのいる方向とは全く違っていた。多分、故意に捨てさせたのだ。ソイタルは驚いたことにそれから、マントを脱ぎ捨て、鎧まで震える手ではずし始めた。
ソイタルはそれもなんのためらいもなく湖の中に投げ込んだ。彼は最後に着ている下着まで全部脱いで全くの素っ裸になってしまった。
望遠鏡を覗く彼女は意外な光景に驚いてしまった。しかし、面白い気もした。マーメイドは一体何を考えているんだろう。
裸のソイタルは手を伸ばすと、マーメイドの美しい手を握りそのまま、自分の体を湖の中に落とした。彼の体は静かに沈んでいき、すぐに見えなくなった。
彼はいつまでたっても浮かび上がってこなかった。そうだ、死んでしまったのだろう。私の思った通りだ。ハーガラは思った。
こうやって死んでみると、ソイタルのことを全く惜しいとは感じなかった。彼は簡単にたぶらかされる単純な精神の持ち主でしかなかったのだ。しかし、なぜかマーメイドの態度にはいらいらした。「あんな風にいい気になりやがって。どちらが上かたっぷり思い知らせてやる。」
計画は次の日に行うことにした。あまりに続けて男がやってきたら、マーメイドだって怪しむに違いがなかった。
とりあえず、マーメイドが男を殺すときにどのようなことをするのかは分かった。明日は耳の聞こえない二人が船に乗って、ソイタルと同じ動作をしさえすれば、マーメイドは自分の魔法がかかったと容易に勘違いするだろう。
楽しみはゆっくりやるのが一番だとハーガラは自分に言い聞かせていた。振り返ると自分の奴隷の男たちが次の命令を待っていた。
彼らの微笑は自分の仲間の死に何の感情も動かされなかったのを示していた。それとも、開放された仲間を本当はうらやんでいたのかもしれなかったのだが。