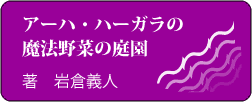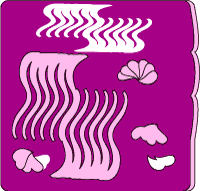4 囚われの人魚
深い水の底でクイル・ソーダヌスは空を見上げていた。信じられないほど遠くにある水面には白い太陽の光がちらちらと揺れていた。でも、彼女のいるあたりにまではその光の力は届いていなかった。あたりは青く澄みきっていてしんとしていた。
彼女はそうやって湖の底から水面に映る太陽の影を眺めるのが好きだった。何本もの白い光の筋が柔らかく、ゆっくり移動していった。
今日は昨日よりかはましな日になりそうだった。
昨日は二度と思い出したくないぐらいの嫌な日だった。また、彼女を捕まえようとした男がやってきたのだ。それもたった一人で。
あの男、ほんとに馬鹿だった。すこし歌ってやったら、自分の中にある悪意を簡単に捨てて、自分の命もすぐに捨ててしまった。たぶんもともと捨てたいぐらいの自分しか持っていなかったのかもしれない。
そんな男がなぜ私のことを捕まえられると思うのだろう。
彼女は湖の底にある、洞窟の中に彼の死体を捨てに行ったときの手触りを思い出して身震いした。ぶよぶよした気味の悪い生き物。死んで当然だと思った。
もっとも、彼の背中に無数に傷の痕があったのが気がかりだったが。多分どこかの牢屋に入れられていたのかもしれない。何か、とんでもない薄汚いことでもして。
そんな物が自分のいる湖に残されているのもなんだか嫌だったが、湖の底の洞窟に入れておけばなぜか嫌な臭いが漏れ出して来ることはなかった。
しばらくしたら、奴だってきれいな真っ白な骨になるだろう。そうしたら、それを削って、何かアクセサリーにしたって面白いかもしれない。
そんなことを考えながら、ソーダヌスはふわふわと玉のように揺れる太陽の影を眺めていた。しかし、その光の影は何者かによってかき乱された。
また、だれか来たんだ。
あの船の影は近くに住む人のものじゃない。彼女ははっきりと悪意を感じた。また、いつものように彼女を侮辱する者がやってきたのに違いがなかった。そんな奴は死んで、骨になるべきだ。そうしてやることが彼らの最もくだらない、欲望とやらから開放してやることにつながる。その方が彼らだって少しは幸せかもしれない。
そう思いながら、彼女はゆっくりと水面に近づいていった。
また、呪いの歌を歌うためにのどを少しだけううんとならした。
大丈夫、また、うまく歌える。私は今までだって誰よりもうまく歌えてきたじゃない。
彼女は気づかれないように船の真下から近づきながら、魔法の歌を歌い始めた。
それは水の中で静かに響いた。
その歌が彼女の水の中で歌う最後の歌になることには全く気づいていなかった。