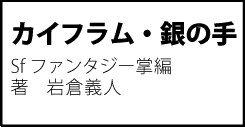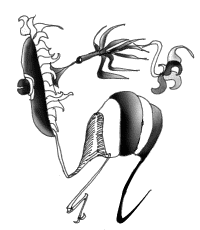
3
「ナミフラの目の涙
甘酢っぱい閉じ込められた霧の跡。
逃げだそうとしている、のたうちまわる、あの目、
ナミフラの目は盲目だ。」
ケフェラートの一人、クサズの無声詩
最後にカイフラムに会ったのはつい三日ほど前の事だった。
彼はいつものように私の仲間を締め殺したあと、私の目の前に立った。
私は恐ろしくて目をつぶって待っていた。彼が私の首を締めるのを。私は彼が生きの根を止めてくれさえすれば、どんなに楽だろうかと思った。なぜ彼は限界を越えて私の事を痛め付けるのだろうか。今日こそ答えを出さなくてはならない。
私は彼が目の前に立っているのを感じながら、目蓋を開いた。彼はまだ、手をかざしていなかった。今日の彼は、痩せこけていて、髪を女の様に長く伸ばし、じっと私の事を見詰めていた。私は今回は首を締められる瞬間を見定めようと待ち構えていた。
しかし、いつまで経っても彼は何もしようとはしなかった。私は彼の口がゆっくり開けられるのを見た。口の奥の方には、舌が喉ちんこのように縮れてうずくまっていた。そのすぐ根本のところに、何か光るものを見付けた。それは真っ黒な色をした針の様だった。
彼は自分の口の中を銀に光っていないほうの指先で示した。私は自分の意識が痺れるようになるのを感じた。それから私は彼の口の中にゆっくり手を伸ばすと、黒い針を捉みだした。やわらかい肉の感触がした。彼はまだ、生きていた。私の目の前で。しかし、それもたぶん終ろうとしているのだ。私は彼を助けなればならなかった。
それ以外に一体どうすれば良かったというのだろう。
私はそれから、彼のひんやりした銀の手をすこしの間触れてから、黒い針を彼の手の平におもいきり突き立てた。手から暖かい血が流れて落ちた。
私はその美しい、とくとくとあふれてくる彼の血をいつまでも眺めていたかった。しかし、その幸せな時間もふいに終りを遂げた。
私の前から彼の姿が消えていたのだ。
しかし、彼とまたすぐに会うときが来るのを私は確信していた。それが今日であることは間違いなかった。彼がそう私に告げたのだ。形に表れない言葉を使って。それをテレパシーなどという、下等な言葉で言い表わしたくなかった。多分私が彼に触れたとき、既に会話は成り立っていたのだ。どのように説明したって分らないかもしれないが。それでも私には十分だった。
彼は何かの理由で私の事を選んだのだった。どんなことがこれから起るにせよ、私はそれに逆らう気はなかった。それとも最初から、カイフラムのような強い力の持ち主には逆らうことなんて無理なのかもしれなかったが、そんなことは今となってはどうだって良かった。
私は彼が姿を現わすべき街で、その二時間前から待っていた。今度は彼の準備も十分整っているはずだ。私は彼に期待したかった。彼は恐しい何かを私に持たらすつもりなのだ。今日彼に会う事は警察の誰にも告げなかった。そんな必要さえもうなくなるのだから。それとも彼がもし生き延びようなどとしているのなら、私は彼の命を終らせるつもりだった。
カイフラムが私の前に姿を見せたとき、私は不思議と恐怖を感じなかった。
その理由はすぐに分った。彼が私の方に手を差し出した時、彼の手には包帯が巻かれていた。彼は銀の手ではない方の手で、それをそっと解き始めた。白い滝の様な包帯が、全て地面に落ちたとき、私は信じ難いものを見た。彼の銀の手が無くなっていたのだ。ちょうど、拳の部分が溶けたように消えていた。
産まれたときから、その場所には何も付いていなかったかのようにさえ見えた。
私は彼のグリーンの瞳を見詰める内に理解した。その拳は切り落されたのなんかではなく、自分から、彼の体から離れたのだ。彼は少し悲しそうな表情をしてから、コートのポケットの中に手を突っこむと、布にきれいに包まれた小さな塊を私に手渡した。
私にはそれが何であるのか分る気がした。それは彼の手なのだ。私は意外にも重いその小さなものが、何十人もの命を奪ってきたことを思いだした。
カイフラムは納得したように、その切り離された手を見詰めながら、うしろを振り向いて、人混みの中に姿を消した。私には、彼を追う気はなかった。別に職務を放棄した訳じゃない。彼がもう少ししたら、死ぬことが分っていた。今だったら、彼の背中に目掛けて銃を撃ったら、彼の肉に弾丸はめり込むだろう。
そう思うと私の手は少し震えた。
しかし、私の腕には彼の銀の手が抱かれているのだ。そして、私は彼が自分の恐しい手を切り離すのを手伝ったのをしっかり覚えていた。私はこの手を一体どうすれば良いのだろうと考えた。
彼が一体なにを望んでいたのだろうと。
私はしばらくその手の包みを撫でてから、一つの決心をした。私が銀の手を持ったまま、ナミフラの目の住む館に向って歩き始めた。
衛兵に私が来たことを告げると、すぐに中に通された。いつものように透明なぶ厚いガラスで出来た扉を十枚潜った。そうすると、とてつもない広い部屋に辿り着いた。そこは優しげな白い光で満ちていた。
部屋ちょうど真ん中あたりに、みすぼらしい寝台が一つだけあった。私はそこに向って歩きながら、自分の足音が、天井のドレープの様な彫刻に反射して戻ってくるのを聴いていた。
私が近づくのに気が付いたのか、その寝台から丸いふくらみが体を起した。ナミフラの目の子供がそこに居たのだ。彼女は執務に疲れると、何時でもそこで眠った。もう一つ奥の部屋にいるとされる、ナミフラの目に常に慰みものにされるのだから、疲れ果てるのも当り前だった。
私は彼女の金髪の輝きを見詰めながら、言った。
「起してしまって申し訳ありません。
しかし、あなたの求めていた物がやっと手に入ったのです。
ナミフラの目もさぞ、お喜びになるでしょう。」
彼女は私の腕に抱かれた、小さな包みを訝しげに見た。また、怯えているのだ。それも無理もない。彼女は自分の力を越えた、死の力をこれから見ることになるのだから。
私はゆっくりと見せつけるようにして、彼女の目の前で汚れた白い包みをほどいた。一体カイフラムは自分の手を包むときどんな悲しみを感じたのだろうと、考えながら。
銀色の手はすっかりちぢこまっていた。そして、私の差した黒い針に付けられた傷から出た血によって、真っ黒に濡れていた。
ナミフラの目の子供はそれを感心したように見詰めた。
「これが、銀の手。
こんな薄汚いのがこの世にあったなんて、信じられないわ。
でも、結局はナミフラの目の力の前に自分自身を生け贄として差しだしたのね。
最後にはどんな事だって正しくなる。
ナミフラの目に見えることだけが結局正しいのよ。」
そう言って彼女は、その黒い塊をさぞ汚れたもののように、指先でつついた。
そのときだった。銀の手がまた動きだしたのだった。
銀の手は喜んで飛び跳ねると、ナミフラの目の子供の首を強く握り締めた。
私は彼女が息絶えるまでの間、静かに目を閉じて、首が締め付けられる音を聴いていた。
私がカイフラムに首を締められていたときも、同じ音がしていたのを思い出しながら。
何分かして、目を開けると、彼女は床に転がっていた。そして、銀の手は役目を終えてほっとしたのか、力を抜いて、彼女のふわふわした髪の毛のとなりに身を横たえた。
「私たちがどんなに逆らおうとしても、だめだったナミフラの目の子供をこうも簡単に殺してしまうなんてな。まったく恐しい力だ。検死官のスイ=ダフにずっと前に貰った、瀕死の体の力を蘇えらせる薬の力がこんな時に役に立つなんて。
いくら強い力を持つ、ナミフラの目だって、彼の力を支えるものを失なってしまってはどうしようもないだろう。」
そう私がつぶやいていると、銀の手は力を使い果たしたのか、形がくずれて、銀の灰になってしまった。
それはナミフラの目の子供の髪の毛の上をうすく灰色に覆った。
私はひざまづくと、彼女の髪をそっと撫でた。別に彼女がいとおしいからそうした訳じゃなかった。そう、私にはその髪の毛にまとわり付いた、銀の手の灰が必要だったのだ。
しばらくすると、私の右手は銀色に輝き始めた。
私は立ちあがると、その手で門番をうまく殺せるのだろうかと考えながら、ガラスの重い戸を開けた。
そして、その戸を閉じてから、振り返って、その半透明な戸を透して向う側を見た。
ちょうど、ナミフラの目のいる部屋の扉がぼんやりと見えた。
私はそれを見てフッと笑ってしまった。
奴は自分の愛する子供を殺されながら、何も出来ないでじっとしているしかないなんて。
ナミフラの目の子供は生きている間にしか、力を跡を継がせる者に引き渡せないなんて、本当に馬鹿げているな。」
中の異変に気付いたのか、外がそうぞうしくなってきた。
私は静かに光る、銀の手を眺めてから、カイフラムの事を思った。
「カイフラムの手に出来た裂け目、それは私の付けた傷。
赤く開かれた、血の瞳。
ナミフラの目を見ようとする瞳。
ナミフラを握り潰そうとする手。
それが銀の手、
それは私の手。」
そこまで言って、やっと私は自分の意思でナミフラの子供を殺したのではないことに気が付いた。
でもその事もあまり気にならなかった。
今やカイフラムは私の一部なのだから。
「カイフラム、銀の手」 終