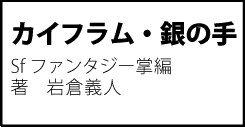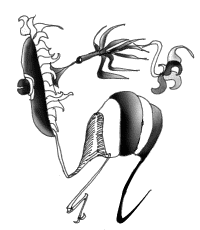
2
話はまだ続きがある。
こんな陰鬱な話を聞いていると、正直嫌になったのではないだろうか。
しかし、それも今日で終わりだ。今日こそカイフラムを殺さねばならない。さもなければ、私の方が殺されるかといっただけの事だ。だから、もう少しだけおしゃべりを許してもらいたい。
最初にカイフラムに会ったあと、私は何度も彼に殺されかけた。しかし、彼は何時も私の事を痛めつけながら、息の根を止める事をしなかった。仲間は常に殺され続けたきたのに。
何時の間にか私の首には彼の締め付けた指の痕がくっきり残って取れなくなってしまった。まるで、死んで変色したヤモリの腹のようだった。私はそれを隠すためにいつも何か布を巻いていなければならなかった。
だが、その首の包帯を見てもその中身がどんなだか知っているのか、誰も何も言わなかった。今日もし、私の方が死ぬのなら、包帯を取って、彼らに見せ付けてやればよかった。
そこまで考えて、やっと彼らが私のあざを恐れる理由が分かった。そのあざを見ると、自分もそのように締め殺されるかもしれない事を突き付けられてしまうからだ。奴らは私の事を生きている死とでも言いたいのだろう。
それから数ヶ月の間、私たちはケフェラートたちに苦しめられ続けた。それでもごくたまに、警察に捕まるケフェラートもいた。それらの下っぱの者たちは、最初は黙秘を続けていたが、最後はナミフラの目の魔力に負けて、いろいろな教団についての隠し事を伝え始めた。
もっとも、彼らの舌は既に縮こまっていたから、紙とペンがその代わりをした。
ナミフラの目はまず彼らに名前を与え直した。脳神経の中に生きているという自覚をむりやりに植え付けたのだ。それにより、とろけてしまいそうなくらいの瞑想性から突然叩き起こされた男は、恐怖にさいなまれて、ナミフラの目の膝元に逃げ込むという具合だった。
しかし、精神に対する過激すぎる暴力が災いしてか、最後には彼らは首を括って死んでしまうというのが、おちだった。
ナミフラの目はそれに対しても涙を流している。とナミフラの目の子供は一度言っていたが、それは本当だろうか。私には分からない。
私とカイフラムの間には確かになんらかの関係があったのかもしれない。
だが、私には彼が何を考えているのか良くわからなかった。彼は私をいつも殺そうとし、なおかつまた、なぜとどめを差さないかといったことを。
彼に最後に会ったのはつい三日ほど前の事だった。