>一章 >二章 >三章 >四章 >五章 六章
ランフォは町中に転がる、兵士達の千切れた頭やロープの様に張り渡された腸などを飛び越えながら、中心の広場に向かった。
丘の上から望遠鏡で殺されていく様子を見ていたときはこれまでに感じたことの無い恐怖を覚えたのがうその様だった。彼がもしうまく口笛が吹けたなら、高らかに吹いただろう。代わりに彼は一気に走り出したかったが、自分の気持ちを押し殺しながら、壊れた建物の壁の穴から辺りをうかがった。確かに彼にとっては今の状態の方が安心なのだ。兵士たちに捕らえられて殺される心配がここではもはや無いのだから。
町の中心の広場は望遠鏡で覗いていたときよりも遥かに広く感じた。竜の炎で消し飛んでしまったのか、サイのように並んでいた破壊銃の群れも黒くただれた鉄の塊になっていた。広場の土は異界の空気と火薬と血の匂いで頭がおかしくなるほどだった汚れていた。
ランフォは裸足の足の裏に血の粘りつくのを感じながら、次元竜が姿を現した空間の割れ目の方に歩いて行った。その割れ目はまだ微かに存在していて、白くミルクのように光っていた。手を伸ばせばその薄い皮膜は簡単に割れてしまうだろう。彼はその向こう側こそが自分の本当の安らげる場所である気がして、目をつぶるとその中に潜り込んで行った。
その中は途方もなく広い空間だった。もっともそこは境目など無いところなのだから、どこよりも狭いということも出来そうだった。ランフォはどうしようもない息苦しさを感じて元の来た扉を探したがそんなものはとっくに消えうせていた。ただ、ミルク色の光の群れが際限も無く流れているのをあきれて見とれているしかなかった。
しかし、その光に目が慣れてくるにつれ、真っ黒な染みがあるのに気付いた。その染みは見ていると悲しくなるようなうごめきをしながらどんどん大きくなっていった。最後にそれは九つに割れた。そして、その九つの巨大な染みの中から細長い腕が伸ばされると、やがてそれは中央で結ばれた。やっとその状態で姿が安定し始めた。
ランフォはそれが、さっき見たケサリーの竜であることに気が付いた。竜の真っ黒な体は血まみれだった。最初は殺した人間の血を自分の体に塗っているのかとも思えたが、やはり、破壊銃で致命傷を受けているようだった。それはそうだ、彼は一度死に、クライマケアによって生き返らせられたのだから。
ランフォは不思議と何の恐怖も感じずに竜の体へと歩み寄っていった。竜の体からクライマケアの香りがするような気さえした。彼がすぐ近くに寄っても、竜はピクリとも動かなかった。死んでしまったのだろうか? 彼は竜の名前を呼びたいと思った。しかし何とと呼べば良いのだろう。薄ぼんやりと光の舞う天井の近くを眺めながら考えていた。
すると、彼のすぐ耳元でささやく声がした。
「クズワーロスプ。それが竜の名前よ。」
クライマケアの声だった。彼女はここに来ているらしかった。姿は見えなかったが、その声を聞いてランフォはとたんに不安を感じ始めた。それに気付いたのか、また声がした。
「怖がらなくてもいいわ。竜も私もあなたを殺したりなんかしない。そう、何時かみたいには。」
ランフォは逃げ出そうと辺りを見回すと、彼の近くには綿のような光が降り積もっていて身動きが取れなかった。彼は渾身の力を込めて鋭い爪を立ててそれを切り裂いた。光は引き裂かれるとき微かな悲鳴を立てた。それを聞いてランフォはびくっと身を震わして、もう一度、竜の方を見た。
すると、竜の九つの体にある、たった一つの頭がさっきまでは地面に転がったままになっていたのだが、ゆっくり持ち上がり始めた。そして、頭が天辺まで持ち上げられたとき、丁度さっきまで頭が隠してした地面に誰かが倒れているのが見えた。真っ黒な肉のベールが上げるられるにつれ、彼女の姿が見えてきたのだ。
ランフォは巨大な竜の体の隙間を急いでかいくぐって走り寄った。仰向けに寝る、彼女の首には赤い血が光っていた。
「クライマケア。大丈夫か? 今、回復の魔法をかけてやるぞ。」
ランフォが自分の精神の器の中に呼びかけて魔法を作り出そうとしていると、彼女はランフォの腕を握ってそれを止めた。
「無駄よ、クリストル。ここでは私たちの魔法は無意味よ。どんなに私たちが精神の器の中に魔法の光を灯そうと思っても、辺りの無限の光たちがすぐに力を吸い取ってしまう。魔法は光に憎しみの力を与えるだけと言ってね。」
クライマケアは薄目を開けていた。ほとんど彼女には力が残っていないようだった。ランフォはどうしようかしばらく迷っていたが、自分の背中の棘に魔法のしずくが数滴残っているのを見つけた。彼はそれをそっと取ると彼女の口の中に流し込んでやった。しばらくして、少しだけ彼女の体が温まり始めたようだった。クライマケアは何度もむせ返ると、身を起こして彼のことを見た。最後に見てから何十年も経っていて、それに全く違った姿をしていたが、それほど変わっているような気がしなかった。彼女は何度も息をついて苦しそうにささやき始めた。
「ランフォ。やっぱり生きていたのね。姿はだいぶ違うけど、私には分かるわ。
あなたは私のことを殺しに来たの? 私はあなたに殺されるのをずっとまってたみたいね。」そう言って彼女は微かに笑った。
「そんなことはないさ、俺が君を殺すなんて。もしそうしようと思ったって私の牙の一本が触れる前に私のちんけな体なんて吹き飛んでいるだろう。
本当は毎日君の心臓をえぐり出せたならどんなにせいせいするだろうかと思い悩んでいたんだけど、なぜか今の君を見ていると憎しみの力が湧いてこないんだ。不思議なもんだ。」
ランフォは手を伸ばすとひび割れた指で彼女の首の血を拭った。しばらくして彼女の口がゆっくり開き始めた。
「なら、一体なにをしに、ここまで来たの? 竜を殺す手伝いでもするつもりだったのかしら。」
「そうだ、何しに来たんだっけ。そうだ、竜の糞が欲しかったんだ。それを使ってゴーレムを作ろうとして・・・。」
「ふふ。あなたはまだ懲りていないのね。一度酷い目に会ったっていうのに。いいわ。あなたにこの子の糞をあげるわ。外の世界でも沢山していただろうけど、それはすぐに消えてしまうの。だけど、ここでした糞なら外に持っていっても消えないはずよ。」
クライマケアが聞いたことも無い奇妙な音節の言葉で竜に話しかけると、竜の体がもぞもぞと震えて向こう側でどさりと音がした。
「気をつけて扱ってね。この子のする最後の糞ですもの。あなたは知っているでしょうけど、この子の魂は今は私の精神の器の中で生きている。でも、私が死んだらそれも終わりよ。私はこの子自身に内側から魂の器を壊されてしまった。私にはこの子を捕らえる権利なんて持っていなかったのに勘違いしてしまったから、この子を怒らせてしまったの。いつかのあなたと似ているわね。私はここでこの子と死ぬけど、あなたはここから出なければならないわね。
だから、この子の最後の力を使ってあなたを元の世界に戻すわ。
さっきの露ありがとう。私の最後に飲んだものとしてはなかなかの味だったわ。」
そう彼女が言い終わる前に竜の尻尾が恐ろしい力で彼の体を締め付けた。そして、開き始めた光のまぶたの中に彼を乱暴に投げ込んだのだった。ランフォはあまりの衝撃に意識を失っていたが、目を覚ましたときには、夕日の光に満ちたケサリーの町に倒れていた。
ふとランフォは自分の手を見ると黒く輝く宝石が握られていた。望遠鏡で見たときのものはすでに消えているだろうが、それよりもずっと小ぶりだった。
ランフォはその人間の頭ぐらいの大きさなのに、ほとんど重さを感じない不思議な石をそっと抱きながら、しばらく、次元の裂け目があった広場を見つめていた。あの向こう側でクライマケアは本当に死んでいるのだろうか。今となっては確かめようも無かった。
それから、彼はゲ・サナとイ・サナのいる小高い丘の方に向かって歩き始めた。
しばらくの間、この石を使ってゴーレムなんて作る気がしないなと思いながら。
ケサリーの竜の糞 終
>homeに戻る
Copyright (C)2004-2018 Yoshito Iwakura
http://lezarakus.nobody.jp/
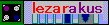
六章 偽りの死
ケサリーの町の中にはもはや死体たちしか住んでいなかった。ランフォはいくら野獣の様な体をしているとは言え、人間たちの脂ぎった内臓には吐き気しか感じなかった。彼が好きなのは野生の小鳥の心臓だった。どのような小鳥でも心臓だけはリンゴのような香りがしていたのだ。そんなことを人間に言っても鈍感な舌はその香りを嗅げないだろうから仕方が無いだろうが。ランフォは町中に転がる、兵士達の千切れた頭やロープの様に張り渡された腸などを飛び越えながら、中心の広場に向かった。
丘の上から望遠鏡で殺されていく様子を見ていたときはこれまでに感じたことの無い恐怖を覚えたのがうその様だった。彼がもしうまく口笛が吹けたなら、高らかに吹いただろう。代わりに彼は一気に走り出したかったが、自分の気持ちを押し殺しながら、壊れた建物の壁の穴から辺りをうかがった。確かに彼にとっては今の状態の方が安心なのだ。兵士たちに捕らえられて殺される心配がここではもはや無いのだから。
町の中心の広場は望遠鏡で覗いていたときよりも遥かに広く感じた。竜の炎で消し飛んでしまったのか、サイのように並んでいた破壊銃の群れも黒くただれた鉄の塊になっていた。広場の土は異界の空気と火薬と血の匂いで頭がおかしくなるほどだった汚れていた。
ランフォは裸足の足の裏に血の粘りつくのを感じながら、次元竜が姿を現した空間の割れ目の方に歩いて行った。その割れ目はまだ微かに存在していて、白くミルクのように光っていた。手を伸ばせばその薄い皮膜は簡単に割れてしまうだろう。彼はその向こう側こそが自分の本当の安らげる場所である気がして、目をつぶるとその中に潜り込んで行った。
その中は途方もなく広い空間だった。もっともそこは境目など無いところなのだから、どこよりも狭いということも出来そうだった。ランフォはどうしようもない息苦しさを感じて元の来た扉を探したがそんなものはとっくに消えうせていた。ただ、ミルク色の光の群れが際限も無く流れているのをあきれて見とれているしかなかった。
しかし、その光に目が慣れてくるにつれ、真っ黒な染みがあるのに気付いた。その染みは見ていると悲しくなるようなうごめきをしながらどんどん大きくなっていった。最後にそれは九つに割れた。そして、その九つの巨大な染みの中から細長い腕が伸ばされると、やがてそれは中央で結ばれた。やっとその状態で姿が安定し始めた。
ランフォはそれが、さっき見たケサリーの竜であることに気が付いた。竜の真っ黒な体は血まみれだった。最初は殺した人間の血を自分の体に塗っているのかとも思えたが、やはり、破壊銃で致命傷を受けているようだった。それはそうだ、彼は一度死に、クライマケアによって生き返らせられたのだから。
ランフォは不思議と何の恐怖も感じずに竜の体へと歩み寄っていった。竜の体からクライマケアの香りがするような気さえした。彼がすぐ近くに寄っても、竜はピクリとも動かなかった。死んでしまったのだろうか? 彼は竜の名前を呼びたいと思った。しかし何とと呼べば良いのだろう。薄ぼんやりと光の舞う天井の近くを眺めながら考えていた。
すると、彼のすぐ耳元でささやく声がした。
「クズワーロスプ。それが竜の名前よ。」
クライマケアの声だった。彼女はここに来ているらしかった。姿は見えなかったが、その声を聞いてランフォはとたんに不安を感じ始めた。それに気付いたのか、また声がした。
「怖がらなくてもいいわ。竜も私もあなたを殺したりなんかしない。そう、何時かみたいには。」
ランフォは逃げ出そうと辺りを見回すと、彼の近くには綿のような光が降り積もっていて身動きが取れなかった。彼は渾身の力を込めて鋭い爪を立ててそれを切り裂いた。光は引き裂かれるとき微かな悲鳴を立てた。それを聞いてランフォはびくっと身を震わして、もう一度、竜の方を見た。
すると、竜の九つの体にある、たった一つの頭がさっきまでは地面に転がったままになっていたのだが、ゆっくり持ち上がり始めた。そして、頭が天辺まで持ち上げられたとき、丁度さっきまで頭が隠してした地面に誰かが倒れているのが見えた。真っ黒な肉のベールが上げるられるにつれ、彼女の姿が見えてきたのだ。
ランフォは巨大な竜の体の隙間を急いでかいくぐって走り寄った。仰向けに寝る、彼女の首には赤い血が光っていた。
「クライマケア。大丈夫か? 今、回復の魔法をかけてやるぞ。」
ランフォが自分の精神の器の中に呼びかけて魔法を作り出そうとしていると、彼女はランフォの腕を握ってそれを止めた。
「無駄よ、クリストル。ここでは私たちの魔法は無意味よ。どんなに私たちが精神の器の中に魔法の光を灯そうと思っても、辺りの無限の光たちがすぐに力を吸い取ってしまう。魔法は光に憎しみの力を与えるだけと言ってね。」
クライマケアは薄目を開けていた。ほとんど彼女には力が残っていないようだった。ランフォはどうしようかしばらく迷っていたが、自分の背中の棘に魔法のしずくが数滴残っているのを見つけた。彼はそれをそっと取ると彼女の口の中に流し込んでやった。しばらくして、少しだけ彼女の体が温まり始めたようだった。クライマケアは何度もむせ返ると、身を起こして彼のことを見た。最後に見てから何十年も経っていて、それに全く違った姿をしていたが、それほど変わっているような気がしなかった。彼女は何度も息をついて苦しそうにささやき始めた。
「ランフォ。やっぱり生きていたのね。姿はだいぶ違うけど、私には分かるわ。
あなたは私のことを殺しに来たの? 私はあなたに殺されるのをずっとまってたみたいね。」そう言って彼女は微かに笑った。
「そんなことはないさ、俺が君を殺すなんて。もしそうしようと思ったって私の牙の一本が触れる前に私のちんけな体なんて吹き飛んでいるだろう。
本当は毎日君の心臓をえぐり出せたならどんなにせいせいするだろうかと思い悩んでいたんだけど、なぜか今の君を見ていると憎しみの力が湧いてこないんだ。不思議なもんだ。」
ランフォは手を伸ばすとひび割れた指で彼女の首の血を拭った。しばらくして彼女の口がゆっくり開き始めた。
「なら、一体なにをしに、ここまで来たの? 竜を殺す手伝いでもするつもりだったのかしら。」
「そうだ、何しに来たんだっけ。そうだ、竜の糞が欲しかったんだ。それを使ってゴーレムを作ろうとして・・・。」
「ふふ。あなたはまだ懲りていないのね。一度酷い目に会ったっていうのに。いいわ。あなたにこの子の糞をあげるわ。外の世界でも沢山していただろうけど、それはすぐに消えてしまうの。だけど、ここでした糞なら外に持っていっても消えないはずよ。」
クライマケアが聞いたことも無い奇妙な音節の言葉で竜に話しかけると、竜の体がもぞもぞと震えて向こう側でどさりと音がした。
「気をつけて扱ってね。この子のする最後の糞ですもの。あなたは知っているでしょうけど、この子の魂は今は私の精神の器の中で生きている。でも、私が死んだらそれも終わりよ。私はこの子自身に内側から魂の器を壊されてしまった。私にはこの子を捕らえる権利なんて持っていなかったのに勘違いしてしまったから、この子を怒らせてしまったの。いつかのあなたと似ているわね。私はここでこの子と死ぬけど、あなたはここから出なければならないわね。
だから、この子の最後の力を使ってあなたを元の世界に戻すわ。
さっきの露ありがとう。私の最後に飲んだものとしてはなかなかの味だったわ。」
そう彼女が言い終わる前に竜の尻尾が恐ろしい力で彼の体を締め付けた。そして、開き始めた光のまぶたの中に彼を乱暴に投げ込んだのだった。ランフォはあまりの衝撃に意識を失っていたが、目を覚ましたときには、夕日の光に満ちたケサリーの町に倒れていた。
ふとランフォは自分の手を見ると黒く輝く宝石が握られていた。望遠鏡で見たときのものはすでに消えているだろうが、それよりもずっと小ぶりだった。
ランフォはその人間の頭ぐらいの大きさなのに、ほとんど重さを感じない不思議な石をそっと抱きながら、しばらく、次元の裂け目があった広場を見つめていた。あの向こう側でクライマケアは本当に死んでいるのだろうか。今となっては確かめようも無かった。
それから、彼はゲ・サナとイ・サナのいる小高い丘の方に向かって歩き始めた。
しばらくの間、この石を使ってゴーレムなんて作る気がしないなと思いながら。
ケサリーの竜の糞 終
>homeに戻る
Copyright (C)2004-2018 Yoshito Iwakura
http://lezarakus.nobody.jp/
