>一章 二章 >三章 >四章 >五章 >六章
彼はその声を聞いてほっとため息をつくと、足を止め、また呼びかけた。今度は「ギッツ・ゲッ・イー」と言った。それが彼らが理解できる僅かな種類の言葉の一つだった。数週間前にガマスル・ファグの町の郊外にある家を出てから、彼らとしか話をしていなかったから、ランフォはたまには人間とも話してみたいと切実に願うようになっていた。
もうそろそろ、ケサリーの町の近くの街道町の近くまで来ているはずだった。もし、彼が街道に沿って町に向かっていたとしたら、とうにケサリーに到着していただろう、だが、彼はあえてそうはしなかった。万が一、街道を使う、王の兵士達の群れや、盗賊や放浪民の一団に出くわしたら、酷い目に合わされるのは目に見えていた。
彼だって、魔法使いの端くれなのだから言うことを聞かせれば良いではないかと、思われるかもしれないが、王の兵士がより強力な魔術師を連れていたら一体どうなるだろうか、また、盗賊の一人や二人だったら、眠らせているうちに殴りかかれば何とかなるだろうが、それ以上人数が居たとしたら、彼にはどうしたって太刀打ちできるわけがなかったのだ。
だから、彼が旅をするときは、決まって街道から数百メートル引っ込んだところの藪や森の中を行くことにしていた。それに野獣のような彼の体は、茨やら笹やらが絡まった中に居るときのほうが町に居るときより、ずっと安心感を覚えるからでもあった。
彼は数歩進むと森の下藪の中から抜け出て、小さな草地の光の中に立っていた。
「今日はここで休むとするか。」彼は肩に食い込んでいた重い背負い袋を地面の草の上に投げ出すと、自分の体もそこに横たえた。目をつぶるとまだのどの奥がチクチクと痛んだ。まだ、あのゴーレムの仕込んだ何かの牙で出来た傷が癒えなかったのだ。
「あの安っぽい解毒呪文ではやっぱりだめか。」彼がずっと前に街道町の蚤の市で見つけた、初級の治癒呪文集のことを罵ってもしかたがなかった。彼がそれを買ったのは昔彼がいた、ガマスル・ファグの町の中の魔法訓練所「イガメークのツタ」のことを思い出したからだった。
むしろ、彼が得意とするのは毒を治癒するよりも毒を負わせることだった。そのことに掛けてなら彼は自信がすこしばかりあった。この間も、街道町に行ったときに、どこかの都会からやって来た、威張り腐った二人連れに毒を盛って酷い目にあわせてやった。今頃彼らは白黒の世界で生きていることだろう。ランフォが盛った毒は飲んだ人の目から色の世界を取り除く毒薬だった。それは「犬の目」と呼ばれる血の色の花をすりつぶして出来るのだったが、そんなものを好んで作るのも彼ぐらいだっただろう。
そんなことを思い出しながら、草の絨毯の上で疲れでうつらうつらしていると、何かが彼をそっとつついた。まぶたを開けると、二匹の奇妙なカカシのようなものが立っていた。しかし、それは四本足で胴体や頭はむくむくとした緑色の塊で出来ていて、所々、鋭い棘が顔を覗かせていた。ちょうど子馬ぐらいの体の大きさだった。
ランフォは驚かせないようにそっと立ち上がると、長細い首の棘の生えていないところを見つけてそこをそっとなでた。
それが、彼の作った魔法生物ソチナ・ズムのゲ・サナとイ・サナだった。彼らはなでられると恥ずかしがって木で出来た足を交差させ、擦り合わせて、不思議な音を出した。ギチン、クチンとそれは言った。ちょうどコオロギなどの虫が音で交信するときの原理に良く似ていた。そうやって彼らは話をするのだ。
植物だけで作られた、彼らの頭には口がなかった。耳さえもなかった、ならば、どうやって彼らは音を聞くのだろうか? 厳密に言うならば、彼らは全身で音を聞いていると言えるだろう。植物というものは元来、神経節がむき出しになっているようなものなので、全身で聞くことが出来得るというわけだった。ただ、魔法生物にする際にその感度を桁違いに上げる加工を施しているというのは言うまでもないことだ。
その事はまた、彼らの体の全身が目でもあるということをも意味していた。しかし、ソチナ・ズムにおいては植物の光受容感覚器の本来の機能である光合成の方に強い役割が割り振られていた。彼らの見る世界はぼんやりと霞がかっているだろう。だが、彼らの見通しが利かない林の中での動くものに対する感覚は並外れたものだった。それに、足や体が華奢な割りに動きがすばやかったから、今回の様な藪の中を行く、途方もない長距離の旅のお供にはぴったりだった。
ソチナ・ズムは魔法的な力で動かされているとは言え、死んだ状態から蘇らせられている訳ではない。それは生きている植物の性質を持った動物のようなものだった。とは言え、頭や胴体のサボテンで出来たところはすでにしなびかけてしまっていた。
もともと、彼らがサボテンだったときは頭にそれぞれ白い花と赤い花を咲かせていた。それから取って、ランフォは彼らにゲ・サナ(赤い花)イ・サナ(白い花)と名付けた。
ランフォは静かだが暗い性格ではない彼らといっしょにいると安らかな気分になっていくのをいつも感じた。残念なのは彼らの魔法生物としての寿命がそれほど長くないことだった。所詮、切花は切り取られた命だということなのだろうか。
ランフォは彼らの背中に括り付けられた重い荷物の紐を解いた。
「ゲ・サナ、イ・サナ。お前たちの頭にはきれいな花さえ咲いていたのにな。
せめて、午後の日光でもたっぷり浴びてくれ。それが、お前たちにとって何よりのご馳走なのだから。」
ランフォはテントを張りながら彼らを見ると、二匹並んで甘い太陽の光の蜜を出来るだけ浴びようとして、光に背中を向けて身じろぎもせず立ちすくんでいた。
もう少しで日が落ちると、彼らの長い休息が始まる。その間にランフォは古びた小さな手帳を引っ張り出して、考え事でもしようと思っていた。面白い新しい魔法を思いつけるのは決まってこういうときだからだった。
その日の晩、ランフォは小さな焚き火を眺めながら思った。なぜ、自分の作るゴーレムはこんなに何度も人を殺そうとするのだろうかと。
彼は自分自身が他人を苦しめたり、怪我を負わせたりすることには何の疑問も抱いたことはなかった。それに彼のゴーレムが自分の命令で誰かを殺したとしたって返って痛快にしか思わなかっただろう。だが、彼らはなぜ自分の命令に背いたのだろうか、自由とやらが欲しかったのだろうか?
彼らが主人を殺すことは自殺するのと同じことだった。自分の仮の生命が存在する根拠が主人の中にあるのだから。
一度目、彼のゴーレムが彼の意思に反して人を殺そうとしたのは、彼が魔法訓練所「イガメークのツタ」に居たときだった。今から三十年は前のことだ。事件が起きた時、ランフォはそこに入学してまだ二年しか経っていなかった。だが、すでに頭の切れでは先輩たちを出し抜くようになっていた。それにとてもきれいな顔立ちをしていたからか、ある女性の教官の魔法使いに気に入られて、彼女の部屋の中の魔法書を好きなだけ見ることが出来た。
彼は古代のゴーレムの製造法の本を読むうちにすばらしいことが書いてあるのを見つけた。
その本にはゴーレムを動物の糞と土を混ぜて作れば強靭なゴーレムが出来ると書かれていた。それはイガメークのツタで教えられていたこととは違っていた。そこでは、土と腐敗した果物などを混ぜて作るのが良いとされていた。しかし、そのゴーレムはたった三日で元の土の山に戻ってしまった。口もろくに利けないどうしようもないうすのろがランフォは嫌いだった。何か教官たちは隠しているのに違いない。彼らは危険性を無闇に恐れているのだろう。それとも生徒たちに力を握らせたくないだけなのかもしれないが。ランフォはなぜか自分ならすさまじい力だって制御できるんじゃないかという気がした。それに、制御できなくなってどうしようもなくなってしまっても、どうでもいい気さえした。
まずは実験あるのみだった。手始めに何かの糞を山ほど手に入れよう。しかし、町の中になんて動物の糞があるはずないじゃないか。いや、待てよ、自然と糞が集まっている場所がある。そこから盗めば手っ取り早いな。ランフォは町の外れにある公衆便所に目を付けた。動物の糞を使うところを人間の糞にしてしまうなんて侮蔑的でなんて楽しいんだろうと、ランフォは女の教官の部屋で一人でひざをたたいて喜んだ。
それにもっとすばらしいことを思いついた。
町の博物館にある、恐ろしく昔に絶滅した生物の糞石を砕いてゴーレムの原料とすればきっとものすごい奴が出来るはずだ。それを人間の糞に少し混ぜてやろう。後はどうやって博物館の鍵を手に入れるかだ。それには、彼の虜になっている、四十過ぎのおばさんの教官が役に立ってくれるに違いなかった。あの糞真面目で通っているクライマケア・シカレナが一番好きなものが若い男の肉体だと知ったら、全ての生徒は度肝を抜かれるだろうな。ランフォはクライマケアの部屋のベッドの布団に包まりながら彼女が帰ってくるのを待った。大声で笑いたいのを必死でこらえるために何度も枕に頭を埋めなければならなかった程だった。枕はほんのりと安っぽい香水の匂いがしていた。しかし、そんなものはすぐにかき消されてしまうだろう。これからの汗の香りで。
一週間が過ぎて、首尾よくクライマケアから博物館の鍵を受け取ったランフォは、一人で小さなランプの明かりを頼りに糞石を探した。真夜中の博物館には案の定、誰もいないようだった。普段なら陰気臭く感じてしまう部屋の空気さえ、逆に芳しく思えた。さて、化石のコーナーに目指すものは眠るはずだ。
それから彼はすすけた戸棚を何度も開けたり閉めたりしていたが、一つの青く光る小さな石を見つけた。暗闇の中でラベルに目を近づけて見た。ランプの光に始祖鳥という文字が浮かんでいた。
「始祖鳥の糞石か。悪くないな。もしかしてゴーレムでも空が飛べるようになるかもしれないな。」彼は自分のまだ見ぬ土の巨人が赤い羽毛を体に生やし、翼を広げているのを思い描いた。彼は石をポケットに滑り込ませてから、もう一度触って、ちゃんと入っているのを確かめると、すばやくそこを立ち去った。
また、クライマケアにお礼をしなければいけないのが億劫に感じた。早く実験を開始したくてたまらなかったのだ。しかし、彼女の実験室を使えなくなったら全ては水の泡だ。彼はふと、なぜ、彼女は自分のしようとしていることの全てを受け入れているのだろうかと疑問に思った。だが、そんなことは些細な事に違いないことにすぐ気が付いた。面白いことを出来るうちに何でもやることだけ考えるのが重要だと、ランフォは自分に言い聞かせていた。
>三章に進む >homeに戻る
Copyright (C)2004-2018 Yoshito Iwakura
http://lezarakus.nobody.jp/
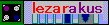
二章 赤い花と白い花
目の前に被さる、緑の葉の群れをすばやく避けながら、ランフォは「ゲ・ゲッ、イ・イー」と見通しのきかないやぶの中に時折呼びかけた。すると、そのたびに、彼の近くの茂みの中から、フチッツ、ピッチと弾けるような不思議な声がしていた。それは彼の連れている、サボテンと木で作り上げた魔性生物の声だった。彼はその声を聞いてほっとため息をつくと、足を止め、また呼びかけた。今度は「ギッツ・ゲッ・イー」と言った。それが彼らが理解できる僅かな種類の言葉の一つだった。数週間前にガマスル・ファグの町の郊外にある家を出てから、彼らとしか話をしていなかったから、ランフォはたまには人間とも話してみたいと切実に願うようになっていた。
もうそろそろ、ケサリーの町の近くの街道町の近くまで来ているはずだった。もし、彼が街道に沿って町に向かっていたとしたら、とうにケサリーに到着していただろう、だが、彼はあえてそうはしなかった。万が一、街道を使う、王の兵士達の群れや、盗賊や放浪民の一団に出くわしたら、酷い目に合わされるのは目に見えていた。
彼だって、魔法使いの端くれなのだから言うことを聞かせれば良いではないかと、思われるかもしれないが、王の兵士がより強力な魔術師を連れていたら一体どうなるだろうか、また、盗賊の一人や二人だったら、眠らせているうちに殴りかかれば何とかなるだろうが、それ以上人数が居たとしたら、彼にはどうしたって太刀打ちできるわけがなかったのだ。
だから、彼が旅をするときは、決まって街道から数百メートル引っ込んだところの藪や森の中を行くことにしていた。それに野獣のような彼の体は、茨やら笹やらが絡まった中に居るときのほうが町に居るときより、ずっと安心感を覚えるからでもあった。
彼は数歩進むと森の下藪の中から抜け出て、小さな草地の光の中に立っていた。
「今日はここで休むとするか。」彼は肩に食い込んでいた重い背負い袋を地面の草の上に投げ出すと、自分の体もそこに横たえた。目をつぶるとまだのどの奥がチクチクと痛んだ。まだ、あのゴーレムの仕込んだ何かの牙で出来た傷が癒えなかったのだ。
「あの安っぽい解毒呪文ではやっぱりだめか。」彼がずっと前に街道町の蚤の市で見つけた、初級の治癒呪文集のことを罵ってもしかたがなかった。彼がそれを買ったのは昔彼がいた、ガマスル・ファグの町の中の魔法訓練所「イガメークのツタ」のことを思い出したからだった。
むしろ、彼が得意とするのは毒を治癒するよりも毒を負わせることだった。そのことに掛けてなら彼は自信がすこしばかりあった。この間も、街道町に行ったときに、どこかの都会からやって来た、威張り腐った二人連れに毒を盛って酷い目にあわせてやった。今頃彼らは白黒の世界で生きていることだろう。ランフォが盛った毒は飲んだ人の目から色の世界を取り除く毒薬だった。それは「犬の目」と呼ばれる血の色の花をすりつぶして出来るのだったが、そんなものを好んで作るのも彼ぐらいだっただろう。
そんなことを思い出しながら、草の絨毯の上で疲れでうつらうつらしていると、何かが彼をそっとつついた。まぶたを開けると、二匹の奇妙なカカシのようなものが立っていた。しかし、それは四本足で胴体や頭はむくむくとした緑色の塊で出来ていて、所々、鋭い棘が顔を覗かせていた。ちょうど子馬ぐらいの体の大きさだった。
ランフォは驚かせないようにそっと立ち上がると、長細い首の棘の生えていないところを見つけてそこをそっとなでた。
それが、彼の作った魔法生物ソチナ・ズムのゲ・サナとイ・サナだった。彼らはなでられると恥ずかしがって木で出来た足を交差させ、擦り合わせて、不思議な音を出した。ギチン、クチンとそれは言った。ちょうどコオロギなどの虫が音で交信するときの原理に良く似ていた。そうやって彼らは話をするのだ。
植物だけで作られた、彼らの頭には口がなかった。耳さえもなかった、ならば、どうやって彼らは音を聞くのだろうか? 厳密に言うならば、彼らは全身で音を聞いていると言えるだろう。植物というものは元来、神経節がむき出しになっているようなものなので、全身で聞くことが出来得るというわけだった。ただ、魔法生物にする際にその感度を桁違いに上げる加工を施しているというのは言うまでもないことだ。
その事はまた、彼らの体の全身が目でもあるということをも意味していた。しかし、ソチナ・ズムにおいては植物の光受容感覚器の本来の機能である光合成の方に強い役割が割り振られていた。彼らの見る世界はぼんやりと霞がかっているだろう。だが、彼らの見通しが利かない林の中での動くものに対する感覚は並外れたものだった。それに、足や体が華奢な割りに動きがすばやかったから、今回の様な藪の中を行く、途方もない長距離の旅のお供にはぴったりだった。
ソチナ・ズムは魔法的な力で動かされているとは言え、死んだ状態から蘇らせられている訳ではない。それは生きている植物の性質を持った動物のようなものだった。とは言え、頭や胴体のサボテンで出来たところはすでにしなびかけてしまっていた。
もともと、彼らがサボテンだったときは頭にそれぞれ白い花と赤い花を咲かせていた。それから取って、ランフォは彼らにゲ・サナ(赤い花)イ・サナ(白い花)と名付けた。
ランフォは静かだが暗い性格ではない彼らといっしょにいると安らかな気分になっていくのをいつも感じた。残念なのは彼らの魔法生物としての寿命がそれほど長くないことだった。所詮、切花は切り取られた命だということなのだろうか。
ランフォは彼らの背中に括り付けられた重い荷物の紐を解いた。
「ゲ・サナ、イ・サナ。お前たちの頭にはきれいな花さえ咲いていたのにな。
せめて、午後の日光でもたっぷり浴びてくれ。それが、お前たちにとって何よりのご馳走なのだから。」
ランフォはテントを張りながら彼らを見ると、二匹並んで甘い太陽の光の蜜を出来るだけ浴びようとして、光に背中を向けて身じろぎもせず立ちすくんでいた。
もう少しで日が落ちると、彼らの長い休息が始まる。その間にランフォは古びた小さな手帳を引っ張り出して、考え事でもしようと思っていた。面白い新しい魔法を思いつけるのは決まってこういうときだからだった。
その日の晩、ランフォは小さな焚き火を眺めながら思った。なぜ、自分の作るゴーレムはこんなに何度も人を殺そうとするのだろうかと。
彼は自分自身が他人を苦しめたり、怪我を負わせたりすることには何の疑問も抱いたことはなかった。それに彼のゴーレムが自分の命令で誰かを殺したとしたって返って痛快にしか思わなかっただろう。だが、彼らはなぜ自分の命令に背いたのだろうか、自由とやらが欲しかったのだろうか?
彼らが主人を殺すことは自殺するのと同じことだった。自分の仮の生命が存在する根拠が主人の中にあるのだから。
一度目、彼のゴーレムが彼の意思に反して人を殺そうとしたのは、彼が魔法訓練所「イガメークのツタ」に居たときだった。今から三十年は前のことだ。事件が起きた時、ランフォはそこに入学してまだ二年しか経っていなかった。だが、すでに頭の切れでは先輩たちを出し抜くようになっていた。それにとてもきれいな顔立ちをしていたからか、ある女性の教官の魔法使いに気に入られて、彼女の部屋の中の魔法書を好きなだけ見ることが出来た。
彼は古代のゴーレムの製造法の本を読むうちにすばらしいことが書いてあるのを見つけた。
その本にはゴーレムを動物の糞と土を混ぜて作れば強靭なゴーレムが出来ると書かれていた。それはイガメークのツタで教えられていたこととは違っていた。そこでは、土と腐敗した果物などを混ぜて作るのが良いとされていた。しかし、そのゴーレムはたった三日で元の土の山に戻ってしまった。口もろくに利けないどうしようもないうすのろがランフォは嫌いだった。何か教官たちは隠しているのに違いない。彼らは危険性を無闇に恐れているのだろう。それとも生徒たちに力を握らせたくないだけなのかもしれないが。ランフォはなぜか自分ならすさまじい力だって制御できるんじゃないかという気がした。それに、制御できなくなってどうしようもなくなってしまっても、どうでもいい気さえした。
まずは実験あるのみだった。手始めに何かの糞を山ほど手に入れよう。しかし、町の中になんて動物の糞があるはずないじゃないか。いや、待てよ、自然と糞が集まっている場所がある。そこから盗めば手っ取り早いな。ランフォは町の外れにある公衆便所に目を付けた。動物の糞を使うところを人間の糞にしてしまうなんて侮蔑的でなんて楽しいんだろうと、ランフォは女の教官の部屋で一人でひざをたたいて喜んだ。
それにもっとすばらしいことを思いついた。
町の博物館にある、恐ろしく昔に絶滅した生物の糞石を砕いてゴーレムの原料とすればきっとものすごい奴が出来るはずだ。それを人間の糞に少し混ぜてやろう。後はどうやって博物館の鍵を手に入れるかだ。それには、彼の虜になっている、四十過ぎのおばさんの教官が役に立ってくれるに違いなかった。あの糞真面目で通っているクライマケア・シカレナが一番好きなものが若い男の肉体だと知ったら、全ての生徒は度肝を抜かれるだろうな。ランフォはクライマケアの部屋のベッドの布団に包まりながら彼女が帰ってくるのを待った。大声で笑いたいのを必死でこらえるために何度も枕に頭を埋めなければならなかった程だった。枕はほんのりと安っぽい香水の匂いがしていた。しかし、そんなものはすぐにかき消されてしまうだろう。これからの汗の香りで。
一週間が過ぎて、首尾よくクライマケアから博物館の鍵を受け取ったランフォは、一人で小さなランプの明かりを頼りに糞石を探した。真夜中の博物館には案の定、誰もいないようだった。普段なら陰気臭く感じてしまう部屋の空気さえ、逆に芳しく思えた。さて、化石のコーナーに目指すものは眠るはずだ。
それから彼はすすけた戸棚を何度も開けたり閉めたりしていたが、一つの青く光る小さな石を見つけた。暗闇の中でラベルに目を近づけて見た。ランプの光に始祖鳥という文字が浮かんでいた。
「始祖鳥の糞石か。悪くないな。もしかしてゴーレムでも空が飛べるようになるかもしれないな。」彼は自分のまだ見ぬ土の巨人が赤い羽毛を体に生やし、翼を広げているのを思い描いた。彼は石をポケットに滑り込ませてから、もう一度触って、ちゃんと入っているのを確かめると、すばやくそこを立ち去った。
また、クライマケアにお礼をしなければいけないのが億劫に感じた。早く実験を開始したくてたまらなかったのだ。しかし、彼女の実験室を使えなくなったら全ては水の泡だ。彼はふと、なぜ、彼女は自分のしようとしていることの全てを受け入れているのだろうかと疑問に思った。だが、そんなことは些細な事に違いないことにすぐ気が付いた。面白いことを出来るうちに何でもやることだけ考えるのが重要だと、ランフォは自分に言い聞かせていた。
>三章に進む >homeに戻る
Copyright (C)2004-2018 Yoshito Iwakura
http://lezarakus.nobody.jp/
