>一章 >二章 >三章 >四章 五章 >六章
ランフォが覗き込んだ望遠鏡の視界の中に、蟻のようにうごめく人間たちの姿が映し出された。そんな非力な者たちが、ケサリーに住む巨大な力を持つ竜を倒そうというのだからランフォは思わず笑ってしまった。望遠鏡から目を離すとすでに辺りは夕闇に沈もうとしていた。遥か彼方の兵士達のテントの群れの方では小さな煙がもくもくと上がり始めた。夕食の準備を始めたのだろう。そんな風に堂々と火が使えるのがうらやましかった。
竜はランフォが火を焚こうが気にしなかっただろうが、兵士たちはそんなことはないに違いない。いくら間抜けな彼らだって、ランフォがすぐ近くの丘にひそんで彼らの行動の一部始終を見張っていることに気付くだろう。
ランフォが、そのケサリーの町を見下ろす丘にたどり着いてからすでに二週間が過ぎようとしていた。この前の小さな村からここにやってくるまでの間にはさも恐ろしい、魔術師たちのわなが待ち構えているのだろうと、震えながら藪の中を潜り抜けて来たのだが、心配するようなことは何も起こらなかった。
もしかすると、村からケサリーの町への最短の道から大きく迂回してやって来たのが功を奏したのかもしれなかったが。結局ここにたどり着くまでに五日もかかってしまった。まっすぐ道を進めれば、たった半日ぐらいで着くことが出来るのだが、見つかって捕らえられて八つ裂きにされるよりはずっとましだった。
ランフォは日陰の魔法使いが残していった古い地図を頼りにここまで、やって来た。もちろん地図には街道から離れた森の中の様子のことなど全くと言っていいほど何も書かれていなかったが、それでも十分役に立った。今彼の居る小高い丘の存在もその地図に書かれていた。もしここが使えたら、町を一望出来るだろう。それに竜がいくら力強くてもそこまでは攻撃は届かないだろうし、うまくすれば兵士や魔術師たちとの戦いだって見物できるかもしれない。ランフォは地図を見ながら思った。
そういうわけで、その丘は町を盗み見るには絶好の場所だったが、それは王の兵士たちにとっても同じことだ。もし、そこに兵士たちがすでにいたとしたら、また別の場所を探さなくてはいけない。しかし、ランフォがその丘を注意深く調べても、かなり長い間人間の立ち入った形跡はなかった。兵士たちはやはり間抜けかとも思えたが、それは彼らの自信の表れであるともいえるだろう。彼らは無駄な労力をかけない主義らしい。余計そのために命を落とす確率が高まっているというのに、気にしないとでもいうのだろうか。
ランフォは火が起こせないので仕方なしにごそごそと袋の中から、石の様に硬くなった干し肉を一切れ取り出すと舌の上に乗せて溶かし始めた。ゲ・サナとイ・サナは彼の後ろの草陰ですでに眠りに就いていた。ほんのかすかな、時折聞こえる彼らの身じろぐ音を聞いていると、ランフォはほっとして大きくあくびをした。
やって来たばかりの時はこれからどんなことが起こるのだろうとわくわくして夜通し見張っていたが、ここ二週間たいした動きが見られないので、いくら辛抱強いランフォであっても正直飽きてしまった。竜は一体どこにいるのだろうか。しかし、兵士たちがそこから動かない様子を見ると、竜は近い将来再びそこに現れることを確信しているのに違いなかった。
彼は口の中でやっと少し肉汁の香りがし始めた干し肉をぐっと飲み干すと、退屈しのぎにまた、望遠鏡を覗き始めた。今度はもう少し倍率を高くしてみよう。その望遠鏡は特別な魔工学品ともいえる物だった。ほんの少し彼が精神を集中させ魔法力を覗き口に注ぎ込むととたんに視界がはっきりして、遠くの兵士の表情まで手に取るように良く見えるようになった。
彼らのケサリーの竜を倒すための罠は単純そのものだったが、その方が返って良かったかもしれなかった。彼らの持つ巨大な牛ぐらいの大きさの大砲の十数門は、半円形に配置され、その中央の点に火力が集中するようになっていた。
その点に必ず竜が突然姿を現すことが分かっているから、そのような配置になっているのだ。ランフォはケサリーの竜の正体は次元竜の一種であるに違いないと踏んでいた。少なくとも兵士たちを統率する魔術師たちも同じように考えているのだろう、そうでなければもっと違った作戦を取るはずだった。
次元竜と呼ばれるものは特異な性質をもった生き物の一種だった。それは生物というよりも生きた光とか、生きた次元の歪みとかに近いものだった。普通の常識でいうと空間そのものが生きるはずはないだろうということになってしまうが、魔法的な力が空間の一点に集まればそういうこともありうることだとされていた。それはイガメークのツタでも言われていることだったし、日陰の魔法使いの持っていた古い魔道書にもそう書かれていた。
そして、次元の割れ目の出来やすいところに彼らは決まって現れ出るのだ。その点がたまたまケサリーの町の中にあったというだけのことだった。だが、そのおかげで数千人の町の人間の魂が奪われてしまった。その竜とやらが魂を貪り食うとき一体どういう味がしたのだろうか? ランフォには想像も付かなかった。彼は吐き気がして頭がふらつくのを感じた。次元竜とは世界に現存するもっとも奇妙な生命だといえるだろう。
しかし、そういったものを実際目の当たりにするのは初めてだった。魔道書にはそういったものは目に見えないほどの小さな世界にのみ生きると書かれていたが、この様な強い影響力をもつ、次元の歪みの生き物とはどれくらいの巨大さなのだろうか? ランフォは考えるまでもなく身震いした。彼は自分が竜と戦う役目ではないことに心底ほっとしていた。しかし、兵士たちに混じる、ガマスル・ファグの魔術師たちはそうとは考えていないようだ。彼らは自分たちのする力試しに奮い立っているのに違いなかった。自分たちの力がどれほど強大か、力が強ければ強いほど試す機会はそうはないからだった。
そんな気迫が望遠鏡のレンズの向こう側からも感じ取れる気がした。さすがにだれがクライマケアだか見当をつけることは出来なかったが、彼女がそこにいるということは疑いない事実だった。砂埃の舞う村の中で見た彼女の横顔をランフォはもう一度まざまざと思い出した。思いがけず、その感覚は途方もない苦痛を呼び起こした。無理もないか、俺はあいつに一度殺されたのだから。彼は一人で苦しげに呟くと、望遠鏡から目を離した。
竜が現れるはずの特異点の周りにはいつもどおり巨大なかがり火が焚かれ始めた。真昼の様とまではいかなかったが、その秘密の祭壇には申し分ない明るさだった。それとは反対にランフォのいる丘を照らすものは、細くやせ細った月と真っ黒の空の体に出来たしみのような貧弱な星の光だけだった。それでも、敏感な彼の目には眩しすぎるくらいだった。
兵士達のキャンプ地はいつもどおり平穏そのものだった。ランフォは監視ばかりの生活に疲れて来ていたので今日は早く寝てしまおうと毛羽立った毛布をかぶって横になった。
まぶたの外側の世界と内側の世界、一体どちら側にケサリーの竜は属すのだろうか、きっと、閉じられつつある隙間の中にのみケサリーの竜は住むことが出来るのだろう。だから、彼らは実体のある世界にしょっちゅうやって来て、魂を貪らなければならないのだ。
そう考えてみると、自分とケサリーの竜はどこか似ている気さえした。
「生と死の狭間にのみ生きるもの、か。」
ランフォは眠りの中で、その無限に近く、また遠い場所から竜が近づきつつあるのを感じた。彼はそのうごめく暗い染みに向かって叫んでいた。
「魂の無い、引き千切れた地獄の中に住む、ケサリーの竜よ。お前は今から、人間のところへやってきて証明しようとしていることが、やっと分かったぞ。
お前は人間がもともと魂などもってはいないことを宣告しにくる。その恐怖をお前は喜んで食うのだ。かわいそうな人間たち。彼らは自分の魂が自分の望む姿をしていないことに気付くのを最も恐れている。彼らは自分の姿を耐えられないほど醜悪であるのを知るのを恐れている。だから、それを知るぐらいなら、お前に進んで魂を差し出すのだろう。」
ランフォが魂の奥で見ていた、竜の姿はいつの間にか巨大な影になっていた。竜の細長い首は九本あったが、それはたった一つの頭につながっていた。つまり、体が九つあるのだ。彼らの体は転々ばらばらの方向に走り去ろうとして、その都度、中央の首にしかりつけられていた。
その時聞いたことも無いような激しい轟音がしてランフォは目を覚ました。丘の下は灰色の煙に包まれて何も見えなかった。兵士達の持ってきた大砲が火を吹き始めたのだ。また、数秒も経たないうちにズシーン、ズシーンと地響きがした。ランフォはさっきの夢の中で見た、恐ろしい姿が破壊銃の火炎の中でもだえているのをうっとり想像していた。
それから三十分くらいたったあとだろうか、砲撃は中止され、やっと煙が晴れてきた。それと共に兵士達の歓声も聞こえてきた。彼らは竜を仕留めたことを確信して狂喜しているのだ。ランフォは望遠鏡を覗き込むと、魔術師たちも喜んではしゃぎまわっているのが見えた。だが、一人のイガメークのツタの魔法衣を着ている魔術師は、竜が出てきた幻の門の方を静かににらみつけていた。
しばらくして、騒ぎが止むと、彼らはテントの中に全員引っ込んでしまった。これでやっと安心して眠ることが出来るという安堵感が兵士達の陣地の中にただよっていた。
あとは兵士たちが引き払ってくれさえすれば、町に下りていって竜の糞があるかどうか調べることが出来る。ランフォにはさっきの砲撃で竜が死んだかどうか確かめようがなかったが、夢の中で見た、恐ろしい姿をもう一度見ることはもはや無いと思うと心底ほっとしていた。
しばらくしてその日の明け方ごろ、ランフォが背中に付いた露を舐め終わって、一息ついていると、大砲の焼け焦げがいたるところにある広場にぽつんと人影があるのが見えた。辺りは青く、霧がかっていた。
ランフォは望遠鏡を急いで覗き込んだ。その人はフードを肩まで下ろしていたので、黒くて長い髪の毛が見えた。クライマケアに違いないとランフォは思った。
クライマケアはそっと右手を上げると奇妙な形に動かし始めた。驚いたことに空間開錠の魔法を掛けているようだった。もしかすると、竜の死体があることを確認しようとしているのかもしれなかったが、兵士たちが持ち場を離れているときに、そんなことをするのは、いかにも軽率であるように思えた。
微かな光を帯びた空間の筋がその幅を広げていった。自分たちのいる現実とは違う世界のまぶたが開かれているのだ。その中に竜はいた。竜の体は光り輝く真っ赤な血に覆われていて、静かに横たわっていた。やはり死んでいるのだろう。
クライマケアは数歩そちらの方に歩み寄ると、また、魔法を掛け始めた。彼女の右手は灰色に光っていた。ランフォにはそれが何の呪文か具体的には分からなかったが、しばらくして、死んだはずの竜の体がぴくぴく動き出したのを見ると、蘇生の呪文の一種であることは間違いないようだった。
「なるほど、やっとこれでガマスル・ファグの町が大砲や魔術師を王の軍隊に貸し出した理由がやっと分かったな。奴らは退治する代わりに新しいしもべを得るというわけか。王は竜のしもべをガマスル・ファグにやるということをどういうことか分かっていない。王都が破壊されるのも近い将来だろう。それとも、ファグの町のいつも通りの慣習とすれば力を保持する喜びを得るためだけのものかも知れないがな。」
望遠鏡の中に見える、クライマケアはまだ、地面に転げている竜の目をこじ開けると、指でそっと瞳を触れた。そして、グレクスマクの印を書き込んだ。これで、竜の偽りの魂は彼女の物になったはずだ。
竜は急に起こされたのが癪に触ったのか苛立たしげに首を持ち上げた。そして、途方もない高みから彼女を見下ろしていた。クライマケアは微笑んで、竜の方に手を伸ばした。そんな笑顔を自分といっしょにいたときも良く見せていたなと。ランフォは空ろに思い出していた。
その差し出された手に答えるように竜はぐっと頭を下ろした。九つの首はそれに連れてしなやかに曲がった。そして、頭の巨大さに似合わない細くて赤い舌をそっと伸ばすと彼女のてのひらにそっと触れて来た。竜はてのひらに書かれた幻の文字を舌の先で読み取っていった。
クライマケアは満足げにその様子を見守っていた。彼女はふと、ランフォのいる丘の上を見た。彼は驚いて首をすくめた。もしかすると、彼女は最初から、ランフォがそこにいたのを気付いていたのかもしれない。もしそうならば、すぐに逃げなければ生き延びるチャンスはなくなってしまうだろう。だが、ランフォはクライマケアが竜を手懐ける様子から目を背けることが出来なかった。
竜は納得したようにてのひらの契約文を読み取っていった。クライマケアは竜の魂の火が自分の精神の器の中にすでに八割がた移されているのを実感して有頂天になっていた。
彼の名前がクズワーロスプということも分かった。さあ、クズワーロスプ、安心して私の中に入ってきて。そうやって、クライマケアは自分が偽りの魂を与えたばかりの復活した次元竜にやさしく呼びかけていた。あなたの香りは私がずっと昔知っていた人に良く似ているわね。彼はもうとっくに死んでしまっているけど、あなたは私と永遠に生きていくのよ。ふふ。冗談でもなく永遠に生きれるかもね。それくらい、あなたと私は相性が良さそうだもの。
竜は満足したのかじっくりと彼女の掌を味わっていた。しかし、契約文の最後の最後の一文のところに差し掛かるとぴたっと動きを止めた。まるで、サインが間違っているとでも言いたいような素振りだった。
「どうしたの?」
クライマケアが問いかける間もなく、彼女の体は宙に浮いていた。九つの体に生えた尻尾の一本が激しく動いて彼女を弾き飛ばしたのだ。竜は怒りに燃えて、次元の隙間から現実世界へと姿を現した。
その後、竜は兵士達の眠るテントを一つずつ踏み潰して回ると、一人一人の魂をおいしそうに貪り食っていた。さわぎに気付いて破壊砲を準備しようと急いだ兵士もいたが、すぐに竜の輝く吐息に焼かれて殺されてしまった。その光は信じられないくらいに美しく輝いていた。魔術師たちはまだ深い眠りについていたから、たとえ飛び起きたとしても、防御呪文を施す暇も無かった。兵士たちはその時点になって初めて、魔法使いが自分たちに与えた魔法の眼鏡が何の役にも立っていないことに気が付いた。
彼らは、恐ろしい叫び声を上げながら、近くの森に駆け込んで逃げようとしたが、竜の口から出る白い息はすぐに彼らに追いつくと、魂を抜き取りにかかった。つまり、白い息の光は人間の目にから進入するわけではないということに魔術師たちはいまさらながら気付いたがどうしようもなかった。もう少し時間さえあれば、最高の防御呪文を最初の攻撃の時と同じように掛けれたはずだが、疲れ果てた彼らの魂の器の中にはほんの少ししか力が残っていなかったのだ。
彼らは自分一人が生き残れば良いとでもいうのだろうか、自分だけに姿隠しの呪文を掛けると岩陰や木の窪みに身を隠した。そのおかげで、しばらくは彼らは竜に姿を見つからずに済んだのだが、執念深い竜は木の匂いを一本ずつ嗅いでいって、中に人間の香りがするのを見つけると、鋭い爪で人間が中に入っている木ごとなぎ倒して潰してしまった。いくら、強力なガマスル・ファグの魔法使いでさえどうすることも出来なかったのだ。
ランフォは、震えながら、兵士や魔法使いたちが皆殺しにされている様子を望遠鏡で見守っているしかなかった。奴は自分だって殺そうと思えば訳も無く殺すだろう。逃げても無駄であることは分かっていた。どんなに遠くに行ったって次元を超えて追いかけて来るだろう。
彼は人間たちが恐怖に打ち震えて自分から竜に魂を差し出しているのを見た。竜は軽蔑した目つきでそれを睨むと、爪で足を切って逃げられないようにしてから、魂を舌で舐めていた。彼は人間たちの決心がすぐに揺らぐのを知っているかのようだった。
竜が千人にも及ぶ兵士たちを殺しつくすのに実際には一時間もかからなかったのだが、ランフォは永遠に時間が止まっているような気さえした。
最後に竜は恐ろしい吠え声を一つ上げた。そして首を中心にして体を円を描くように並ばせると、尻尾を持ち上げて九つの糞をした。それは真っ黒な光り輝く宝石の様であるのが、遠くの望遠鏡からもはっきり見えた。
それから、間もなく、竜はもう一度開いた別の空間のまぶたに体をねじ込むと姿を消した。
ランフォは三十分ぐらいの間、そこからすぐに立ち去るべきか悩んだが、結局奴が殺そうと思ったらどこにいたって同じだということにもう一度気付くと、糞を取りに町の方へとふらふら降りて行った。
>六章に進む >homeに戻る
Copyright (C)2004-2018 Yoshito Iwakura
http://lezarakus.nobody.jp/
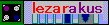
五章 黒い光の糞
ランフォが覗き込んだ望遠鏡の視界の中に、蟻のようにうごめく人間たちの姿が映し出された。そんな非力な者たちが、ケサリーに住む巨大な力を持つ竜を倒そうというのだからランフォは思わず笑ってしまった。望遠鏡から目を離すとすでに辺りは夕闇に沈もうとしていた。遥か彼方の兵士達のテントの群れの方では小さな煙がもくもくと上がり始めた。夕食の準備を始めたのだろう。そんな風に堂々と火が使えるのがうらやましかった。
竜はランフォが火を焚こうが気にしなかっただろうが、兵士たちはそんなことはないに違いない。いくら間抜けな彼らだって、ランフォがすぐ近くの丘にひそんで彼らの行動の一部始終を見張っていることに気付くだろう。
ランフォが、そのケサリーの町を見下ろす丘にたどり着いてからすでに二週間が過ぎようとしていた。この前の小さな村からここにやってくるまでの間にはさも恐ろしい、魔術師たちのわなが待ち構えているのだろうと、震えながら藪の中を潜り抜けて来たのだが、心配するようなことは何も起こらなかった。
もしかすると、村からケサリーの町への最短の道から大きく迂回してやって来たのが功を奏したのかもしれなかったが。結局ここにたどり着くまでに五日もかかってしまった。まっすぐ道を進めれば、たった半日ぐらいで着くことが出来るのだが、見つかって捕らえられて八つ裂きにされるよりはずっとましだった。
ランフォは日陰の魔法使いが残していった古い地図を頼りにここまで、やって来た。もちろん地図には街道から離れた森の中の様子のことなど全くと言っていいほど何も書かれていなかったが、それでも十分役に立った。今彼の居る小高い丘の存在もその地図に書かれていた。もしここが使えたら、町を一望出来るだろう。それに竜がいくら力強くてもそこまでは攻撃は届かないだろうし、うまくすれば兵士や魔術師たちとの戦いだって見物できるかもしれない。ランフォは地図を見ながら思った。
そういうわけで、その丘は町を盗み見るには絶好の場所だったが、それは王の兵士たちにとっても同じことだ。もし、そこに兵士たちがすでにいたとしたら、また別の場所を探さなくてはいけない。しかし、ランフォがその丘を注意深く調べても、かなり長い間人間の立ち入った形跡はなかった。兵士たちはやはり間抜けかとも思えたが、それは彼らの自信の表れであるともいえるだろう。彼らは無駄な労力をかけない主義らしい。余計そのために命を落とす確率が高まっているというのに、気にしないとでもいうのだろうか。
ランフォは火が起こせないので仕方なしにごそごそと袋の中から、石の様に硬くなった干し肉を一切れ取り出すと舌の上に乗せて溶かし始めた。ゲ・サナとイ・サナは彼の後ろの草陰ですでに眠りに就いていた。ほんのかすかな、時折聞こえる彼らの身じろぐ音を聞いていると、ランフォはほっとして大きくあくびをした。
やって来たばかりの時はこれからどんなことが起こるのだろうとわくわくして夜通し見張っていたが、ここ二週間たいした動きが見られないので、いくら辛抱強いランフォであっても正直飽きてしまった。竜は一体どこにいるのだろうか。しかし、兵士たちがそこから動かない様子を見ると、竜は近い将来再びそこに現れることを確信しているのに違いなかった。
彼は口の中でやっと少し肉汁の香りがし始めた干し肉をぐっと飲み干すと、退屈しのぎにまた、望遠鏡を覗き始めた。今度はもう少し倍率を高くしてみよう。その望遠鏡は特別な魔工学品ともいえる物だった。ほんの少し彼が精神を集中させ魔法力を覗き口に注ぎ込むととたんに視界がはっきりして、遠くの兵士の表情まで手に取るように良く見えるようになった。
彼らのケサリーの竜を倒すための罠は単純そのものだったが、その方が返って良かったかもしれなかった。彼らの持つ巨大な牛ぐらいの大きさの大砲の十数門は、半円形に配置され、その中央の点に火力が集中するようになっていた。
その点に必ず竜が突然姿を現すことが分かっているから、そのような配置になっているのだ。ランフォはケサリーの竜の正体は次元竜の一種であるに違いないと踏んでいた。少なくとも兵士たちを統率する魔術師たちも同じように考えているのだろう、そうでなければもっと違った作戦を取るはずだった。
次元竜と呼ばれるものは特異な性質をもった生き物の一種だった。それは生物というよりも生きた光とか、生きた次元の歪みとかに近いものだった。普通の常識でいうと空間そのものが生きるはずはないだろうということになってしまうが、魔法的な力が空間の一点に集まればそういうこともありうることだとされていた。それはイガメークのツタでも言われていることだったし、日陰の魔法使いの持っていた古い魔道書にもそう書かれていた。
そして、次元の割れ目の出来やすいところに彼らは決まって現れ出るのだ。その点がたまたまケサリーの町の中にあったというだけのことだった。だが、そのおかげで数千人の町の人間の魂が奪われてしまった。その竜とやらが魂を貪り食うとき一体どういう味がしたのだろうか? ランフォには想像も付かなかった。彼は吐き気がして頭がふらつくのを感じた。次元竜とは世界に現存するもっとも奇妙な生命だといえるだろう。
しかし、そういったものを実際目の当たりにするのは初めてだった。魔道書にはそういったものは目に見えないほどの小さな世界にのみ生きると書かれていたが、この様な強い影響力をもつ、次元の歪みの生き物とはどれくらいの巨大さなのだろうか? ランフォは考えるまでもなく身震いした。彼は自分が竜と戦う役目ではないことに心底ほっとしていた。しかし、兵士たちに混じる、ガマスル・ファグの魔術師たちはそうとは考えていないようだ。彼らは自分たちのする力試しに奮い立っているのに違いなかった。自分たちの力がどれほど強大か、力が強ければ強いほど試す機会はそうはないからだった。
そんな気迫が望遠鏡のレンズの向こう側からも感じ取れる気がした。さすがにだれがクライマケアだか見当をつけることは出来なかったが、彼女がそこにいるということは疑いない事実だった。砂埃の舞う村の中で見た彼女の横顔をランフォはもう一度まざまざと思い出した。思いがけず、その感覚は途方もない苦痛を呼び起こした。無理もないか、俺はあいつに一度殺されたのだから。彼は一人で苦しげに呟くと、望遠鏡から目を離した。
竜が現れるはずの特異点の周りにはいつもどおり巨大なかがり火が焚かれ始めた。真昼の様とまではいかなかったが、その秘密の祭壇には申し分ない明るさだった。それとは反対にランフォのいる丘を照らすものは、細くやせ細った月と真っ黒の空の体に出来たしみのような貧弱な星の光だけだった。それでも、敏感な彼の目には眩しすぎるくらいだった。
兵士達のキャンプ地はいつもどおり平穏そのものだった。ランフォは監視ばかりの生活に疲れて来ていたので今日は早く寝てしまおうと毛羽立った毛布をかぶって横になった。
まぶたの外側の世界と内側の世界、一体どちら側にケサリーの竜は属すのだろうか、きっと、閉じられつつある隙間の中にのみケサリーの竜は住むことが出来るのだろう。だから、彼らは実体のある世界にしょっちゅうやって来て、魂を貪らなければならないのだ。
そう考えてみると、自分とケサリーの竜はどこか似ている気さえした。
「生と死の狭間にのみ生きるもの、か。」
ランフォは眠りの中で、その無限に近く、また遠い場所から竜が近づきつつあるのを感じた。彼はそのうごめく暗い染みに向かって叫んでいた。
「魂の無い、引き千切れた地獄の中に住む、ケサリーの竜よ。お前は今から、人間のところへやってきて証明しようとしていることが、やっと分かったぞ。
お前は人間がもともと魂などもってはいないことを宣告しにくる。その恐怖をお前は喜んで食うのだ。かわいそうな人間たち。彼らは自分の魂が自分の望む姿をしていないことに気付くのを最も恐れている。彼らは自分の姿を耐えられないほど醜悪であるのを知るのを恐れている。だから、それを知るぐらいなら、お前に進んで魂を差し出すのだろう。」
ランフォが魂の奥で見ていた、竜の姿はいつの間にか巨大な影になっていた。竜の細長い首は九本あったが、それはたった一つの頭につながっていた。つまり、体が九つあるのだ。彼らの体は転々ばらばらの方向に走り去ろうとして、その都度、中央の首にしかりつけられていた。
その時聞いたことも無いような激しい轟音がしてランフォは目を覚ました。丘の下は灰色の煙に包まれて何も見えなかった。兵士達の持ってきた大砲が火を吹き始めたのだ。また、数秒も経たないうちにズシーン、ズシーンと地響きがした。ランフォはさっきの夢の中で見た、恐ろしい姿が破壊銃の火炎の中でもだえているのをうっとり想像していた。
それから三十分くらいたったあとだろうか、砲撃は中止され、やっと煙が晴れてきた。それと共に兵士達の歓声も聞こえてきた。彼らは竜を仕留めたことを確信して狂喜しているのだ。ランフォは望遠鏡を覗き込むと、魔術師たちも喜んではしゃぎまわっているのが見えた。だが、一人のイガメークのツタの魔法衣を着ている魔術師は、竜が出てきた幻の門の方を静かににらみつけていた。
しばらくして、騒ぎが止むと、彼らはテントの中に全員引っ込んでしまった。これでやっと安心して眠ることが出来るという安堵感が兵士達の陣地の中にただよっていた。
あとは兵士たちが引き払ってくれさえすれば、町に下りていって竜の糞があるかどうか調べることが出来る。ランフォにはさっきの砲撃で竜が死んだかどうか確かめようがなかったが、夢の中で見た、恐ろしい姿をもう一度見ることはもはや無いと思うと心底ほっとしていた。
しばらくしてその日の明け方ごろ、ランフォが背中に付いた露を舐め終わって、一息ついていると、大砲の焼け焦げがいたるところにある広場にぽつんと人影があるのが見えた。辺りは青く、霧がかっていた。
ランフォは望遠鏡を急いで覗き込んだ。その人はフードを肩まで下ろしていたので、黒くて長い髪の毛が見えた。クライマケアに違いないとランフォは思った。
クライマケアはそっと右手を上げると奇妙な形に動かし始めた。驚いたことに空間開錠の魔法を掛けているようだった。もしかすると、竜の死体があることを確認しようとしているのかもしれなかったが、兵士たちが持ち場を離れているときに、そんなことをするのは、いかにも軽率であるように思えた。
微かな光を帯びた空間の筋がその幅を広げていった。自分たちのいる現実とは違う世界のまぶたが開かれているのだ。その中に竜はいた。竜の体は光り輝く真っ赤な血に覆われていて、静かに横たわっていた。やはり死んでいるのだろう。
クライマケアは数歩そちらの方に歩み寄ると、また、魔法を掛け始めた。彼女の右手は灰色に光っていた。ランフォにはそれが何の呪文か具体的には分からなかったが、しばらくして、死んだはずの竜の体がぴくぴく動き出したのを見ると、蘇生の呪文の一種であることは間違いないようだった。
「なるほど、やっとこれでガマスル・ファグの町が大砲や魔術師を王の軍隊に貸し出した理由がやっと分かったな。奴らは退治する代わりに新しいしもべを得るというわけか。王は竜のしもべをガマスル・ファグにやるということをどういうことか分かっていない。王都が破壊されるのも近い将来だろう。それとも、ファグの町のいつも通りの慣習とすれば力を保持する喜びを得るためだけのものかも知れないがな。」
望遠鏡の中に見える、クライマケアはまだ、地面に転げている竜の目をこじ開けると、指でそっと瞳を触れた。そして、グレクスマクの印を書き込んだ。これで、竜の偽りの魂は彼女の物になったはずだ。
竜は急に起こされたのが癪に触ったのか苛立たしげに首を持ち上げた。そして、途方もない高みから彼女を見下ろしていた。クライマケアは微笑んで、竜の方に手を伸ばした。そんな笑顔を自分といっしょにいたときも良く見せていたなと。ランフォは空ろに思い出していた。
その差し出された手に答えるように竜はぐっと頭を下ろした。九つの首はそれに連れてしなやかに曲がった。そして、頭の巨大さに似合わない細くて赤い舌をそっと伸ばすと彼女のてのひらにそっと触れて来た。竜はてのひらに書かれた幻の文字を舌の先で読み取っていった。
クライマケアは満足げにその様子を見守っていた。彼女はふと、ランフォのいる丘の上を見た。彼は驚いて首をすくめた。もしかすると、彼女は最初から、ランフォがそこにいたのを気付いていたのかもしれない。もしそうならば、すぐに逃げなければ生き延びるチャンスはなくなってしまうだろう。だが、ランフォはクライマケアが竜を手懐ける様子から目を背けることが出来なかった。
竜は納得したようにてのひらの契約文を読み取っていった。クライマケアは竜の魂の火が自分の精神の器の中にすでに八割がた移されているのを実感して有頂天になっていた。
彼の名前がクズワーロスプということも分かった。さあ、クズワーロスプ、安心して私の中に入ってきて。そうやって、クライマケアは自分が偽りの魂を与えたばかりの復活した次元竜にやさしく呼びかけていた。あなたの香りは私がずっと昔知っていた人に良く似ているわね。彼はもうとっくに死んでしまっているけど、あなたは私と永遠に生きていくのよ。ふふ。冗談でもなく永遠に生きれるかもね。それくらい、あなたと私は相性が良さそうだもの。
竜は満足したのかじっくりと彼女の掌を味わっていた。しかし、契約文の最後の最後の一文のところに差し掛かるとぴたっと動きを止めた。まるで、サインが間違っているとでも言いたいような素振りだった。
「どうしたの?」
クライマケアが問いかける間もなく、彼女の体は宙に浮いていた。九つの体に生えた尻尾の一本が激しく動いて彼女を弾き飛ばしたのだ。竜は怒りに燃えて、次元の隙間から現実世界へと姿を現した。
その後、竜は兵士達の眠るテントを一つずつ踏み潰して回ると、一人一人の魂をおいしそうに貪り食っていた。さわぎに気付いて破壊砲を準備しようと急いだ兵士もいたが、すぐに竜の輝く吐息に焼かれて殺されてしまった。その光は信じられないくらいに美しく輝いていた。魔術師たちはまだ深い眠りについていたから、たとえ飛び起きたとしても、防御呪文を施す暇も無かった。兵士たちはその時点になって初めて、魔法使いが自分たちに与えた魔法の眼鏡が何の役にも立っていないことに気が付いた。
彼らは、恐ろしい叫び声を上げながら、近くの森に駆け込んで逃げようとしたが、竜の口から出る白い息はすぐに彼らに追いつくと、魂を抜き取りにかかった。つまり、白い息の光は人間の目にから進入するわけではないということに魔術師たちはいまさらながら気付いたがどうしようもなかった。もう少し時間さえあれば、最高の防御呪文を最初の攻撃の時と同じように掛けれたはずだが、疲れ果てた彼らの魂の器の中にはほんの少ししか力が残っていなかったのだ。
彼らは自分一人が生き残れば良いとでもいうのだろうか、自分だけに姿隠しの呪文を掛けると岩陰や木の窪みに身を隠した。そのおかげで、しばらくは彼らは竜に姿を見つからずに済んだのだが、執念深い竜は木の匂いを一本ずつ嗅いでいって、中に人間の香りがするのを見つけると、鋭い爪で人間が中に入っている木ごとなぎ倒して潰してしまった。いくら、強力なガマスル・ファグの魔法使いでさえどうすることも出来なかったのだ。
ランフォは、震えながら、兵士や魔法使いたちが皆殺しにされている様子を望遠鏡で見守っているしかなかった。奴は自分だって殺そうと思えば訳も無く殺すだろう。逃げても無駄であることは分かっていた。どんなに遠くに行ったって次元を超えて追いかけて来るだろう。
彼は人間たちが恐怖に打ち震えて自分から竜に魂を差し出しているのを見た。竜は軽蔑した目つきでそれを睨むと、爪で足を切って逃げられないようにしてから、魂を舌で舐めていた。彼は人間たちの決心がすぐに揺らぐのを知っているかのようだった。
竜が千人にも及ぶ兵士たちを殺しつくすのに実際には一時間もかからなかったのだが、ランフォは永遠に時間が止まっているような気さえした。
最後に竜は恐ろしい吠え声を一つ上げた。そして首を中心にして体を円を描くように並ばせると、尻尾を持ち上げて九つの糞をした。それは真っ黒な光り輝く宝石の様であるのが、遠くの望遠鏡からもはっきり見えた。
それから、間もなく、竜はもう一度開いた別の空間のまぶたに体をねじ込むと姿を消した。
ランフォは三十分ぐらいの間、そこからすぐに立ち去るべきか悩んだが、結局奴が殺そうと思ったらどこにいたって同じだということにもう一度気付くと、糞を取りに町の方へとふらふら降りて行った。
>六章に進む >homeに戻る
Copyright (C)2004-2018 Yoshito Iwakura
http://lezarakus.nobody.jp/
