>一章 >二章 三章 >四章 >五章 >六章
そうしなければ、彼女の地獄の様な有様になった実験室の中で少しでも息を吸い込んだりしたら、気分が悪くなって死んでしまうかもしれなかった。
部屋の中央には奇妙な形をした巨大な壷が置かれていた。それはまだやわらかいゴーレムを入れておくために作られた特別な鋳型だった。何本もの突起がその表面にあった。ゴーレムの足や手になる部分だ。
クライマケアは浅黒い手で、そのぴかぴか光る表面をなでさすって言った。
「この中にすでに新しい命が宿っているのね。偽りの命。あなたの中にある偽りの命のための炎はいったいどんな色をしてるんでしょうね。」
彼女が自分のことを振り返って見つめているのを、ランフォは気付きながらしばらく無視して作業を続けていたが、やがて答えた。
「知るもんか、奴の魂の色なんて。ただ、俺の中にいてちくちく痒いばっかりだ。でも、もう少しで、十分な大きさにまで成長するだろう。そうすれば奴の目を覚ませても大丈夫になる。あせってはだめだ。そう君の本には書いてあった。」
クライマケアの部屋にあったゲサクの魔道書には、ゴーレムの材料の糞はなるべく新鮮な物を使うべし。さもなくば・・・と書かれていた。しかし、そういう重要な部分にさしかかると本のページは決まって破られているものだ。ランフォは彼女にページの切れ端を知らないか聞いてみたが、やはり分からないようだった。それどころか彼女はその本を持っているだけで読んだこともないのかもしれない。
ランフォは先の部分が気になったが、どのようになるのかこれから実際に確かめれば分かるだろう。恐ろしくもあったがたまらなくわくわくもしていた。
彼は最後の土を練り上げるとそこに指で刻みを付け、カマスの印を書いた。そして、自分の中にある精神の器の中にしまってあるゴーレムの仮の魂にその印を覚えこませた。今まで何度この作業を繰り返したのか思い出せなかったが、それを忘れるとゴーレムの体の各部分の統率がまるでとれなくなるのだ。一度実習の時間で腐った果物を材料とするゴーレムを作ったとき、失敗した生徒がいて、そのゴーレムの動きはなかなか見ものだった。頭と手と足が転々ばらばらな方向に行こうとするものだから、体はすぐに引きちぎれて、屑の山になってしまった。そしてその瞬間にそのゴーレムを作った生徒の中の仮の魂も激しく弾けたので、彼自身もショックを受け気を失ってしまった。
魔法生物を扱うときには、術師の方にもリスクを伴うということをランフォは痙攣する彼を見て知った。ランフォ自身のゴーレムはその時極めて順調に動いてはいたのだが。
しかし、これから作るゴーレムと比べれば、例えるなら竜と飼い犬ぐらいの差があるに違いなかった。まだ眠っているとは言え、仮の魂の炎の強さが尋常ではなかったのだ。本体の自分自身の魂がその炎で火傷しないか心配なぐらいだった。
「さて、これで良し。俺は一眠りするよ。君は授業に行ってくれ。でもその前に着替えてからにした方が良いぞ。生徒たちはみんな、異臭防御の魔法を鼻に掛けていないだろうから。」
最後の粘土を壷の中に入れ、蒼海樹の葉で作った蓋をしながら彼は言った。
「ええ。分かってるわ。クリストル」そうクスクス笑いながらクライマケアは出て行った。徹夜で作業していたにも関わらず彼女は元気そうだった。自分もあいつぐらいの体力があればな。と思いながらランフォは部屋の隅でぼろ布に包まってため息を付いた。眠るのは三十時間ぶりだったので、考える暇もなく夢の中に落ち込んでいった。
夢の中でランフォはひとりでに最後の作業が行われているのを見た。彼は歯で自分の爪を噛むと勢い良く頭を振った。すると、爪が剥げて血が床に滴っていた。しかし、それには気にも止めずに立ち上がるとゴーレムの入った壷の前に立ち、壷の表面にその血をインク代わりにして奇妙な印を描いた。それは今までランフォが見たこともないような印だった。ランフォは余りの指の痛さに悲鳴を上げた。
そこで彼は目を覚ましたのだ。床を見ると恐ろしい量の血の水たまりが出来ていた。彼は現実に自分の爪を食いちぎっていたのだった。彼は驚いてぼろ布で手を拭うとどうしようか迷った。あの夢の中で見た印を本当にゴーレムの壷に描くべきなのだろうか。
だが、迷っている暇などなかった、そうしなければその複雑な印を忘れてしまって二度と描けなくなってしまうだろう。そんなことに彼は耐えられそうになかった。
立ち上がると、夢で見た手順通りにゴーレムの真っ黒い壷の頭の所に目掛けて血しぶきを飛ばしながら奇妙な文字のようなものを書き付けていった。字を書き終わるとランフォはそれを六角形の直線で囲んだ。そして次は足となる部分にも同じ印を描いた。右足の印と左足の印は左右対称の形になっていた。右手の印を描き、最後に左手の印を描こうとした時にランフォはなぜか線が描けない事に気が付いた。指から流れる血が乾いて固まってしまったらしかった。ランフォは苛立たしげにもう一度歯で激しく指を噛むと再び血が流れ始めた。指先をしばらく口に含んで血を飲み込んでからランフォは最後の字を書こうと身構えた。彼の胃の中を赤い血が流れ落ちていくのが透けて見えるような気さえした。
ちょうどその時だった。最後の印を描き終えていないというのに、壷はめきめき音を立て始めた。ゴーレムが動き出しだのだ。彼は焦った。しかし、最後の字のやっと半分を描き終えた時には壷はこなごなに砕け散ってしまっていた。そして、その中にあるものがランフォに向かって勢い良く振り下ろされた。ランフォはかすれていく意識の中でゴーレムの腕が自分の首をしっかり押さえつけているのを見た。
早く、奴の魂の火を取り出して消さなければ、そうしなければ殺されてしまう。そう思う暇もなく、ランフォ自身の意識の方が掻き消えてしまった。
それからランフォが目を覚ますまでの間に町では最悪な事が起きていた。ランフォのゴーレムは町の中を悠々と歩くと手当たりしだい人を捕まえて脳天に一撃食らわせて頭蓋骨を砕いて回っていたのだった。当然イガメークのツタの魔法使いの教官たちも借り出されて対処させられたが、不思議なことに一切の魔法が効かないようだった。ゴーレムの体に描かれた、うろこ状の悪魔の印がそれを防いでいるのに違いがなかった。
ゴーレムを止めるにはその動力源になっている彼を作った術師の精神の器の中のゴーレムの仮の魂の火を消す以外に方法はなかった。問題はただ一つあった。誰がそのゴーレムを作ったか知るためにはゴーレムの中にある、偽物の精神の器に刻まれた、持ち主の名前を読めば良かった。だが、そのためには、ゴーレムにひどく接近しなければならなかったのだ。結局、若い一人の魔法使いの教官の命と引き換えにして名前は読み取られた。彼が、「クリストル・ランフォ」と呟いたときには、すでに首の骨を砕かれていた。
クライマケアはその様子を遠くから見ていたが、何もせずにただ震えていた。彼女はあらかじめその若い魔法使いが頭を砕かれる前から、犯人がランフォであることを知っていた。それに自分だって手を貸していたのだから、疑われるのではないかと恐れていたのだ。
しかし、他の教官たちは恐ろしい目つきをしながら彼女を取り囲むと、追及し始めた。
それから兵士たちが土塁を積み上げてなんとかゴーレムの動きを止めている間に、教官たちはクライマケアの実験室になだれ込んで来た。まだ、ゴーレムの壷のかけらやら、糞や土の山が散乱する汚い部屋の中でランフォは気を失ったままだった。
教官たちはあらゆる手を用いてランフォは叩き起こそうとしたが、目を覚まさなかった。
一番年配の教官が強力な昏睡回復の呪文を唱え始めた時、町の兵士が急いで部屋に飛び込んで来た。「またゴーレムが動き出しました。すでに全ての防壁を破って兵士を殺し始めています。町長は破壊銃で、すぐにでも奴を殺すべきだ。と言っていますが。」
教官たちは顔を見合わせた。町の外の物を全て破壊し尽くすほどの威力の破壊銃で射撃すれば、町はどうなってしまうだろう。ガマスル・ファグの町の魔法力の源である、スーメラーシムの香炉に傷が付いたら取り返しのつかないことになってしまう。そんなことが彼らの頭の中を瞬間的に悪夢のように駆け巡った。しかし、クライマケアがそのつかの間の沈黙を破った。
「クリストル・ランフォの生命の器ごと破壊しましょう。彼は結果的に死んでしまうでしょうが、必ずゴーレムの仮の魂の火を消すにはそれしか方法がありません。それとも、それも面倒なら彼を今すぐ殺すしかないでしょう。」
教官長は驚いて言った。
「殺すなんて。恐ろしいことを。私たちには彼を殺す権利なんて持っていないじゃないか。だが、精神の器を壊すことなら許されていないとは言えないだろう。そうとは言え、君はそれでいいのか?」
しかし、クライマケアは彼をまっすぐ見据えて言った。
「この事態は彼と私が招いたことです。私たち、魔術師は自分たちのした責任は取らなければいけません。彼は生命の器を失い、私は彼を失うのです。」
今度は教官長たちも黙っているだけだった。
作業は速やかに行われた。ランフォは生命の器を砕かれ、もぬけの殻になった体は町の外に捨てられた。ランフォはその作業の中で自分の口がひとりでに動いているのを感じた。クライマケアが彼に話させているのだ。彼はクライマケアが自分の唇にそっと触れているのを無意識の中で感じた。
「裏切り者には死を、魂の醜きものには破滅を。」
ゴーレムはすぐにその瞬間に土くれの山に戻っていた、まさに頭を砕かれそうにその腕に抱えれていた一人の兵士はその山から逃れようと必死でもがいていた。
何時間もの間、もうすでに土くれの山に過ぎないのに、それに向かってありとあらゆる罵声が浴びせられた。もちろん罵声ばかりでなくさまざまな石ころやゴミが投げつけられたのでいっそうゴミの山はうずたかくなるばかりだった。町の外から来た人はそれを見て、なぜ町の真ん中の広場にゴミ捨て場が出来たのかと首を捻っただろう。
その一方でランフォは町の外で忘れ去られていた。生命の器を持たなければ、スーメラーシムの香炉からの煙を受けることも出来なくなる。それに、町の外にある自然的なごく微弱な魔法力だってためることが不可能になってしまうのだ。その器に溜めた魔法力をランプの中の油に例えると良く分かるだろう。その真ん中に灯されるのが、魂の炎という訳だ。今、ランフォの生命の器の中に蓄えられていた魔法力は、ほとんどその割れ目から流れ落ちようとしていた。ゴーレムなどの非生命体の魂の火は術師の器の中に言わば寄生しているような格好になるのだが、術師自身の魂の炎が最優先されるので、燃料の余裕がなくなるとすぐに自然と消えてしまうのだった。
次は、中心の火が消える番だった。もう数分と持たないかもしれなかった。しかし、その火は消え入りそうになりながら決して消えることはなかった。誰かが彼の口の中に直接魔法力を注ぎ入れていたのだ。ランフォはその甘い汁をむさぼるように吸った。とは言っても生命の器はひび割れだらけだったから、すぐに流れ落ちてしまったのだが。
もうろうとする、ランフォの視界の中で人の姿が揺れていた。最初は悪魔か怪物かと思えたが、すぐにそれは色の浅黒い老人の姿に変わっていった。彼は日陰の魔法使いと呼ばれていた。最もそう呼ばれていたのは、彼がガマスル・ファグにいたかなり昔の事だったし、彼もそう呼ばれるのを嫌っていた。
日陰の魔法使いはしばらくランフォの事をじっと観察していたが、息が落ち着いてきたのを見て取ると、逞しいランフォの体を軽々と担いでどこかに荒い息をしながら歩いて行ってしまった。暗闇に沈み始めた道にはランフォの指から未だに滴り続ける、血の玉が転々と残されていた。
>四章に進む >homeに戻る
Copyright (C)2004-2018 Yoshito Iwakura
http://lezarakus.nobody.jp/
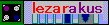
三章 壊れた器
次の日からランフォは全ての授業に病欠の届けを出すと、ゴーレムの製造に取り掛かった。それは恐ろしい苦労の連続だったが、クライマケアの協力もあってなんとか乗り切った。彼女は自分の鼻とランフォの鼻にしばらく匂いを感じない魔科学の加工を施した。そうしなければ、彼女の地獄の様な有様になった実験室の中で少しでも息を吸い込んだりしたら、気分が悪くなって死んでしまうかもしれなかった。
部屋の中央には奇妙な形をした巨大な壷が置かれていた。それはまだやわらかいゴーレムを入れておくために作られた特別な鋳型だった。何本もの突起がその表面にあった。ゴーレムの足や手になる部分だ。
クライマケアは浅黒い手で、そのぴかぴか光る表面をなでさすって言った。
「この中にすでに新しい命が宿っているのね。偽りの命。あなたの中にある偽りの命のための炎はいったいどんな色をしてるんでしょうね。」
彼女が自分のことを振り返って見つめているのを、ランフォは気付きながらしばらく無視して作業を続けていたが、やがて答えた。
「知るもんか、奴の魂の色なんて。ただ、俺の中にいてちくちく痒いばっかりだ。でも、もう少しで、十分な大きさにまで成長するだろう。そうすれば奴の目を覚ませても大丈夫になる。あせってはだめだ。そう君の本には書いてあった。」
クライマケアの部屋にあったゲサクの魔道書には、ゴーレムの材料の糞はなるべく新鮮な物を使うべし。さもなくば・・・と書かれていた。しかし、そういう重要な部分にさしかかると本のページは決まって破られているものだ。ランフォは彼女にページの切れ端を知らないか聞いてみたが、やはり分からないようだった。それどころか彼女はその本を持っているだけで読んだこともないのかもしれない。
ランフォは先の部分が気になったが、どのようになるのかこれから実際に確かめれば分かるだろう。恐ろしくもあったがたまらなくわくわくもしていた。
彼は最後の土を練り上げるとそこに指で刻みを付け、カマスの印を書いた。そして、自分の中にある精神の器の中にしまってあるゴーレムの仮の魂にその印を覚えこませた。今まで何度この作業を繰り返したのか思い出せなかったが、それを忘れるとゴーレムの体の各部分の統率がまるでとれなくなるのだ。一度実習の時間で腐った果物を材料とするゴーレムを作ったとき、失敗した生徒がいて、そのゴーレムの動きはなかなか見ものだった。頭と手と足が転々ばらばらな方向に行こうとするものだから、体はすぐに引きちぎれて、屑の山になってしまった。そしてその瞬間にそのゴーレムを作った生徒の中の仮の魂も激しく弾けたので、彼自身もショックを受け気を失ってしまった。
魔法生物を扱うときには、術師の方にもリスクを伴うということをランフォは痙攣する彼を見て知った。ランフォ自身のゴーレムはその時極めて順調に動いてはいたのだが。
しかし、これから作るゴーレムと比べれば、例えるなら竜と飼い犬ぐらいの差があるに違いなかった。まだ眠っているとは言え、仮の魂の炎の強さが尋常ではなかったのだ。本体の自分自身の魂がその炎で火傷しないか心配なぐらいだった。
「さて、これで良し。俺は一眠りするよ。君は授業に行ってくれ。でもその前に着替えてからにした方が良いぞ。生徒たちはみんな、異臭防御の魔法を鼻に掛けていないだろうから。」
最後の粘土を壷の中に入れ、蒼海樹の葉で作った蓋をしながら彼は言った。
「ええ。分かってるわ。クリストル」そうクスクス笑いながらクライマケアは出て行った。徹夜で作業していたにも関わらず彼女は元気そうだった。自分もあいつぐらいの体力があればな。と思いながらランフォは部屋の隅でぼろ布に包まってため息を付いた。眠るのは三十時間ぶりだったので、考える暇もなく夢の中に落ち込んでいった。
夢の中でランフォはひとりでに最後の作業が行われているのを見た。彼は歯で自分の爪を噛むと勢い良く頭を振った。すると、爪が剥げて血が床に滴っていた。しかし、それには気にも止めずに立ち上がるとゴーレムの入った壷の前に立ち、壷の表面にその血をインク代わりにして奇妙な印を描いた。それは今までランフォが見たこともないような印だった。ランフォは余りの指の痛さに悲鳴を上げた。
そこで彼は目を覚ましたのだ。床を見ると恐ろしい量の血の水たまりが出来ていた。彼は現実に自分の爪を食いちぎっていたのだった。彼は驚いてぼろ布で手を拭うとどうしようか迷った。あの夢の中で見た印を本当にゴーレムの壷に描くべきなのだろうか。
だが、迷っている暇などなかった、そうしなければその複雑な印を忘れてしまって二度と描けなくなってしまうだろう。そんなことに彼は耐えられそうになかった。
立ち上がると、夢で見た手順通りにゴーレムの真っ黒い壷の頭の所に目掛けて血しぶきを飛ばしながら奇妙な文字のようなものを書き付けていった。字を書き終わるとランフォはそれを六角形の直線で囲んだ。そして次は足となる部分にも同じ印を描いた。右足の印と左足の印は左右対称の形になっていた。右手の印を描き、最後に左手の印を描こうとした時にランフォはなぜか線が描けない事に気が付いた。指から流れる血が乾いて固まってしまったらしかった。ランフォは苛立たしげにもう一度歯で激しく指を噛むと再び血が流れ始めた。指先をしばらく口に含んで血を飲み込んでからランフォは最後の字を書こうと身構えた。彼の胃の中を赤い血が流れ落ちていくのが透けて見えるような気さえした。
ちょうどその時だった。最後の印を描き終えていないというのに、壷はめきめき音を立て始めた。ゴーレムが動き出しだのだ。彼は焦った。しかし、最後の字のやっと半分を描き終えた時には壷はこなごなに砕け散ってしまっていた。そして、その中にあるものがランフォに向かって勢い良く振り下ろされた。ランフォはかすれていく意識の中でゴーレムの腕が自分の首をしっかり押さえつけているのを見た。
早く、奴の魂の火を取り出して消さなければ、そうしなければ殺されてしまう。そう思う暇もなく、ランフォ自身の意識の方が掻き消えてしまった。
それからランフォが目を覚ますまでの間に町では最悪な事が起きていた。ランフォのゴーレムは町の中を悠々と歩くと手当たりしだい人を捕まえて脳天に一撃食らわせて頭蓋骨を砕いて回っていたのだった。当然イガメークのツタの魔法使いの教官たちも借り出されて対処させられたが、不思議なことに一切の魔法が効かないようだった。ゴーレムの体に描かれた、うろこ状の悪魔の印がそれを防いでいるのに違いがなかった。
ゴーレムを止めるにはその動力源になっている彼を作った術師の精神の器の中のゴーレムの仮の魂の火を消す以外に方法はなかった。問題はただ一つあった。誰がそのゴーレムを作ったか知るためにはゴーレムの中にある、偽物の精神の器に刻まれた、持ち主の名前を読めば良かった。だが、そのためには、ゴーレムにひどく接近しなければならなかったのだ。結局、若い一人の魔法使いの教官の命と引き換えにして名前は読み取られた。彼が、「クリストル・ランフォ」と呟いたときには、すでに首の骨を砕かれていた。
クライマケアはその様子を遠くから見ていたが、何もせずにただ震えていた。彼女はあらかじめその若い魔法使いが頭を砕かれる前から、犯人がランフォであることを知っていた。それに自分だって手を貸していたのだから、疑われるのではないかと恐れていたのだ。
しかし、他の教官たちは恐ろしい目つきをしながら彼女を取り囲むと、追及し始めた。
それから兵士たちが土塁を積み上げてなんとかゴーレムの動きを止めている間に、教官たちはクライマケアの実験室になだれ込んで来た。まだ、ゴーレムの壷のかけらやら、糞や土の山が散乱する汚い部屋の中でランフォは気を失ったままだった。
教官たちはあらゆる手を用いてランフォは叩き起こそうとしたが、目を覚まさなかった。
一番年配の教官が強力な昏睡回復の呪文を唱え始めた時、町の兵士が急いで部屋に飛び込んで来た。「またゴーレムが動き出しました。すでに全ての防壁を破って兵士を殺し始めています。町長は破壊銃で、すぐにでも奴を殺すべきだ。と言っていますが。」
教官たちは顔を見合わせた。町の外の物を全て破壊し尽くすほどの威力の破壊銃で射撃すれば、町はどうなってしまうだろう。ガマスル・ファグの町の魔法力の源である、スーメラーシムの香炉に傷が付いたら取り返しのつかないことになってしまう。そんなことが彼らの頭の中を瞬間的に悪夢のように駆け巡った。しかし、クライマケアがそのつかの間の沈黙を破った。
「クリストル・ランフォの生命の器ごと破壊しましょう。彼は結果的に死んでしまうでしょうが、必ずゴーレムの仮の魂の火を消すにはそれしか方法がありません。それとも、それも面倒なら彼を今すぐ殺すしかないでしょう。」
教官長は驚いて言った。
「殺すなんて。恐ろしいことを。私たちには彼を殺す権利なんて持っていないじゃないか。だが、精神の器を壊すことなら許されていないとは言えないだろう。そうとは言え、君はそれでいいのか?」
しかし、クライマケアは彼をまっすぐ見据えて言った。
「この事態は彼と私が招いたことです。私たち、魔術師は自分たちのした責任は取らなければいけません。彼は生命の器を失い、私は彼を失うのです。」
今度は教官長たちも黙っているだけだった。
作業は速やかに行われた。ランフォは生命の器を砕かれ、もぬけの殻になった体は町の外に捨てられた。ランフォはその作業の中で自分の口がひとりでに動いているのを感じた。クライマケアが彼に話させているのだ。彼はクライマケアが自分の唇にそっと触れているのを無意識の中で感じた。
「裏切り者には死を、魂の醜きものには破滅を。」
ゴーレムはすぐにその瞬間に土くれの山に戻っていた、まさに頭を砕かれそうにその腕に抱えれていた一人の兵士はその山から逃れようと必死でもがいていた。
何時間もの間、もうすでに土くれの山に過ぎないのに、それに向かってありとあらゆる罵声が浴びせられた。もちろん罵声ばかりでなくさまざまな石ころやゴミが投げつけられたのでいっそうゴミの山はうずたかくなるばかりだった。町の外から来た人はそれを見て、なぜ町の真ん中の広場にゴミ捨て場が出来たのかと首を捻っただろう。
その一方でランフォは町の外で忘れ去られていた。生命の器を持たなければ、スーメラーシムの香炉からの煙を受けることも出来なくなる。それに、町の外にある自然的なごく微弱な魔法力だってためることが不可能になってしまうのだ。その器に溜めた魔法力をランプの中の油に例えると良く分かるだろう。その真ん中に灯されるのが、魂の炎という訳だ。今、ランフォの生命の器の中に蓄えられていた魔法力は、ほとんどその割れ目から流れ落ちようとしていた。ゴーレムなどの非生命体の魂の火は術師の器の中に言わば寄生しているような格好になるのだが、術師自身の魂の炎が最優先されるので、燃料の余裕がなくなるとすぐに自然と消えてしまうのだった。
次は、中心の火が消える番だった。もう数分と持たないかもしれなかった。しかし、その火は消え入りそうになりながら決して消えることはなかった。誰かが彼の口の中に直接魔法力を注ぎ入れていたのだ。ランフォはその甘い汁をむさぼるように吸った。とは言っても生命の器はひび割れだらけだったから、すぐに流れ落ちてしまったのだが。
もうろうとする、ランフォの視界の中で人の姿が揺れていた。最初は悪魔か怪物かと思えたが、すぐにそれは色の浅黒い老人の姿に変わっていった。彼は日陰の魔法使いと呼ばれていた。最もそう呼ばれていたのは、彼がガマスル・ファグにいたかなり昔の事だったし、彼もそう呼ばれるのを嫌っていた。
日陰の魔法使いはしばらくランフォの事をじっと観察していたが、息が落ち着いてきたのを見て取ると、逞しいランフォの体を軽々と担いでどこかに荒い息をしながら歩いて行ってしまった。暗闇に沈み始めた道にはランフォの指から未だに滴り続ける、血の玉が転々と残されていた。
>四章に進む >homeに戻る
Copyright (C)2004-2018 Yoshito Iwakura
http://lezarakus.nobody.jp/
