>一章 >二章 >三章 四章 >五章 >六章
ランフォは火を起こして濃いお茶を入れると、冷えたハムをほお張りながらそれを暖めるように、少しずつ口の中にカップを傾けた。
思えば、あれから何十年も経ったものだ。日陰の魔法使いが自分の背中にこんな恐ろしい毛を生やしてから。何度その毛をむしり取ったか数え切れないぐらいだ。でも、日陰の魔法使いは彼を捕まえて何度も殴ってから気を失わせると、すぐに彼の背中からするどい棘を生やさせる毒薬を準備し始めたのだった。それは耐えられない苦痛を彼に与えもしたが、そのおかげで彼は今も生きているのだ。ランフォが野獣の魔法使いと呼ばれる由縁となったその棘の役割は彼にとって重要だった。その棘につく自然の魔法力の凝縮されたものをなめ取ることによって彼は生き延びているのだった。彼の生命の器は今も継ぎはぎだらけだったので、いくら魔法力の油を溜め込んでいても少しずつ穴からもれていってしまうのだから、普通以上の特殊な魔法力の収集機を絶対に必要としていたのだ。
しかし、なぜ日陰の魔法使いは自分のことを助けたのだろう? ランフォは今になって疑問に思った。やさしさからだろうか? そんなはずはない。彼がもし死にかけたランフォを見つけたとき、やさしさと呼べるものを持っていたとしたら、ランフォを見殺しにしていただろう。それにずっと一緒に暮らしていても数回しかまじまじと見る機会のなかった、皺だらけの顔にはめ込まれたガラスのような瞳には表情が映し出されたことはなかった。まるで、地面に捨てられたガラス球が曇り空を空ろに映しているのと同じような感じがした。ランフォを拾った理由は偶然、良い実験材料が無料で転がっていたからというだけだと、ランフォの心の中の日陰の魔法使いは答えた。彼はいつも灰色のマントを着ていて、かげろうのように歩いた。彼だって本当は普通の人間なのに、何か目を反らせたいような雰囲気をしていた。
日陰の魔法使いがランフォの心の中だけの存在になったのは三十年ぐらいは前のことだった。ある朝突然、しわくちゃの置き手紙だけが残されていた。手紙にはただ、自分の実験室を彼のために残すということと自分はもうここに戻ることはないだろうと書かれていた。
ランフォはその時、日陰の魔法使いの実験室から徒歩で一日ほど離れたところにある、ガマスル・ファグの町に彼が行って、町の番兵に撃ち殺されている様子を想像した。灰色のマントが小さく赤く燃え上がる様子を。馬鹿げた空想だった。彼は無駄に死ぬことなど決してしないだろう。
彼は何か極めて重要な用事で出かけたのに違いなかった。今までなら彼が家を開けるとき何時になったら戻るか、書き置きなどせずにランフォに背中を向けたまま呟くのが常だった。「何かまた、恐ろしいことをしているのに違いない。」ランフォは背中の棘が震えて擦りあってパチパチ音を立てた。手紙の最後にはまたこう書かれていた。
「もう間違ってもお前は自分の背中の毛を抜いたりしてはいけない。私はもうお前の毛を生やすことなど出来ないのだから。」
ランフォは今、皺だらけになった自分の頬を触ると濡れているのを感じた。彼はまだ、そんな大昔の人の事を思い出して泣くこともあるのかとすこし驚いていた。そのしゃくりあげる声を聞いて、ゲ・サナとイ・サナが不思議そうに顔を摺り寄せて来たのを、彼は喜んでそっと撫でてやった。
「さあ、出発だと言いたい所だが、お前たちは今日は留守番だ。私はケサリーの町の近くにある、村に行って情報を仕入れてくる。大丈夫だ、心配するな。お前たちには誰にも見つからないように姿隠しの呪文を唱えてやる。」
テントを畳んでから、ソチナ・ズムたちの佇む近くに置くと、彼らに姿隠しの呪文を唱え始めた。すると、彼らの姿がうっすらとかすんでよく見えなくなっていった。完全に姿が消える訳ではないが、旅人がよっぽど目を凝らさないかぎり見つけることは出来ないだろう。それにランフォは念のために、焚き火の跡に砂をかけたり葉っぱをまぶしたりして入念に隠すのを忘れなかった。
これで良し。ランフォは自分のためのザックを背負うともう一度サボテンで出来た馬たちのことを振り返った。今日は少し曇りかけているが、うまく彼らのところに日光が届けば良いのだが。そうすこし考えてから、彼はすばやくこんもりと茂った藪の中に飛び込んで行った。耳元でする、葉っぱのこすれあう感触が心地良く流れ去っていくのを感じてうれしくて彼は小さく吠えた。その声を聞いて彼が元は普通の人間だったことが分かる者は多分いないかっただろう。
その小さな隠されたキャンプ地に彼が戻ったのは三日も経ったあとだった。ランフォはとても疲れた表情をしながら、ソチナ・ズムにかけた呪文を解くと地面に座り込んでしまった。ケサリーの町の近くはとても恐ろしいことになっていた。その近くの村でさえ、王の派遣した千人もの兵士たちであふれかえっていた。もちろんその中には彼の天敵あるとさえ言える正統な魔術師たちも何人も加わっていた。ランフォは入念に変装していたが、彼らに近づかないように気をつけた。彼は村人の格好をして村の酒場に潜り込んだ。魔術師たちはめったに酒など飲まないことは分かっているのでそこが一番安心できる場所だった。彼らは精神の極度の集中を魔法を使うのに必要としていたが、酒を飲むと意識が乱れるので、そんなものを進んで飲むはずがなかったのだ。
村の小さな酒場は馬鹿げた任務に絶望した沢山の兵士たちで、昼間からほとんど満員だった。村人らしい客がいなくて返って好都合だった。
ランフォはしばらくぶりに吸う、人間の体臭に吐き気を覚えた。はやく森に帰って湿ったコケの匂いでも嗅ぎたい。そう切実に願ったが、しかたがなかったので、何度も少しずつ人間の匂いを吸い込んで鼻を慣らしていった。数分してランフォはカウンターのバーテンから一杯ビールを買うとそれを手に持って陽気に歌いながら、テーブルについていた兵士たちに目掛けて乾杯と大声を上げた。
その体格の良い若い兵士たちは、突然の変わったじいさんの登場に面食らっていたが、気にせずランフォは空いている席に潜り込んでしまった。
「兵隊様たちもたまらんでしょう。ケサリーの恐ろしい竜と言ったらもう。ここにいて何もしなくても魂を抜かれちまいそうになるもんです。」
兵士は焦げたソーセージにかぶりつきながら言った。
「良く知ってるなじいさん。あの竜は魂を食うんだとさ。魔術師の連中は魂そのものを食うのではなく、生命の源となる魔法力を音もなく食い漁るとか言ってたけど、俺たちにそんな難しいことを言われてもな。」
もう一人の少し背の低いやせた男が薄茶色の陶器のカップから口を離すと、心配そうに呟いた。
「俺たち、本当に大丈夫だよな。先遣隊みたいに殺されるのは嫌だぞ。」
「そんな、暗い顔すんなよ。なんとかなるって、ガマスル・ファグからも応援の魔法使いが来てくれたしな。奴らは普通、王の軍隊なんかに誰か派遣することなんてありえないらしいが王は大金を払って雇ったんだろうよ。うらやましいよな。
だけど、そのおかげで俺たちはいつも通り生きて帰ることができるさ。なんでもガマスル・ファグの魔法使い、何て言ったかすごいおばさんなんだがそれが魂を抜かれずに済む方法を考えてくれたらしい。何でもその竜は光の力を使って俺たちの魂を抜き取ろうとするらしいから、奴の使う特別な光さえ俺たちの目に入らないようにしさえすれば、怖くも何ともないらしい。俺は装備班だから一足早く見せてもらえたんだけど、用は変なでっかいサングラスさ。そんなもので奴に無敵になるなんてね。」
「そうか、それで、お前がさっきから落ち着いてる訳がやっと分かったよ。」
「だから、後は飯でも食って力を付けるだけさ。なあ、じいさんもしょぼしょぼしてまってかわいそうだし、こんな干からびたソーセージでも良かったら食ってやってくれよ。」
居眠りをいているふりをしていたランフォは、臭い匂いの肉の塊を少しだけ千切ると口の中に入れた。よくおしゃべりをする薬をもってきたのだがそれを飲ませる必要もなかった。こいつらは、守るべき機密という言葉を知らないらしい。その後、話の風向きは都に残してきた女たちのことに移って竜の事はこれ以上聞き出せないのが分かったので、「ちょっともう老人ですので眠くなって来ましたのでおいとまさせていただきます。」そうふらふら立ち上がって店を出た。その親切な兵士は心配して、気付けの薬まで持たせてくれたのだった。バーテンはそんなじいさんを見たことがないので最後まで不振そうな表情を崩さなかったのだが。しかし、もう十分な情報を得られた。彼らは五日後にケサリーに旅立つらしい。ランフォはその竜が息の根を止められた後に立ち寄れば、うまく竜の糞を手に入れることが出来るだろう。もし、彼らが失敗していたとしたら、糞を手に入れるのが難しくなってしまうだろうが、その時はその時だった。
村の小さな大通りに出て、後ろを振り返ると砂埃の向こう側から魔術師の集団がやって来るのが見えた。ランフォは驚いてすばやく樽の陰に隠れたが、向こうは何も気付いた様子はなかった。ほっとして様子をうかがうとその集団の中に意外なものを見た。その魔術師の一人はガマスル・ファグのイガメークのツタの魔法衣を着ていた。そうだ、奴らが来ているんだった。今のうちに村から離れるのが得策か。ランフォは立ち去ろうとして、腰を伸ばすと、砂の混じった強い風が吹いた。それにイガメークのツタの魔法使いのマントのフードが一瞬だけはじかれるように降りてしまった。その人はすぐに風が行ってしまうとフードを元に戻したが、その横顔は忘れもしない人のものだった。
クライマケア・シカレナ、彼女に違いなかった。あれから何十年も経っているのに彼女はまだ若々しかった。きっとスーメラーシムの香炉から特別な力を受けているのだろう。ガマスル・ファグの住人は全て香炉の力を生命の器に流し込むことが許されていたが、その量は均等というわけではなかったのだ。
ランフォは最後に彼女が自分を殺そうとした時の声をはっきりと聞いていたのだ。意識の底の夢の中で。彼は恐ろしくて樽の陰でしばらく体を震わせていたが、なかなか震えは止まらなかった。ここで止まっていてはいけない。ランフォはふらつきながら裏通りの方へ歩くと、やっと普通に歩けるようになった。
それから村を出て、ランフォはすぐにソチナ・ズムの待つキャンプ地に向かって帰ろうと思った。しかし、それには思いがけない困難を強いられた。村の周辺に泥棒除けの結界が張り巡らされていたのだ。村に来るときにはなかったのだから自分が来たのがばれたのかもしれなかった。その結果は力は強くはないが、その光のクモの巣に触れるとそれを張った術師に感知される種類の物だった。すぐに魔術師たちに駆けつけられたら、ランフォにとって致命的な危険にさらされてしまう。ランフォはその周りを嗅ぎまわってなんとか迂回路を見つけようとした。しかし、結界のクモの糸は極めて巧妙に張られていた。土の中を掘ってトンネルをつくろうとしても、そこにも菌糸のように伸びていたのだ。仕方なしにランフォはごく瞬間的に透明化の魔法を自分にかけて、結界を潜り抜けたり、また、一瞬だけ結界の神経を眠らせる魔法をかけたりして少しずつ村から離れて行った。
たった今、彼の前に見回りの兵士が現れたらどうしようもなかった。それぐらい、彼にとって透明化の魔法は難しいものだった。
もう何年かイガメークのツタで訓練を受けてさえいれば、また、スーメラーシムの香炉の力を得ていさえすれば、そんな魔法は何百回でも容易にかけれただろう。
ランフォは疲れ果てると土の中に穴を掘って身を埋めて眠った。もう見つかるか見つからないかなんてどうでも良くなっていた。休まなければすぐにも死んでしまうかもしれなかったのだから。彼は急いでかろうじて背中の毛に僅かについた朝露をなめて命をつないだ。結局なんとか無事にキャンプ地にたどり着いたときにはそこから出発してから、三日の時間が過ぎてしまっていたのだった。
彼のイ・サナとゲ・サナは日光をたっぷり浴びて本当に元気そうだった。その足元にうずくまると、ランフォはすぐに寝息を立て始めた。辺りは静かな夕暮れが訪れていた。闇はもうすぐその醜い野獣の体を隠してしまうだろう。ずっと変装していたいと思っても彼の魔法は丸一日持たなかったのだ。彼はそれでも町に行き、もちろんガマスル・ファグ以外の町なのだが、色々物を物色したりこそ泥したり、詐欺師の真似事をしたりして生きていくしかしかたがなかった。それがどんなに危険であったとしても、彼は本当は人間であることを忘れたくなかったのだろう。
>五章に進む >homeに戻る
Copyright (C)2004-2018 Yoshito Iwakura
http://lezarakus.nobody.jp/
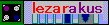
四章 ケサリーの竜
ランフォは寒気に身を震わせて目を覚ました。辺りはミルクのような朝霧でしっとりと覆われていた。おっと、気を付けなくてはいけない。背中の棘についた朝露が地面に落ちてしまってはもったいない。ランフォはすばやくなれた手つきで朝露を集めると、大事そうにペロペロなめ始めた。すると、だるくてしかたがなかった体に力が戻り始めた。生命の器の中の火が今日の分の燃料を得て、喜んで燃え始めたのを確かに感じた。立ち上がってそっと振り返ると、彼の育て上げた、サボテンの魔法生物ソチナ・ズムが昨日の姿勢のまま立っていた。しかし、彼の歩く音を聞いてうれしそうに駆け寄ってきた。その間接は何時もどおりギクシャク音を立てていた。ランフォは火を起こして濃いお茶を入れると、冷えたハムをほお張りながらそれを暖めるように、少しずつ口の中にカップを傾けた。
思えば、あれから何十年も経ったものだ。日陰の魔法使いが自分の背中にこんな恐ろしい毛を生やしてから。何度その毛をむしり取ったか数え切れないぐらいだ。でも、日陰の魔法使いは彼を捕まえて何度も殴ってから気を失わせると、すぐに彼の背中からするどい棘を生やさせる毒薬を準備し始めたのだった。それは耐えられない苦痛を彼に与えもしたが、そのおかげで彼は今も生きているのだ。ランフォが野獣の魔法使いと呼ばれる由縁となったその棘の役割は彼にとって重要だった。その棘につく自然の魔法力の凝縮されたものをなめ取ることによって彼は生き延びているのだった。彼の生命の器は今も継ぎはぎだらけだったので、いくら魔法力の油を溜め込んでいても少しずつ穴からもれていってしまうのだから、普通以上の特殊な魔法力の収集機を絶対に必要としていたのだ。
しかし、なぜ日陰の魔法使いは自分のことを助けたのだろう? ランフォは今になって疑問に思った。やさしさからだろうか? そんなはずはない。彼がもし死にかけたランフォを見つけたとき、やさしさと呼べるものを持っていたとしたら、ランフォを見殺しにしていただろう。それにずっと一緒に暮らしていても数回しかまじまじと見る機会のなかった、皺だらけの顔にはめ込まれたガラスのような瞳には表情が映し出されたことはなかった。まるで、地面に捨てられたガラス球が曇り空を空ろに映しているのと同じような感じがした。ランフォを拾った理由は偶然、良い実験材料が無料で転がっていたからというだけだと、ランフォの心の中の日陰の魔法使いは答えた。彼はいつも灰色のマントを着ていて、かげろうのように歩いた。彼だって本当は普通の人間なのに、何か目を反らせたいような雰囲気をしていた。
日陰の魔法使いがランフォの心の中だけの存在になったのは三十年ぐらいは前のことだった。ある朝突然、しわくちゃの置き手紙だけが残されていた。手紙にはただ、自分の実験室を彼のために残すということと自分はもうここに戻ることはないだろうと書かれていた。
ランフォはその時、日陰の魔法使いの実験室から徒歩で一日ほど離れたところにある、ガマスル・ファグの町に彼が行って、町の番兵に撃ち殺されている様子を想像した。灰色のマントが小さく赤く燃え上がる様子を。馬鹿げた空想だった。彼は無駄に死ぬことなど決してしないだろう。
彼は何か極めて重要な用事で出かけたのに違いなかった。今までなら彼が家を開けるとき何時になったら戻るか、書き置きなどせずにランフォに背中を向けたまま呟くのが常だった。「何かまた、恐ろしいことをしているのに違いない。」ランフォは背中の棘が震えて擦りあってパチパチ音を立てた。手紙の最後にはまたこう書かれていた。
「もう間違ってもお前は自分の背中の毛を抜いたりしてはいけない。私はもうお前の毛を生やすことなど出来ないのだから。」
ランフォは今、皺だらけになった自分の頬を触ると濡れているのを感じた。彼はまだ、そんな大昔の人の事を思い出して泣くこともあるのかとすこし驚いていた。そのしゃくりあげる声を聞いて、ゲ・サナとイ・サナが不思議そうに顔を摺り寄せて来たのを、彼は喜んでそっと撫でてやった。
「さあ、出発だと言いたい所だが、お前たちは今日は留守番だ。私はケサリーの町の近くにある、村に行って情報を仕入れてくる。大丈夫だ、心配するな。お前たちには誰にも見つからないように姿隠しの呪文を唱えてやる。」
テントを畳んでから、ソチナ・ズムたちの佇む近くに置くと、彼らに姿隠しの呪文を唱え始めた。すると、彼らの姿がうっすらとかすんでよく見えなくなっていった。完全に姿が消える訳ではないが、旅人がよっぽど目を凝らさないかぎり見つけることは出来ないだろう。それにランフォは念のために、焚き火の跡に砂をかけたり葉っぱをまぶしたりして入念に隠すのを忘れなかった。
これで良し。ランフォは自分のためのザックを背負うともう一度サボテンで出来た馬たちのことを振り返った。今日は少し曇りかけているが、うまく彼らのところに日光が届けば良いのだが。そうすこし考えてから、彼はすばやくこんもりと茂った藪の中に飛び込んで行った。耳元でする、葉っぱのこすれあう感触が心地良く流れ去っていくのを感じてうれしくて彼は小さく吠えた。その声を聞いて彼が元は普通の人間だったことが分かる者は多分いないかっただろう。
その小さな隠されたキャンプ地に彼が戻ったのは三日も経ったあとだった。ランフォはとても疲れた表情をしながら、ソチナ・ズムにかけた呪文を解くと地面に座り込んでしまった。ケサリーの町の近くはとても恐ろしいことになっていた。その近くの村でさえ、王の派遣した千人もの兵士たちであふれかえっていた。もちろんその中には彼の天敵あるとさえ言える正統な魔術師たちも何人も加わっていた。ランフォは入念に変装していたが、彼らに近づかないように気をつけた。彼は村人の格好をして村の酒場に潜り込んだ。魔術師たちはめったに酒など飲まないことは分かっているのでそこが一番安心できる場所だった。彼らは精神の極度の集中を魔法を使うのに必要としていたが、酒を飲むと意識が乱れるので、そんなものを進んで飲むはずがなかったのだ。
村の小さな酒場は馬鹿げた任務に絶望した沢山の兵士たちで、昼間からほとんど満員だった。村人らしい客がいなくて返って好都合だった。
ランフォはしばらくぶりに吸う、人間の体臭に吐き気を覚えた。はやく森に帰って湿ったコケの匂いでも嗅ぎたい。そう切実に願ったが、しかたがなかったので、何度も少しずつ人間の匂いを吸い込んで鼻を慣らしていった。数分してランフォはカウンターのバーテンから一杯ビールを買うとそれを手に持って陽気に歌いながら、テーブルについていた兵士たちに目掛けて乾杯と大声を上げた。
その体格の良い若い兵士たちは、突然の変わったじいさんの登場に面食らっていたが、気にせずランフォは空いている席に潜り込んでしまった。
「兵隊様たちもたまらんでしょう。ケサリーの恐ろしい竜と言ったらもう。ここにいて何もしなくても魂を抜かれちまいそうになるもんです。」
兵士は焦げたソーセージにかぶりつきながら言った。
「良く知ってるなじいさん。あの竜は魂を食うんだとさ。魔術師の連中は魂そのものを食うのではなく、生命の源となる魔法力を音もなく食い漁るとか言ってたけど、俺たちにそんな難しいことを言われてもな。」
もう一人の少し背の低いやせた男が薄茶色の陶器のカップから口を離すと、心配そうに呟いた。
「俺たち、本当に大丈夫だよな。先遣隊みたいに殺されるのは嫌だぞ。」
「そんな、暗い顔すんなよ。なんとかなるって、ガマスル・ファグからも応援の魔法使いが来てくれたしな。奴らは普通、王の軍隊なんかに誰か派遣することなんてありえないらしいが王は大金を払って雇ったんだろうよ。うらやましいよな。
だけど、そのおかげで俺たちはいつも通り生きて帰ることができるさ。なんでもガマスル・ファグの魔法使い、何て言ったかすごいおばさんなんだがそれが魂を抜かれずに済む方法を考えてくれたらしい。何でもその竜は光の力を使って俺たちの魂を抜き取ろうとするらしいから、奴の使う特別な光さえ俺たちの目に入らないようにしさえすれば、怖くも何ともないらしい。俺は装備班だから一足早く見せてもらえたんだけど、用は変なでっかいサングラスさ。そんなもので奴に無敵になるなんてね。」
「そうか、それで、お前がさっきから落ち着いてる訳がやっと分かったよ。」
「だから、後は飯でも食って力を付けるだけさ。なあ、じいさんもしょぼしょぼしてまってかわいそうだし、こんな干からびたソーセージでも良かったら食ってやってくれよ。」
居眠りをいているふりをしていたランフォは、臭い匂いの肉の塊を少しだけ千切ると口の中に入れた。よくおしゃべりをする薬をもってきたのだがそれを飲ませる必要もなかった。こいつらは、守るべき機密という言葉を知らないらしい。その後、話の風向きは都に残してきた女たちのことに移って竜の事はこれ以上聞き出せないのが分かったので、「ちょっともう老人ですので眠くなって来ましたのでおいとまさせていただきます。」そうふらふら立ち上がって店を出た。その親切な兵士は心配して、気付けの薬まで持たせてくれたのだった。バーテンはそんなじいさんを見たことがないので最後まで不振そうな表情を崩さなかったのだが。しかし、もう十分な情報を得られた。彼らは五日後にケサリーに旅立つらしい。ランフォはその竜が息の根を止められた後に立ち寄れば、うまく竜の糞を手に入れることが出来るだろう。もし、彼らが失敗していたとしたら、糞を手に入れるのが難しくなってしまうだろうが、その時はその時だった。
村の小さな大通りに出て、後ろを振り返ると砂埃の向こう側から魔術師の集団がやって来るのが見えた。ランフォは驚いてすばやく樽の陰に隠れたが、向こうは何も気付いた様子はなかった。ほっとして様子をうかがうとその集団の中に意外なものを見た。その魔術師の一人はガマスル・ファグのイガメークのツタの魔法衣を着ていた。そうだ、奴らが来ているんだった。今のうちに村から離れるのが得策か。ランフォは立ち去ろうとして、腰を伸ばすと、砂の混じった強い風が吹いた。それにイガメークのツタの魔法使いのマントのフードが一瞬だけはじかれるように降りてしまった。その人はすぐに風が行ってしまうとフードを元に戻したが、その横顔は忘れもしない人のものだった。
クライマケア・シカレナ、彼女に違いなかった。あれから何十年も経っているのに彼女はまだ若々しかった。きっとスーメラーシムの香炉から特別な力を受けているのだろう。ガマスル・ファグの住人は全て香炉の力を生命の器に流し込むことが許されていたが、その量は均等というわけではなかったのだ。
ランフォは最後に彼女が自分を殺そうとした時の声をはっきりと聞いていたのだ。意識の底の夢の中で。彼は恐ろしくて樽の陰でしばらく体を震わせていたが、なかなか震えは止まらなかった。ここで止まっていてはいけない。ランフォはふらつきながら裏通りの方へ歩くと、やっと普通に歩けるようになった。
それから村を出て、ランフォはすぐにソチナ・ズムの待つキャンプ地に向かって帰ろうと思った。しかし、それには思いがけない困難を強いられた。村の周辺に泥棒除けの結界が張り巡らされていたのだ。村に来るときにはなかったのだから自分が来たのがばれたのかもしれなかった。その結果は力は強くはないが、その光のクモの巣に触れるとそれを張った術師に感知される種類の物だった。すぐに魔術師たちに駆けつけられたら、ランフォにとって致命的な危険にさらされてしまう。ランフォはその周りを嗅ぎまわってなんとか迂回路を見つけようとした。しかし、結界のクモの糸は極めて巧妙に張られていた。土の中を掘ってトンネルをつくろうとしても、そこにも菌糸のように伸びていたのだ。仕方なしにランフォはごく瞬間的に透明化の魔法を自分にかけて、結界を潜り抜けたり、また、一瞬だけ結界の神経を眠らせる魔法をかけたりして少しずつ村から離れて行った。
たった今、彼の前に見回りの兵士が現れたらどうしようもなかった。それぐらい、彼にとって透明化の魔法は難しいものだった。
もう何年かイガメークのツタで訓練を受けてさえいれば、また、スーメラーシムの香炉の力を得ていさえすれば、そんな魔法は何百回でも容易にかけれただろう。
ランフォは疲れ果てると土の中に穴を掘って身を埋めて眠った。もう見つかるか見つからないかなんてどうでも良くなっていた。休まなければすぐにも死んでしまうかもしれなかったのだから。彼は急いでかろうじて背中の毛に僅かについた朝露をなめて命をつないだ。結局なんとか無事にキャンプ地にたどり着いたときにはそこから出発してから、三日の時間が過ぎてしまっていたのだった。
彼のイ・サナとゲ・サナは日光をたっぷり浴びて本当に元気そうだった。その足元にうずくまると、ランフォはすぐに寝息を立て始めた。辺りは静かな夕暮れが訪れていた。闇はもうすぐその醜い野獣の体を隠してしまうだろう。ずっと変装していたいと思っても彼の魔法は丸一日持たなかったのだ。彼はそれでも町に行き、もちろんガマスル・ファグ以外の町なのだが、色々物を物色したりこそ泥したり、詐欺師の真似事をしたりして生きていくしかしかたがなかった。それがどんなに危険であったとしても、彼は本当は人間であることを忘れたくなかったのだろう。
>五章に進む >homeに戻る
Copyright (C)2004-2018 Yoshito Iwakura
http://lezarakus.nobody.jp/
