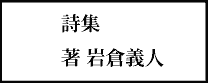「オレンジ・キャンディー」
その白い紙筒を手に持った、灰色の服の男の子は、
案の定、僕の分身だった。
僕はその男の子にドクダミの星型の空気を割り当てて、
僕は自分のためだけに、工場の白亜色の壁と空と不安とを
目のレンズに映す。
僕の役割は、灰色の服の男の子が、持っているはずの
白くてとんがっている紙筒を、
一度も見詰めないことだった。
僕のいるところは、その男の子のいないところだった。
僕のいないところには、いつも、
その男の子の甘い、オレンジの皮膚の香りがしていた。
その子はオレンジを踏み潰して水たまり色の空を、
オレンジ・キャンディー色に変えた。
それは腐ったオレンジを踏み潰して、オレンジ・ジュースで
僕の顔をオレンジ色に変身させて、ベタベタにするのが、
そいつの作戦だった。
僕はその男の子にいつも唾を吐きかけたくて、
いつも口に唾を溜めようとして努力していた。
そのために思い出すのはいつもオレンジ・キャンディーだった。
僕はその子の紙筒に、目を反らして、
唾を一滴でもかけられたら、
そのゲームは僕らの勝ちのはずだった。
僕は本当の事を言うと、
その男の子のほっぺたを殴りつける事だけを
夢に見ていた。
だけど、僕の目には工場の白亜色の空しか見えなかった。
僕の目には工場の白亜色の空しか見えなかった。
その男の子を殴りつけたときの、こぶしの感覚を空想して、
僕は絶え間なく、興奮していた。
腐ったオレンジを殴りつけた感覚はすてきだった。
その男の子を抱きしめたときの感触はすてきだった。
けど、だけど、吐き気がした。
オレンジ・キャンディーの香りだった。
でも、その男の子の背中がふるえていなかったのは
悪い気は、しなかった。
僕は吐きかけるためのつばを、
その男の子のオレンジのキスで
吸い取られてしまった。
僕は進んでそのゲームをダメにした。