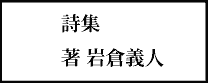犬の毛玉
そんなもの、どうだっていいだろと
僕は手に握っていたものを捨てた
それは真っ白な毛と真っ黒な毛が入り交じった
毛の団子だった
その毛の持ち主は三日前に死に
また四日後に生まれてくるはずだった
赤錆色の月、それが徐々に口を開け
にんまりと笑った
今からそれが僕の魂を食い尽くすよと
明るい声で犬のティーリは答えた
三日前の明け方にティーリはトラックに
ひき殺されて死に
四日後にその子供たちが彼女の毛玉の中から
生まれてくるはずだ
見つけだされないように洞窟の中で
息をひそめていても無駄だ
ティーリはすべての物の臭いをかぎ分け
闇の中を走ってくる
その足音。
僕は赤い花をばらして地面に敷き
その足音が聞こえないように気をつけた
だけどティーリはいつの間にかやってきて
僕の手のひらに彼の毛玉を乗せた
秘密という名の毛玉
ティーリの口からは
いつも透明なよだれがしたたっていた
新しい夜明けとそれに閉じこめられた昨日という時間
それを囲むようにして笑っている人々
金色の光の中で人間たちはにじむように
溶け合っていて
僕はその中に入っていくことは
できなかった
なぜなら彼らは石でできていて
三日前にハンマーでくだかれてしまったからだ
石をハンマーで砕く音
それを聞きながら僕はゆっくり眠りについた
明日になれば
巨大な蛇がやってきて
それをすっかり飲み込んでしまうだろう
ただ、残される物は彼らの髪の毛
それをティーリがやってきて
闇の中に埋めるのだろう
闇の味はティースプーンに満たされた蜂蜜に似ていて
一杯目はおいしいが
二杯目は胸をムカつかせる
だから二杯目以上は
ティーリにくれてやるのが
賢い選択というものだ
明け方がやってくると
月は太陽の光の中に閉じこめられて
叫び声をあげることもなく
静かに死んでいく
それでもやっぱりそれに納得できなくて
人は真夜中にドアをたたくのだろう
自分自身の恋人を返せという意味で
そのたびに僕は
オレンジの皮を
ちょっとずつ剥いていって
その破廉恥な臭いを楽しみながら
君のことをかんがえるのだろう
赤いナイフをくわえたティーリがやってきて
それを切り裂くのを
僕はただまっているつもりだよ
だってそれは単なる妄想にすぎないからさ
明け方になると
ティーリがやってきて
僕の手のひらから
皮を剥かれて裸になった
オレンジを盗みとり
彼はそれをかみ砕いて
こう叫ぶだろう
自分はもうここには存在していないと
明け方になると
悲しい歌は終わってしまい
ただの気の抜けたシグナルに変わってしまうんだろう
僕はそれに挨拶をして
それからそれの手を握り
こう言うだろう
「ティーリはもう一度やってきて
それから僕を傷つけるだろう」と
だけどそのあとはもう知らない
青空の光はすべてを凍り漬けにするからだ
神様とやらがそれを望んだからであり
僕自身がそれを望まなかったからであるからだ
ティーリは塩漬けニシンが好きだった
だから僕はニシンを瓶に閉じこめて
海に返してやることにした
それがやっぱりニシンにとって
幸せであるのに違いないからだ
ティーリの胃袋の中よりも
海の底の方が広いだろう
いくらティーリが大食らいであったとしても