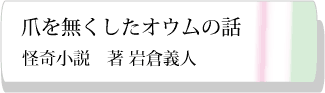2
「わしが女郎屋に通いだしたのには訳がある。
皆はわしがいい年して色狂いになったとか言っていただろうが、本当はそうじゃなかったんだ。
わしはたった一羽の文鳥に会いにいくためにそこに通っていた。
その文鳥は女郎のくせに変わったところがあって、自分が気に入った客だけを相手にしていた。
もちろん、それが許されるだけのものはあったのかもしれんが。
その文鳥の名前を仮に沢桜とでもしておこう。
とにかく、その沢桜の変わったところというのは、お前にはまだわからんだろうが事をしとる最中にお客の目玉をつついてしまうところじゃった。運悪く目が潰れたものもおったそうだが、沢桜はそれを責められることもなかった。
ある人を除いてな。どんなにかわいくて力のある女郎でも目玉をつついても良い相手とそうでない相手があるもんだ。
そんなことはあの娘はよく知っとったはずだが。それでも、あるとき沢桜はある人の目を潰してしまった。それで、その男が気を失っているうちになんとかしなければならなかった。
目を覚ましたときには大変なことになるのは目に見えていた。
そのとき、わしはそれを相談されてどうしようか迷った。
わしは沢桜を助けるために、知り合いの霊媒師に頼んで目を取り替えてもらった。代わりになったのは鳥の目ではなく、蛇の目だったらしいがそんなことはどっちでもよかったんじゃ。
その目を取り替えられたフクロウは何も気がつくことがなく、上機嫌で宿を後にしたらしいからな。
そのときに霊媒師に払った代金が例の家から持ち出した胡桃というわけだ。
お前には悪いと思っとるが、うらまれてもしかたがない。」
そこまで話すと祖父は障子の向こう側でケホケホと力なく咳をしました。
大変な怪我をしていて、そんなことを話していたのですから、疲れて血でも吐いていたかもしれません。
私はそんな祖父の言い訳を聞いて、馬鹿なことにすっかり信じ込んでしまいました。
今思うと、家のものに対する不信が私と祖父との間で強い絆になっていたのかもしれませんでした。
だいたい、その文鳥の女郎を助けるためとしたって、いくらなんでも何年も家を空ける理由にもなりませんから。そんなことに気づいたのもやっと最近なのです。
しかし、今更祖父の不平を述べてもなんの解決にもなりませんから、先を急いでお話しようと思います。
祖父が女郎屋を追い払われたときの話です。
祖父は言いました。
「わしはだんだんに胡桃を金に換えて支払いに使っておったが、どうにもならんときがついにきてしまった。わしは今度は沢桜に助けてくれと頼んだ。その時に奴は言いおった。
「分かりました。助けてあげます。その代わり、私があなたに何をしても許して下さると約束してください。」と。わしは目を突付かれると思ったからしばらく、返事もせずに目をしばたいておった。
すると、「大丈夫です。心配なさらなくても。あなたの目を奪ったりしません。」
そんな風に沢桜は言ったんじゃ。
わしは安心して沢桜の注いでくれた酒を飲んだ。本当はもうどうなってもよかったんだ。
多分その酒の中に眠り薬かなにか仕込まれていたのかもしれん。
わしが目を覚ますと、おかしなことに気がついた。わしの小指の爪が無くなっていた。どうしたんだ? と沢桜に聞くと彼女は笑って答えた。はい。食べました、と。
わしの爪がなくなっていたのにも関わらず、それほど痛みは感じなかったし、木に止まるときでも、小指の爪は必要ないだろうと思えたので別に気にしなかった。
それから、彼女は毎日一枚ずつわしの足の爪をはいでいった。
今度は薬で眠らされることもなく、目の前で沢桜はわしの爪を剥ぎ、おいしそうに食べていった。
まるで、桜の花びらでも飲み込むような優雅さじゃった。
わしはそれを見てうっとりとした気分を味わったもんだ。
そうこうするうち、わしの足の爪も全部なくなってしまった。足先が膿み始めたのか、痛くてしかたがなかった。それにそんなに爪が早く生えるものでもなし、どうすればいいのか彼女に聞いた。
そしたら、こう答えた。「あなたにはもう用はないと。」
それから、わしは用心棒の鳶(とび)の助に頭を殴られて、通りに放り出されてしまった。
わしはしばらくして目を覚ますと、自分の目の前に大きなごろつきの野良猫がいるのにやっと気がついた。わしが死んでいるのかどうか、伺っているらしかった。わしはなんとか猫の突き出した薄汚い爪をかいくぐって、近くの木の上に飛んでいった。
そのときじゃった。わしの足にとんでもない激痛を感じたのは。爪を剥がれて膿んだ足ではとても枝に止まってなどいられなかった。わしはなんとか羽ばたいて地面に降りた。だが、はげしく地面に叩きつけられてしまった。
わしは朦朧とする意識の中でこう思った。沢桜はこうなることを知ってわざとわしの爪を剥いでいったんだ、とな。
わしたち鳥には羽根と翼が一番大事だと思われているが、足もその次に大事じゃ。
お前はそのことを忘れるなよ。
そうして地面で休んでいると、すぐにまた、さっきのごろつきの野良猫がやってきた。灰色をした気持ちの悪い奴だった。奴は生贄がいることを知って、仲間を呼んだらしかった。
わしの周りでは今でも奴らの吐き気のする声が聞こえるようだ。」
そこまで言うと祖父は死んだように静かになってしまいました。
耳を凝らすとかすかな寝息がしていたので、眠っていたようです。
それからすぐに祖父はオウム病院に連れていかれましたが、家に戻ることは二度とありませんでした。」
虫かごの中のオウムの話もこれでやっと終わったようです。
彼自身も疲れてしまったのでしょう。
その時の彼のおじいさんと同じようにかすかな寝息を立て始めました。
しかし、次の日の朝にはそのオウムの体は残念なことに冷たくなっておりました。
奇妙なことに彼の足の爪が無くなっていましたから、夜中のうちにそれを自分で剥いで飲み込んでしまったのでしょう。そうすることで、文鳥の沢桜のように何かしらの力が得られるとでも思ったのでしょうか。
冷たくなったオウムの口元を見てみますと桜色の爪が一枚くわえられておりました。
終 「爪を無くしたオウムの話」