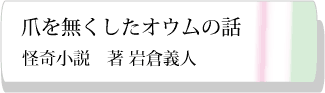1
「今更取って付けたように言うまでもありませんが。」
と、私が昨日道端で拾ったしょぼくれたオウムが言いました。
「私はオウムですから、私の祖父も当然オウムの姿をしておりました。」
そう言ってオウムは狭苦しい虫かごの中で、かゆそうに自分の体を口ばしでかきむしりました。きっとノミでも住んでいるのでしょう。かわいそうに羽根の根本が血で滲んでおりました。
「そりゃあ、当たり前だろう。」と私がつぶやきますと、オウムはいら立たしげに首をもたげました。
「私の祖父は私が三つのときに家を出て、辛子通りの女郎屋に入り浸るようになりました。
そんな年にもなってきれいな女郎の文鳥に恋でもしてしまったのでしょう。
祖父は家にあった胡桃(くるみ)を知らぬ間に持ち出して彼女に与えてしまいました。その時までは家には八つ胡桃があったのですが、祖父は五つまで持ち出してしまいました。
お分かりになられますでしょうが、胡桃は鳥の世界での貴重な財産なので御座います。ですから、祖父のせいで家がいっぺんに傾いでしまいました。
私はまだ幼かったので良く分かりませんでしたが、家の者は大変苦労したらしく、「じいさんは死んだと思え!」と言い聞かせられておりました。
それで、ちょうど私が五つになったころでしょうか、祖父が這うようにして家に戻ったのです。
ですが、私は祖父の姿を最後に見てから数年経っておりましたから、彼の姿を見てもうす汚いオウムだと思う以外、何の思いも沸き上がって参りませんでした。
ただ、なんとなく、こいつのせいで皆が酷い目にあったと言い聞かせられておりましたから、漠然とした憎しみを思い描いたのであります。
こいつがいなければ殻ばかり混じったヒエを食わなくて済んだとか、学校に行った時に仲間にネズミの穴の中に追っ払われたりしなくても済んだんじゃないかとか、様々なことが胸をよぎりました。
その時に同級の仲間が私に言った言葉は思い出したくもありませんが、お前はネズミの女郎を嫁に貰え、そんで、カビの生えたチーズに穴でも掘って新しい巣にでもしてろとかなんとか言ってましたが。
それでその時の祖父の話ですが、祖父は途中で野良猫にでも追いかけられたのでしょう、体中に目も当てられないぐらいの傷を負っておりました。
彼が倒れたまま玄関先にいつまでも放っておくわけにもいかず、私の家にまだ一人だけ雇われていた下男が、すぐに片付けてしまうだろうと思っておりましたが、私の母がすぐに奥の部屋に運び入れるように言いました。
私はそのようすがあんまりに恐ろしくて、障子の影から覗いておりましたが、しばらくして呼ばれたお医者様の声が外にも漏れて参りました。
その声は奇妙にしわがれておりましたから、今でもはっきりと覚えております。その時その声がこう言っているのが聞こえました。
「大変申し上げにくいのですが、お爺様は足に大変なお怪我をなさっております。
そのせいで木の上から転げ落ちたのではないでしょうか。
羽根に隠れてよく見えないでしょうが、内臓にも大変なお怪我をされております。
今すぐに大きな病院へとお連れになったほうがよろしいかと。」
私はそれを聞きながらやっと祖父の呪縛から解放される日が来たのだいう喜びが静かに湧き上がってくるのをこらえ切れませんでした。それはなんとも奇妙で恐ろしい感覚でしたから、とまどってしまいました。誰だって誰かが死ぬのを自分が密かに喜んでいるのを知って冷静でいられる人なんて、おりますでしょうか。」
オウムはそこまで言うと急に今までしゃべり続けていたのがうそのように黙り込んで、暗い顔をしました。それからひとしきりまた、口ばしと爪で体と掻きました。
そんなに掻いたら逆に悪くなってしまうのではないかと大層心配しましたが、しばらくしてやっと体のかゆいのが治まったようで、こんどは虫かごの隅で体を小刻みに震わせ始めました。
先ほどから、半開きにした窓から、夕暮れのひんやりとした風が入り込んできていましたから、それが嫌だったのでしょう。
私は窓を閉めながらオウムに話しかけました。
「いいんだよ。まだ、君は家に来たばかりなのだし、話はまた追々聞かせてくれればいいから。
君は出来るだけあったかくして、今は眠ったらどうだい。」
それを聞いて安心したのでしょう。オウムはトロンと目を半開きにしてましたが、頭を三度ほど振って眠気を飛ばすとまた、おしゃべりを始めました。私は正直、オウムのおかしな話にも退屈しだしておりましたので、逃げ出したい気分でした。ですが、彼は私の事を逃しませんでした。
彼は「今日でなければ話すときは無い。多分明日には死んでしまうだろう」と言いました。
そう言われては私だって彼を道端で拾った手前、無視することも出来ませんでした。
オウムはゆっくりと苦しそうに話し始めました。そういう口調が一番効果的だということをどこで習ったのでしょう。
「お話はもうしばらくで終わります。
祖父のお話の続きです。
お医者様は診断を下されたのち、すぐにお帰りになられました。
それに付いて母は見送りに玄関先まで行ってしまったので、私も自分の部屋に戻ろうと立ち上がったのです。
そのときでした。祖父の声が中からしたのです。
その声はこんなことを言いました。
「坊主か。そこにいるのは。
わしがまだなぜ生きているのか不思議に思って覗きに来たのか。」
私はしかられると思ってすぐに逃げようとしましたが、不思議と体が動きませんでした。それで、じっと障子の影から祖父のうめき声に耳を傾け続けなければならなかったのです。
「おやおや逃げんでもいい。
もうじきその必要もなくなる。
そうだ、逃げられんかったのはわしのほうじゃ。
お前にだけは本当のことを聞いておいてもらいたい。それがわしの最後の望みだ。」
その時の私はどうしても逃げ出すことが出来なくなっていましたので、黙りこくっていましたが、それを望みを聞き入れてくれる印と勘違いして祖父はまた話し始めました。