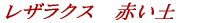
二十章 千切れた小さな握り拳
「千切れた小さな握り拳の植えられた野原。
見えない体はどこへ行ったの?
見ることの出来ない体は地面の下をうろつき回って
汚い地下の川を飛び越して
森に帰ってしまったのかしら。
それともガラスみたいに凍り付いて
地面を切り刻んで、遊んでいるのかしら。
そんなの手のある所を掘り返してみたらすぐ分かるはず。
でもリルファーがそんなことするなって言うから、
私は今はやめておくわ。」
誰にも聞くことのできない、初めてのレザラクスの歌
「アンフィ。アンフィ。」
リルファーは口の中でそうつぶやきながら町の中を歩いた。その声は死んだアンフィに聞かせるためでもなかったし、彼もそれを聞きたくないのは分かっていた。ただ、髪の毛の部屋の中で見た、小さなアンフィの口の動きをまねすると安心出来るからだった。
彼女はポケットの中に静かに丸まっているアンフィといつか別れなければならないと思うと、苦しくて何もかもだめにしてしまいたくなった。だけど、自分の体がバラバラになってしまうにしても、今はまだ彼の体を腐らせるわけにはいかなかった。
リルファーは、初めて手にした人の死体を一体どんなふうに扱えば良いのか分からなかった。そんな話はレザラクスの教則の中にも一言も載っていなかったし、誰も知っているはずはなかった。初めて産み出された死、そんなものと自分はいっしょにいるんだ。と思うと、彼女はやっと怖くなり始めた。だけど、ポケットの中にもう一度手を伸ばして、彼の体に触れると柔らかい皮膚の感じは彼女を慰めて、ひとりぼっちにならないようにした。
彼女は彼にあげた分の残りの死を使って、彼と一緒に見えない体を壊してしまおうかとも考えたが、彼は必死にそれを引き留めようとしていた。
リルファーは暗くなり始めた町の細い路地を歩きながらまず、この子の体が腐らないようにしてあげなくっちゃ。と思うと、薬局を探した。町の中央の通りに戻ると、もうほとんどの店がシャッターを下ろしてしまっていた。小さな白い光に包まれた薬局はまだ開いていた。彼女は店の中の太ったプラックスに包帯と消毒薬が欲しいと言った。
彼はどこも怪我をしていないように見える彼女をいぶかしそうに見ながらそれを包んだ。
「私はこれから苦しみの野に行くの。そこに生えている草の棘はとっても鋭くて、私の皮膚を切り裂くけど、この子と同じように私は痛さは感じないわ。」
そう彼女は試しに呟いてみたけれど彼の心には何の感情も引き起こさなかったらしかった。男は黙って包みをカウンターの上に置くと、勘定を言った。その値段はとても高くてリルファーには払えそうになかった。仮の神の子宮の中でもらった荷物の中に入っていた財布の中には一番近い、プラックスの職業養成所までの馬車代ぐらいしか入っていなかったのだ。彼女が財布の中身を何度も覗き込んでいると、男は待ちきれないように言った。
「あんたは知っているだろうが、町の神官医のいるお寺に行けばただで見てもらえる。明日まで我慢できるのなら、そこに行けばいいだろう。ただ、実際に怪我をまだしていなかったら何ももらえないだろうが。」
その言葉がリルファーの中に、ある考えを生み出させた。リルファーはお礼を言うと包みをそのままにして店を出た。あの包みを持って走りさえすれば、寺に行く面倒はなくなるのだが、もうこれ以上このしんきくさい目をした男と関わり合うのは嫌だった。
でもこれで、アンフィのために包帯をもらうことが出来るわ。ただ、自分が明日まで待てないことにすぐ気が付いた。そんなに待っていたら、彼の体が腐り始めてしまう。仕方なしに男に教えてもらった辺りを探した。町はとても狭かったのですぐに寺は見つかるだろうと思ったが、路地の裏を探し回って何周もしなければならなかった。
やっと見つけた門の所には診療所とではなく、神官医の聖所と書かれていた。薬局の男の言っていた通り、すでに寺の木の扉は固く閉ざされていて、押してもビクともしなかった。ただし、門には夜中に困った者は門を叩くようにと書かれていた。リルファーはすぐに門を叩こうと思ったが、このままでは何もしてくれないだろう。彼女は新しい神官衣のそでをめくると、腕の肌を見つめた。まさかこの子のためにまたこんなことをしなくてはならないなんてね。リルファーはリンゴを囓るように自分の腕に歯を食い込ませた。彼女は痛くて叫びそうになった。前はちっとも痛くなかったのに、もしかして体がプラックスに成りかけているせいかも。彼女は舌打ちすると、街灯の下に行って、思った通り血が赤く滴り落ちているのを満足そうに見た。懐かしい私自身の色。それから、急いで寺の門の前に戻るとこん身の力を込めて扉を叩いた。口から自然にわめき声が出た。「あなた達。私は怪我をしたのよ。開けないと扉を潰して、包帯をもらうから。」
しばらくして、門の覗き戸が開くと若いプラックスが顔を出した。その顔は「なんのご用ですか。申し訳ありませんが先生はお出かけになっています。助手の私で良ければなんなりと・・」彼がそう言い終わる前に、リルファーは血の滴り落ちる腕を彼の顔に突きつけた。しぶきは彼の顔にまともにかかって、それを拭った手を見た助手は驚いて悲鳴を上げた。門はすぐに開けられた。
診察室は寺の外観とは違っていて、全てが銀色に光っていた。ここには電気が引かれていて、彼がスイッチを入れると天井はまぶしく光った。彼女は珍しい光の棒を目が痛くなるまでじっと見つめていた。彼は黙って医療箱を取り出すと彼女の腕に包帯を巻いた。なんでこんなことをするのかとリルファーに聞く気も起きない様子だった。それでも、リルファーは言った。「私、たぶん明日も腕を咬みたくなって、それをするわ。そしたら、また、扉を叩くかもしれない。」
彼は驚いて彼女の顔を見た。また真夜中にたたき起こされて、それが永遠に毎日続くことになったら大変だと思ったのに違いなかった。
「私、あなたが巻いている様子を見たから、たぶん自分でも出来ると思うの。」
彼は彼女の気が変わらない内に急いで言った。「分かった。君に包帯と消毒薬をあげよう。だから、出来るだけ夜中にはもう来ないでくれ。」
部屋の中には銀色に光る巨大な金属の作業台があった。その上にアンフィを出して彼に包帯を巻いてもらうことを想像したくもなかった。たぶんアンフィはその清潔さに打ちのめされて、どこかに消えてしまうだろうと彼女は思った。私は彼のことを裏切ることは出来ないわ。そうならなくて良かった。リルファーは神官医の助手にお礼を言おうと振り返ると、すでに元通りに扉は固く閉まっていた。その扉はまるで今まで開いたことがないかのように見えた。ただ、血がまだ扉に光っていたから、自分がそこにいたのだということをリルファーは思い出した。
彼女は街灯の下でアンフィを取り出すと、消毒薬を染み込ませた包帯で優しく巻いていった。彼は永遠に治らない怪我をしたのかもしれなかった。それが死ぬっていうことなのかしら、それとも彼には怪我を治す必要がなくなったんだから良かったんだ、とも思えた。その回復力こそがプラックスがレザラクスを利用し続けた理由だったんだから。巻きながら彼の指を触ってみたが固まっていて動かなかった。よく見ると指の間の皮膚が溶けてくっつき合っていた。彼の手は生まれながらに握り拳のままだったのだ。手はとても綺麗にピンク色に光っていた。
そうやって包帯で巻いてしまうと彼がまた動き出す準備を始めたかのようにも見えた。だけども、リルファーは彼にもうそんなことはしなくても良いのよ。と言って慰めると彼の恐怖は収まったようだった。
リルファーはそれからどこに行こうか考えた。プラックスの旅行者のための無料の宿泊所が町のどこかにあるはずだったが、また閉じられた門を叩くことを考えると嫌になってしまった。彼女は月の明かりを頼りにして町の外れまで行くと、灌木の茂みの中に潜り込んでそこで眠った。レザラクスの塔にいたときも良くそんなことをしていたな。と思い出す暇もなく彼女を眠りの闇がくるみ込んでいった。
次の日、彼女の周りで牛の鳴く声がして目が覚めた。その辺りには小さな牧場があるようだった。町の中心に向かって歩きながら、どうやったら苦しみの野に行けるだろうか思いを巡らした。たぶん東の果ての方だろう。人間達はそこから十年ほど前には実際にここに来ていた。ただ、そこに行き着くことが出来ても、人間達のずっと前に死んだ死体達と廃墟を見ることになるだけかもしれなかった。でも、リルファーは彼らが生きている気がした。多分、こちらに来るのに飽きてしまっただけなんだろうか。それとも、もっと別の理由があるかもしれなかった。タルヒナーは彼らが死に絶えたとはっきり言っていた。だが、彼女が間違っていることだってきっとあり得る。彼女は全てのレザラクスとは一体だということが出来るだろうが、それ以外のことなんて彼女には何も分かりはしないのだ。
彼女は神の第二子宮の中で死ぬことを忘れ去らされて、逆に赤土の本を使ってプラックスをコントロールしている事を喜んでいたが、それこそが彼らの望んでいたことなのだ。彼らは自分の出来ないことを諦めて他者に潜り込み、隠れて成し遂げてもらおうとする。このかわいいアンフィだってそうだった。彼だって自分では作り出すことが出来ない完全な死を私にただで貰おうとしていたじゃないか。でも、リルファーはそれでも彼を許したのだった。
リルファーはこれから先、自分が捕らわれてしまうはずの肉体のみが残り精神が崩壊するとはどういうことなんだろうかと思った。彼らは体の殻の中に時間を失ってしまうみたいだった。そう考えるとやっと神の第二子宮の事が少し分かった気がした。そこは神の子宮ではなく彼らの失われた子宮の中だったのだ。それでその中で彼らは死にそうなレザラクスの体が壊れてしまわないように無時間を与えた。その無時間が副次的に彼女たちの精神を傷つけ続けたのだ。ふつうのプラックスはそんなことをしなくても簡単に体は滅びない状態になることが出来る。だから、彼らが最も恐れるのは体が先に死んで精神だけが独立して生き残ってしまうということなのだ。それがレザラクスの本来持っていた正体なんだろうか。
彼らはプラックスがプラックス自身に課したことの結果を嫌がり始めた、そして結局は最も忌み嫌う者にひれ伏して助けてもらおうとした。それで彼女たち自身にとってもそうすれば救われると、彼らは思ったのだ。
私はもうひれ伏す必要なんて無いわ。ちゃんともう心も体も同時に死ねる。そう言う自信があった。アンフィだけが本当の意味で信頼できる仲間だった。彼女はプラックスに利用される前の遠い過去のレザラクス達が最後に至っていた亡霊達が大気の中で薄まって、そこらじゅうを微かに満たしているのが、感じ取れそうな気がした。それはそうだ大気の主成分は亡霊で出来ているのだから。彼女たちは元々苦しみの野の境界線にいて、そこから野の方に喜んで飛び立っていったに違いがなかった。私はもう彼女たちを忌み嫌う側に付いてしまったんだろうか。
リルファーはまだ一向にプラックスへの変化を起こそうとしない自分の体を呆然と見下ろした。きっともう少ししたら、コーラルに黒い薬を注射されたときと同じような変化を起こしていくのだろう。
でも、たとえ自分が考えた通りであったとしたら、レザラクスの今持っている身体の面での回復力はプラックスから与えられたことになってしまう。コーラルの言う通り、もう二つのものは切り離すことが出来ない状態にあるのかもしれない。
とりあえず彼女は、苦しみの野と呼ばれた所になんとしても行ってみなくては、と決心して、村の外れの馬車の停留所を目指した。途中の道ばたの店でパンと牛乳を買った。パンは固くてぼそぼそしていたが、とても美味しかった。それを食べながら仮の神の子宮から逃げ出してから何も今まで食べていなかったことにやっと気が付いた。
乗合馬車の持ち主にまさか苦しみの野に行きたいと言っても取り合ってもらえるはずはなかったので、出来るだけ東の方面に出掛ける馬車を探した。だが、全ての乗合馬車は近郊の町に向かってしか走っていなかった。確かに旅行者がそこまで遠くに行こうとすることはよっぽど物好きがすることなのだろう。彼女は次に貨物馬車を順番に当たっていった。その方が長距離走る必要がある馬車に上手く出くわすかもしれなかった。彼女はほとんどお金を持っていなかったから、御者を手伝う代わりにただで乗せてもらえないか頼んだ。
東の方面に行く馬車は始めから僅かだったが、御者は彼女が見るからに貧弱なのとプラックスの訓練学校で御者の資格を取っていないことを理由に即座に断った。みんな親切にプラックスになったばかりなのなら、早く職業訓練学校に行った方が良いと勧めてくれた。
リルファーは考え直してそこに行ってから東を目指しても良かったのだが、ポケットの中でだんだん腐りつつあるアンフィがそんな遠回りを許してくれはしなかった。
彼女が途方に暮れていると、一人の若いプラックスの御者が声をかけてきた。さっき断った者の一人だ。「なぜ君は、そんなに東の方に行きたいんだい?」さっきから彼女のことを見ていたのだろう。リルファーはどう答えようか迷った。
「人間達の所に行きたいの。」
彼は馬の鼻面をしばらく黙って掻いてやっていた。
「人間て、君はそんなものをみたいのか。しばらく前までは乞食みたいな格好をしてやって来ていたらしいけど、今はこの国にはどこにもいないだろう。」
「東の果てにはきっといるわ。そこに行ってなぜ私たちの国に来るのをやめたのか聞きに行く。多分彼らは宗教心を無くしたのに違いないけど。」
「東の果てか。そこに奴らはまだしつこく生き残っているのか。でも、君はそんな所まで出掛けて行って、帰れなくなったらどうするんだ。帰胎を必要とするようになったりしたらどうする。荒野の真ん中で死の胎児になっちまったらどうしようもないぞ。」
彼は途方もない冗談を言っていたが、相手が黙っているので、関わり合いにならない方が得だと思ったのだろう。
「どういう訳だかは、別にこっちには関係が無いが、確かに俺は前の助手が喧嘩してどこかに行ってしまったから、新しく番をしてくれる者を探してもいるんだ。」彼が振り返ると、馬車の荷台に張り付けられた助手募集の張り紙がくしゃくしゃになって風に揺れているのが見えた。「職業登録所に行っても、現在希望者ゼロの掲示しか出ていない。確かに御者の国から支払われる給料は技術職の十分の一程度しかないからな。俺は馬が好きだからこの仕事を選んだんだが、間違いだったかもしれないと思ってるんだ。」
リルファーは彼に背中を向けて、馬のたてがみを引っ張っていた。馬は嫌がって身を捩らしていた。彼はそれを見ながら考えた。こいつは自分がどうなっても良いから東の果てに行って人間を見ようとしている。それが本気だったら、頭がどうかしているのに決まってる。こんな奴はほっといた方が良い。だが、その後彼の口をついた言葉は全く逆の意味だった。
「君が行こうとしている場所まではとても送り届けることは出来ないが、まあ良いや。乗りたければ乗れ。」彼女は顔を輝かしてありがとうと言うと御者の席に登った。
「おい。そこは俺の席だ。荷物は運んでやるが、自分の体は自分で運べ。君には馬のくつわを取ってもらう。」リルファーは驚いて席を飛び降りると、謝ることもせず、馬の前に突っ立っていた。はは。大変な役立たずの動物を一匹増やしてしまったぞ。俺は馬鹿の上に馬鹿を積み重ねる癖があるらしい。まったく仕様がないな。彼はぶつくさ良いながら地面に飛び降りてくつわの引き方を教えようとした。だが、彼が地面に着く前に馬車は勢い良く動き出した。彼女は上手く馬たちを操っていた。彼は自分が危うくひかれそうになっていたことを忘れて大声を出した。「おい。馬を引けるのは分かったから、ちょっと待て、今から地図を見せるから。」彼女は放っておいたら、簡単に国の果てまで行ってしまうだろう。それが西だか東だかは全く関係なしに。