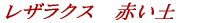
十七章 アンフィ
「そげの刺さる板に寝かされたまま、頭をもたげて巡らすと何本もの木の枝が空に舞うのが見えた。だが、いつまで経ってもその枝は地面に落ちなかった。最初私はそれが糸で空からぶら下げられているのに違いないと思ったがそうではなかった。木の枝の下に這いずって行って手を伸ばすと私の手は樹皮に触れた。つまり、木の幹は空白に食い荒らされていて見えなくなってしまっていたのだ。私は背中に流れる固まった血を手に取るとその透明な幹に塗りつけて、体を与えた。そうすると、驚くべき事に空中に投げ出されたままになっていた、木の枝達が一斉に地面に落ちてたたき付けられ、轟音を立てて割れた。」
タルヒナー・ウルクバクの回想 47ページより抜粋
その新しい不思議な死の子供が来てから、アンフィは夜中に目を覚ますとベットから抜け出て、その子の近くに来て、毎晩寝顔を眺めた。開け放たれた、廊下の青い終夜灯がかすかに部屋の中を照らしていたから、部屋の中にある沢山のベットに足をぶつけないで済んだ。急に監視するためにプラックスの教官が部屋を覗くかもしれなかったから、彼はベットと同じ高さに身をかがめて、その子のことを見つめた。その子はとても柔らかそうな唇をしていて、桃色に輝いていた。それを見ているとアンフィはいつも舐めてみたいと感じた。だけど、自分が舌を延ばすとまた恐ろしい黒い染みが姿を現せるのが分かり切っていたのでそれが怖かった。その黒い舌の染みで自分は昔とても楽しいことをしていたらしかったが、それがどんなものだったのか、さっぱり思い出せなかった。
彼はまた長い舌を目一杯延ばしてその染みを見ようとした。こんな暗闇の中だってそれは、暗闇に食われることもなくちゃんと見えるだろう。その勇気があるのなら、この子の唇にキスする権利だってきっとあるはずだ。アンフィは静かに閉じられた歯の門を開き舌を外におびき出した。部屋の湿った空気に触れると舌は敏感に震えて怖がった。今、その子を味わう時がやっと来たことが分かった。多分その子を味わえば、あの恐ろしく嫌な香りのシハレウにもまた耐えることが出来るようになって、またシハレウを口でくわえて絵を描くことだって出来るようになるのに違いないと思うと彼は興奮した。
そうして、もう少しで舌が唇に触れようとした時だった。部屋に差し込む青い淡い光の中に巨大な影が映った。アンフィは素早く床に伏せた。自分が倒れた音が教官に聞こえたかもしれなかった。彼の心臓は緊張してドクドク言ったが、その影が何秒かして音もなく消えてしまったのでほっとした。彼は時々頭を持ち上げて自分の位置を確かめると、出来るだけ音を出さないように気を付けながら、元にいたベットに戻った。汗ばんだ足の裏には黒い灰がべったりくっついていたがそれを払う気持ちも起きなかった。ただ、朝起きてからシーツの上にそれを見るとうんざりしてしまうというだけの話だった。何かその灰は自分の体から分泌されている様な気さえした。他の子供達は本当に何とも思っていないのだろうか。よく分からなかった。他の子供達はアンフィがいくら話しかけても余り答えてくれなかった。塔の最上階からここに降りてきたばかりの時は、同じ時に死の子供になったプラックスは良く笑いかけてくれたりさえしたのだが、ここ最近は食堂で小声で話しかけても、うるさそうに首を振るだけで何も話さずに顔を歪めた。自分以外の死の子供達はどこかおかしかった。
彼らは喜んで与えられたシハレウを飽きもせず使っていたが、アンフィはそれが忌まわしいことに思えて、それを使うのを止めた。すると不思議に夜中に目が覚めるようになっていった。アマは彼のことを叱りつけて何度もシハレウを手に握らせた。だが、彼は手で絵を描くことは出来そうになかった。そして、何度口にそれをくわえても、彼の舌は乱暴に押し出してしまった。偽りの死の子供達の父親は彼の舌の大きなインクの染みを指さして、君は呪われているのではなく、選ばれているだけなのだから何も気にしなくて良いんだ。君が前にここに来たときだって問題なく作業は行われていたのだから。と言ったが、彼が自分のことを蔑んでいることはその言葉によっていっそう明らかになっていくばかりだった。
だが、夜中に目を覚ますようになってから、不思議な物音がしているのに気が付いた。まるで、その音は石畳の廊下を何百人もの人が裸足で歩いているような感じだった。一度は、教官のプラックスに見つかるかもしれなかったが、廊下にまで出て行った。だが、そこには誰もいなかった。彼がいる階よりもっと下の方、シハレウの部屋の方からその静かな雨音のような響きがしているような気がした。もしかして、地下の部屋に本当に雨が降っているのかもしれなかった。だから、朝になると彼らが一生懸命描いていた全ての絵が消されて、元の白い壁になっているのだろうか。分からなかったが、教官に聞くことだけはいくらなんでもしなかった。彼らにここのことを尋ねることは厳しく禁止されていたのだ。
彼はいつか何が起きているのか確かめてみようと決心した。自分一人で真夜中にあの部屋に降りて行くことを思うと怖くて気が狂いそうだった。だれか一緒に行ってくれる人がいればどんなに良いだろうか。あの、新しく来た死の子供はどうだろうか、あの子だったらまだこの部屋に来てばかりだし、まだ話をしてくれるかもしれない。アンフィは明け方近くになってやっと眠れそうだった。そのもうろうとした意識の中で、今日あの子のベットの枕元に張られていた、名前を思い出した。イレアラ・カルス。彼がその子に期待していた名前となぜか違う気がした。では自分はどんな名前を期待していたんだ? と、問いかけてみたが、いつも通り答えはなかった。
次の日の朝食の時に、リルファーは奇妙な死の子供に声をかけられた。彼女は面と向かって、死の子供に話しかけられたのが初めてだったので、びっくりして口ごもった。その子は銀色の綺麗な髪をしていたが、皮膚は壁のようにぼろぼろはげ落ちそうだった。その唇はもごもご動き続けていたが、何を言っているのかさっぱり分からなくて困ってしまった。死の子供達の普通の会話はレザラクスのそれとは異なっているようだった。本当の死の子供達は多分何も習わずにそれを身につけるのだろうから、リルファーには予想も付かなかった。だが、彼らが授業の中でその言葉を使おうとすると、アマは普通の言葉を使いなさいと厳しく叱った。なぜ、その言葉を禁止する必要があるのかリルファーには分からなかったが、彼女には不都合はなかったので、ほっとしていた。
その、彼女よりも背が小さくて胸の高さぐらいしかない死の子供は朝食のトレイを持ったまま何か言ったが、少し考え込むと「あなたのとなりに座っても良いか?」と言い直した、レザラクスの言葉で。リルファーはなぜ共通の言葉であるカズルでなくレザラクスの言葉を彼が使ったのか驚いたが、「ええ。どうぞ。」と、カズルで答えた。
彼は黙って満足して席に着くと、くたくたに煮込まれ過ぎた野菜の煮物を美味しそうに食べた。スープを飲み終わると初めてパンを囓りだした。スープの皿には小さなエビの子供が残されていた。リルファーは彼がそれを口に含んだ瞬間びっくりしてすぐに吐きだしていたのをはっきり見た。「あなたはエビが嫌いなの?」その子は驚いて、リルファーの方を振り返った。彼にはその意味がよく分からなかったのかもしれない。リルファーは指を伸ばすと彼の皿の中のエビをつついた。彼はしばらくしてやっとリルファーの言おうとしていることが分かったらしかった。
「エビは嫌いじゃないよ。ただ、僕からエビは逃げたいと思った。だから、僕の口からエビを逃がしてやったんだ。」今度はたどたどしくカズルを使って答えた。「エビの方があなたを嫌っているの?それはもう死んでいるのに。」
その子は今度はもう何も答えずにスプーンでエビの首を千切り始めた。「そうか。もう逃げない。これはもう死んでいるのかもしれない。」また、レザラクスの言葉を使った。
その事をリルファーが聞こうとしたときに彼は言った。「僕はアンフィ・ブラスツゥラって呼ばれていた。アンフィ・ブラスツゥラをスプーンでつついて首を切られると分かっていても逃げなかったら、それはもう死んでいるんだろうか?」
彼はもう一度、リルファーのことを見た。「君はイレアラ・カルスという名前だ。僕が君に話しかけても逃げなかったのはなぜなんだろう。僕は今晩みんな寝た後にまた君に話しかけるけど、その時君は逃げようとするだろうか。」
彼女はその名前を聞いて考えたくもないものを思い出した。その子が本当にアンフィだったとするなら、彼女は逃げ出さなくてはならなかったはずだ。
だが、その子の事を怖がる必要なんてどこにもないはずだと自分に言い聞かせた。今アンフィが私の本当の名前を知ることが出来るはずがないもの。自分から言い出さない限りは。「どうして、夜に話しかけようと思ってるの?」そう落ち着いた気分で、リルファーが問いかけられる状態になった時にはすでに隣の席に彼の姿は無かった。
それからまたいつも通りの恐ろしい一日が始まった。蟻のように一列になって死の子供達は地下の教室まで降りて行った。まず最初に大きな空洞の部屋にこぶのようにくっついた小さな部屋に行くと、一人に一つずつ大きな机を抱えて運んだ。小さな部屋には入り口が二つあったから、運ぶ流れが滞ってしまうことはなかったが、それでも、小さな体の死の子供達にとっては大変な重労働だった。円形の形をした部屋の壁にぴったりくっつけて机を並べていった。部屋の中央の部分には全く机が置かれなかったので巨大な空間が開いた。当然元の机の入れてあった、こぶの部屋から近い方から並べて行ったので、最後に来た死の子供はその何十倍もの距離を運ばなくてはならなかった。死の子供にはとても大きな者やその腰ぐらいの大きさの小さな者までいたが小さな者ほど運ぶ力が弱かったから、運ぶのに遅れて遠くまで行かなくてはいけなくなりがちだった。
机を並べるだけで、一時間以上もかかっていたかもしれない。だが、そこには時計がなかったのでよく分からなかった。死の子供達は机の下に収納できるようになっている小さなイスを引き出すと壁に向かって座り、全ての机が並べ終わるのを黙って待った。
そうして、息を切らせながら運んでいると、何度も狭い通路や壁に激しくぶつかった。そのたびに部屋全体が机をぶつけた子供を非難するように大きな音を出して震え、反響した音はなかなか止みそうになかった。リルファーはその音を聞く内にそれがここに来たばかりの時に聞いた地響きの音だということにやっと気付いた。その音は彼女のことを必要以上に苛立たせた。この部屋はとてつもなく広い場所だったのに、彼女目がけて全ての壁が突進してきて、そのまま突き抜けていってしまう気がした。だが、自分の運んだ机に座り、目をつぶったまま音に耐えているといつの間にかその轟音は止んでいた。そして、うっすら目を開けると自分の目の前に真っ白な光り輝く新しい壁を見つけて、またシハレウを使う場所がちゃんと出来ていることに驚き、喜んだ。しかし、それに絵を描けるのはもっと後だ。アマ・エムルスルダが彼らの背中越しの部屋の中央に立ち、静かに話し始めた。
「死の子供達、埋め込まれた果実。壁に生えた羽。光り輝く血の香り。
あなた達はこれからだんだんに戻っていきます。死の暗がりの中に。」
言葉の最初の部分はいつも同じだったが、続きは毎朝変わっていた。アマがその言葉を唱えると、すぐ後に子供達が声をそろえて続けた。彼らの声はひび割れていてかさかさだったから、アマの声を聞き分けることが出来たのだが、その枯れ葉の中を沢山のねずみが駆け回るような音は全く部屋から抜け出せずに部屋の中に積もり始めた。アマの声は完全にその中に埋もれて、リルファーには聞き分けられそうになかった。しかたなく、隣に座った死の子供の口から出る言葉と同じような意味の言葉を一生懸命叫んだ。リルファーは苦しくなって、そこから逃げ出したくなったが、机に体が縛り付けられているように痺れて動けなかった。だが、そのまま声を出さなかったら、他の音に意識を踏みつぶされてどこかに行ってしまいそうだから、彼女は出来るだけ大声でわめき散らして他の鋭いナイフの群の様な音達を退かせようと努力した。そして、最後には自分の声が全てに勝って、他の音をすべて殺したと思った。リルファーは嬉しくなってまだ叫び続けたが、息を吸うために少し止めると、自分の声意外の全ての音が全く無くなっているのに気が付いた。
リルファーは驚いて辺りの子供を見て、後ろを振り返ると、アマはまだ部屋の中心にいて別にこちらの方を気にしている様子もなかった。彼女はほっとするとまた壁の方を見た。
数分してリルファーの最後の叫び声も壁の中に吸収されてしまうと、部屋には完全な静けさが訪れた。それを待ってからアマはまた話し始めた。彼は紙に書かれたリストをめくったのだろうか、かさかさした音がした。「エイサムズス、あなたは今日、死の子供の言葉を二回使いました。もう二度とここでは使ってはいけません。カリントファイ、あなたは死の子供の言葉を二十五回使いました。もう二度とここでは使ってはいけません。ポエシエーダ・イウあなたは死の子供の言葉を三回使いました。あなたには昨日も注意しました。もう二度とここでは使ってはいけません。」注意は永遠と続くようだったが、リルファーは不思議と一度も注意されなかった。それにその日は気を付けて聞いていたが、アンフィの名前も呼ばれた様子はなかった。彼は間違わなかったのだろう。
「あなた達はここではカズルを使わなくてはいけません。さもなければあなた達は死の世界から戻ることが出来なくなってしまいます。」そう静かにアマが言うのがやっと注意が終わったことの合図だった。
これが死の子供にとっての授業なのだろうか、レザラクスの時みたいに人間の作った呪われた物についてノートを取ったり、草の名前を覚えたりすることは無かった。リルファーにとっては無理矢理覚え込まされることが一切無かったので楽ではあった。このとても不思議な音の波に心を締め付けられることの苦痛を除いては。
それから、まだしばらく音を使った授業が続けられた。だが、すぐに他の死の子供達の声にアマの言葉がかき消されてしまうので、個々の内容の違いはよく分からなかった。となりの死の子供の顔を覗き込んでも飽きもせず声を出していたので、彼らにとっては違いがあるものなのだろう。またアマが読み上げたものを紙に書き取る授業もあった。それが済むとまた苦労して運んだ机を元の場所に戻さなくてはいけなかった。運びながらなぜこんなに無意味な運動をさせられなければならないんだろうと苛立たしく思ったが、壁にシハレウで絵を描く内にそんなことは忘れてしまった。しかし、今日は落としたシハレウを取ろうと振り返ったときに遠くから一人の死の子供が自分のことを見つめていることに気が付いた。白い光のもやの中で彼の姿が飲み込まれて今にも無くなってしまいそうだった。 少しして、それがアンフィが呪われている証拠だとリルファーは思った。
その日の晩、彼女はアンフィが来ると言っていたのを忘れてベットの中で眠っていた。だから、彼が忍び足で近づいてきたときにも全く気が付かなかった。彼はリルファーのベットの枕元に張られた名前のカードを顔を近づけて確認すると、シーツを持ち上げて彼女のベットの中に潜り込んだ。アンフィは手探りでリルファーの腕を見つけるとそれを優しく触りながら言った。「イレアラ・カルス、起きてよ。僕だよアンフィだよ。君はまだ来たばっかりだから、夜にだって起きれるはずだ。もうそれが出来なくなったのなら、君は死の子供に捕まえられてしまったんだ。ねえ、そうじゃないよね。」
リルファーは心地よい深い眠りから、いじけた苛立たしい現実に無理矢理連れ帰られる途中でおかしな声を聞いた。その声を出したものは白い綿毛に包まれていて、細い足は鱗でささくれ立っていた。とても大きな鳥の雛に違いがなかった。その雛はピイピイ言うのも絶望のために忘れてしまったのか、かさかさに干からびた音を時々出した。リルファーがその雛をもっとよく見ようと近づいていくと、雛は驚いて頭を持ち上げて彼女のことを見た。そして小さなくちばしを延ばすと空気の中でこつんと音がした。それ以上雛は首を伸ばすことが出来なかった。リルファーと雛の間にはガラス窓があるようだった。そんな柔らかそうなくちばしではガラス窓を破る力などあるはずはないわ。私が今開けてあげる。彼女はそうつぶやいてから、窓の縁に手を伸ばすともっと良く雛の顔が見えた。彼のくちばしの間には赤い口の中が光っていた。それは普通と違っていて、縦に引き裂かれていて、口は左右にぱくぱく動いた。そしてまだ窓を開けられずにいると鳥はしびれを切らして痙攣したような叫び声を上げ始めた。リルファーは怖くなって後ずさりすると足の裏に何かが触れた。鳥の雛は彼女の足の下にいて彼女に踏みつぶされて死んでいた。
彼女は足の裏のひんやりした鳥の血の苦痛の中で目を覚ました。目を覚ましても濡れた感じは消えなかった。手を伸ばして触ると近くにすべすべしたもっと大きな物があるのを感じた。人の体らしかった。その固まりは言った。
「僕だよ。イレアラ・カルス。君はやっぱり目を覚ますことが出来たんだね。僕の思ったとおりだ。まだ分からないのかい。アンフィ・ブラスツゥラだよ。今日の朝、夜になったら、君の所に来るって言ったじゃないか。」彼はリルファーの手をそっと握った。手は凍えそうになっているぐらい冷たかった。彼女は無関心に呟いた。
「あなたの手を触っていると、前に居た所の湖に張った氷を触っていたときのことを思い出す。その氷の縁は尖っていて、ナイフみたいに体を鋭くして私の手を時々傷つけたけど、その赤さはとても綺麗だったからその暴力を私は許してあげた。」
リルファーは急に黙ってしまったその手の持ち主の目が光る方に話しかけた。
「あなたは一体何なの? アンフィ・ブラスツゥラ。あなたは寂しくてそれを紛らわす場所を見つけたくて、無責任にどこへだって潜り込もうとしているだけじゃない。そんなあなたを受け入れてくれるものなんて何もないわ。あなたは排泄物みたいにまた外の世界に押し出されるだけ。その偽物の宿主に自分の体の栄養を奪われて、本当は利用されてるだけじゃないの。」
いつまで経っても彼は何も言い出さなかった。彼女はいらいらして残された夢の世界に戻りたかったので、彼をベットから蹴り落としてやろうかと思い、体に力を入れた。その緊張に彼は気付いたのだろうか。やっと口を開いた。真っ暗なのに彼の口の中の血に濡れたような赤さが見える気がした。彼の口は鳥のように閉じたり開いたりを始めた。
「そうだね。君には僕のことが分かっているらしい。でも、僕が見つけようとしているものは君にだってきっと役に立つと思うよ。君は不思議に思ったことがないかい? 朝になったら、僕らの描いたシハレウの壁が元のように真っ白に戻っているのがどうしてだろうということを。壁がそれを食い尽くしているんだろうか。僕はシハレウを使うのをほとんど止めてしまったから気付いたんだけど、長くシハレウを使い続けて居る者ほど、僕が話しかけても何も答えてくれないんだ。彼らはいつも何かを話したいのに口をぱくぱく動かすだけなんだ。そうしている内にその子の体はどんどん縮まっていってしまってこの部屋からどこかに連れて行かれる。彼らはその時とても怯えていて辛そうだよ。彼らはその後帰胎出来るって事を多分忘れてしまっているのかもしれない。そう考えたら、壁が何を食っているのかが君にだって分かるだろ。壁は僕らが思っていることを食い尽くそうとしているんだよ。
だから、僕は壁がどんなふうに記憶を食べているのか確かめてみたいと思う。それで、君にも一緒に来て貰いたいんだ。なぜ自分がそんなことを頼まれているのか君は不思議に思うかもしれないけど、本当は僕は君がうらやましいんだ。君は毎日僕らがアマ・エムルスルダの言う通りにしているけど、イレアラは違うじゃないか、毎日恐ろしい声で叫び声を上げてる。どうして、アマは君のことを許しているのか分からないけど。」
そこで、彼はささやくのを止めた。きっと彼女が返事をするのを待っているのだろう。
「どうして私があなたの興味があることに応じなければいけないのかさっぱり分からないけど、私も行くわ。壁が本当に記憶を食っているのかどうか私も見てみたいわ。」
「そうか。ありがとう。それなら明日の夜行こう。今日はもう朝になってしまう。少しは眠らないと。」そう言うと彼はリルファーを握っていた手を離してベットから身を滑らして出て行った。彼女は彼が居なくなったことが何となく寂しかったので、彼の居たほうのベットの側に寝返りを打った。彼の甘く剥がれ落ちていく皮膚の香りがしていた。