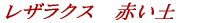
十三章 一節 桃色の鎖
「囓ったってだめよ、桃色の鎖は。
それは本当は桃よりも柔らかいんだけど、囓る前に私たちの歯が溶けてしまうの。それを咬み千切ったりしたくないってね。私たちは桃を殺したくないのよ。」
第一のレザラクスの逸話より
リルファーはしばらくの間自分の周りで漂う不思議な声を聞いて過ごした。それで自分がもう苦しみの野に向けて旅立っているのか、それとももう着いたのかその声に聞こうと思ってぼんやりしているとその声は消えた。リルファーはほっとしてまた目を閉じた、何か柔らかい物に巻かれて自分の体がどこかに運ばれていくのを感じた。それは私にとって気持ちの良いところなのかしら。あの虹の息の部屋でなければどこでもいいや。
そう声がした方に尋ねると、その声は「そうだ、君の行くのはそこではない」と答えたような気がした。それで彼女は私は苦しみの野に行くの? と聞いたが、今度は何も答えてはくれなかった。リルファーはとても不安に感じて小さく悲鳴を上げたが、「もう何もかも大丈夫になる。安心しろ。」
そう言われて長い眠りに落ちた。
それからどれぐらいの時間が経ったのか分からなくなってしまったが、リルファーはまたうっすらと目蓋を開けた。彼女が今、寝ているところはとても奇妙な場所だった。床は冷たくてひんやりしていて体の体温が徐々に奪われていくのを感じた。彼女は寝転がったまま頭を捻って辺りを見ると、自分が寝ているところから遠ざかるにつれて床の石が盛り上がっているようだった。つまりすり鉢型の床の中に寝ているのだ。その真っ白な床の石は登り始めた太陽の光に暖め始められたのかまぶしく輝き始めた。リルファーは毛布も何もなしに床にいたから凍えきってしまっていたのだが、これでやっと楽になると思った。
彼女はなぜか寝転がったまま体を動かしたくないように感じていたのだが、そのとても大きな部屋の窓を見ようと少しだけ起きあがろうとした。だが、その時背中に鋭い痛みを感じてそれを諦めざるを得なかった。やはりあの木から落ちたとき背中の骨のどこかを強く打ったのに違いがなかった。彼女は妙に視点が定まらない目で窓の方をそっと見た。
その部屋の壁の一面は全て窓ガラスで出来ているらしく、巨大な細長いガラスの白い金属の縁が列をなしているのが見えた。外の木にはおかしなぐらいの鮮やかな黄緑色の葉の固まりが風に左右に動かされてなびいていた。その様子は彼女を少しだけほっとさせた。だが、何かがおかしかった。痛む背中を気遣いながらまだぼんやりとしか見えない目を何度もしばたかせて、外をもう一度見た。目の玉の奥に何度も鈍い痛みを感じながら分かったことはリルファーをうろたえさせた。窓の外の庭に生える木が全て逆さまに見えるように木の天辺の葉が綺麗に刈り取られているのだった。「一体誰がそんなふうにしたのかしら。」
そうやって少し笑ってから今度は天井を見た。天井にくっつけられた木の出っ張りはなじみのある形だったが、それがそこにあるのが余りに意外だったので彼女は気付かなかったのだ。その丸い木の板の上の物はガラスのコップに違いがなかった。しかも、その中には少しだけ水が入っているようにしか見えなかった。それで彼女は確かめてみようと思った。唾を出来るだけ口の中にためておいて、吐き出したのだ。唾は白く鋭い剣のような形を保ったまま、天井に向かって静かに走ると黒い染みを残した。そこまでしてリルファーはやっと自分を納得させることが出来た。「私は床に寝かされているのではなく、天井に張り付けられているんだ。だから、手首と足首に薄桃色の鎖が見える。それが天井に私をつなぎ止めている。ここは私のための牢獄なのかしら。」
リルファーはその半透明の鎖に耐え難い苦痛を感じたがまたこうとも思えた。その鎖がなかったら、自分は床にに叩きつけられていると。もうリルファーは地面に叩きつけられるのは御免だった。しかし、そういうことにたとえ気付いたとしても自分が重力に逆らったところに居るとはどうしても思えなかった。自分の体重の全てがその細い鎖にかかっているという痛みだってなかった。
「おかしいわ。どう考えたって私が地面に打ち付けられた時に起きた異常でこうなったなんて思えない。それにさっきは唾は天井に落ちていったけど髪の毛は別にどうにもならないし。」
確かに彼女の髪の毛は逆立ったりしていなかった。しかし、そうした考えも窓の外から差し込み続ける白い光の苦痛と動けないことの苛立ちとでぼやかされていった。ただ、彼女が今感じるのは息を少しするのも苦しいような不安感だけだった。だが、どうしても彼女は体を動かしたい気分になれなかった。そのガラスのような細い鎖は力を入れればすぐに割れてしまうのは明らかだった。でも、なぜかそうしたくなかったのだ。彼女はその薄桃色の鎖が割られたときの苦痛が自分自身が壊されたときの苦痛と同じであることに気付いていたからそうしたのかもしれなかった。
その幻のような鎖はよく見れば彼女の手首や足首の内側から生えているようだったが、リルファーは今はその鎖のことは確かめないでおこうと思った。
そして、苦痛による夢うつつの中で辺りを見回すとまた不思議な物を見た。彼女の周りにも他のレザラクス達が何人もそうやってすやすや寝息を立てているのだった。
「なんだ、私はいつの間にかレザラクスの塔に戻っていたのか。」
そう思って彼女も他のレザラクス達の寝息に安心してそれに仲間入りしようと思って目をつぶった。そうやって出来るだけ長くリルファーは目蓋を固く閉じ続けていた。でもやっぱり他のレザラクス達も普通ではなかった。みんな手首と足首に私と同じような鎖を光らせていたのではなかったのだろうか? それに私はみんなの姿にどうしてこんなに長い間気付かなかったのだろうか? リルファーは目を開けてそれを確かめようとしたが「もし他のレザラクス達が幻だったとしたら、私が見ることでみんなが消えてしまう。もしそうだったとしたらみんながかわいそうだわ。私が見ることでみんなを殺してしまうことになる。」
だから、リルファーはしばらくの間耳をそばだて続けた。彼女たちの存在がたとえなかったとしても耳の中に彼女たちの寝息が残りさえすれば彼女たちが本当にそこにいたことを証明できる気がしたのだ。そうすれば、私は一人ぼっちじゃなくて済む。そして、彼女たちの静かな寝息を自分の鼓膜の中に出来るだけ沢山閉じこめていった。それから、もう十分だと思えたとき彼女は目をそっと開けた。良かった。彼女たちはちゃんと居てくれた。
リルファーは自分の一番近くに寝ているレザラクスの一人に声を掛けて起こしてみることにした。前と同じように真夜中に起きてふざけあうことが出来ると思ったのだ。
彼女は声を出そうとしてこんなにも口を開けて音を出すのが難しいということに驚いていた。なぜかかすれ声しかでなかったのだ。それでも隣のレザラクスに話しかけてみることにした。
「ねえ、あなた聞こえる? これから起き出して台所に行って、給仕係のプラックスが隠しているクッキーを盗みに行かない? あいつはそれをそこにおいてはいけないことになってるから告げ口だって絶対出来ないわ。ねえ、聞いているの?」
リルファーは自分の口から出てきた言葉の無意味さに自分で驚いていたが、言ってしまったからには仕方がなかった。彼女の隣に寝ている背の高いレザラクスは最初彼女に背中を向けて寝息を立てていたが、リルファーがささやきかけると目を覚ましかかったのかこちらに寝返りを打った。彼女はまたささやき続けた。「ねえ起きて、クッキーだけじゃなくて猫にやる魚の干物も盗んだって良いのよ。あいつらあんな臭い物をとても喜ぶのよ。それに・・・。」
リルファーはレザラクスが目を少しの間覚ましてこちらを見つめたときに余りに驚いて口を噤まざるを得なかった。彼女の顔に降り注ぐ強い白い光の中で最初はよく見えなかったのだが、もう一度彼女が瞬きした瞬間それがはっきり見えた。彼女の目玉の有るべき所には真っ黒い何かがはめ込まれていたのだ。それはガラス玉のようだった。
リルファーは嫌悪感を強く感じてそれから目を離したが、そのレザラクスは少しだけ口を歪めた。それは痛みに苦しんでいるのかそれともリルファーに向かって笑いかけているのか全く分からなかったが、しばらくするとリルファーが話しかける前の姿勢に戻ってすやすや寝息を立て始めた。彼女はほとんど耳が聞こえてさえいなかったようだ。しかし、その表情は満足げにさえ見えた。
「一体どういうことなんだろうか?」リルファーはしばらくの間、恐怖と不快さに打ちひしがれてしまった。そして、今度は話しかけずに周りのレザラクスの様子をじっくり観察した。
右隣のレザラクスは目が真っ黒だったが、左隣のレザラクスは右手と左足が無いようだった。リルファーの頭の真上の方向のレザラクスはまだ彼女の首筋は酷く痛んだので余りはっきり確認することは出来なかったのだが、そのレザラクスは一見どこも悪くはないようだが白い寝間着を掻きむしる瞬間に彼女は秘密を盗み見ることが出来た。その太り気味の彼女の腹には、はっきりしたかぎ裂きを縫い合わせた痕があった。
しだいに分かって来た結果に彼女は恐怖しもしたが、最後には鈍い怒りの感情だけが残った。彼女は冷静にこう判断した。
「なぜ、あの子達がここに居なければいけないのか。彼女たちは明らかに重大な傷害を体に得ているわ。放っておけば必ず死んでしまうぐらいの。どんなにレザラクスの回復力が優れているからといっても、それにも限度があるもの。彼女たちは限界を超えてしまった。
だから、彼女たちはここにいるのよ。あの足のないレザラクスだって神官医は血を十分に止めてやることが出来なかったのに違いがないわ。だから彼女はまだ血を滴らせ続けている、でも彼女はまだ死んでいないわ。外の世界では必ず死んでしまうはずなのに。
レザラクス達には死ぬことが許されていないし、また実際に死んだ者がいない理由だってこれで分かった。この部屋では私たちはどんなふうになったって絶対死ねないんだわ。多分、時間の流れ方がすごくゆっくりなんだ。だから、いつまで経っても日が沈まないし外では小鳥が鳴いてる。でも、あれは単なる幻かもしれないけど。」
そこまで考えると彼女は一つの疑問に突き当たらざるを得なかった。自分がなぜここに入れられたのかという疑問に。木から落ちたときの傷は酷かったけれど、じっと寝ていたら、次第に痛みは和らいで来ていた。もう少ししたら前と同じように歩けるような気がした。それならばどうして? 答えは自分の中に残るトワンス・ロフの言葉が出してくれた。
君がもし君が望んで死にたいのならば君は行くべき所に行くだろう。
そんなふうに彼が言ったことがなかっただろうか。
「いいや、あったわ。それで彼は私の意志を確かめた。それでここに私を入れたのよ。さぞかし彼は満足したはずよ。厄介者が居なくなったのだし。」
彼女は絶望に打ちひしがれていたが、部屋に満ちる狂気のような白い光が雲を突き抜けて彼女の顔に差し始めた。すると、奇妙なことに苦しさや疑念がその光によって分解されていくのがはっきり感じられた。リルファーは必死でそれに抵抗したが、結果は無駄だった。彼女は気を失って強制的に眠らされたのだった。
一体何度そんなふうに眠らせられて、また床のひんやりした寒気にたたき起こされた後だろうか。彼女は自分に話しかけてくる声を聞いた。それは初めて聞いたはずなのに何度も笑いあったことのある誰かの声にそっくりだった。リルファーはぼんやりしながらそれは誰だったか思い出そうとしたが結局無理だと諦めてしまった。
しばらくして、またその声が「リルファー。」と囁いた。まるで気持ちの良い道ばたで聞こえるような声だった。リルファーは今度ははっきりと目を覚ました。そして、期待のこもった声で「コーラルなの?」と聞いた。あの声は一体どこからしたのだろうか。周りを見渡しても、それからコップがずっと置きっ放しになっている天井のテーブルの方を首を捻ってみても彼女に呼びかけた人がいる気配はなかった。彼女は夢だったんだろうかと思って、もう一度その夢の続きを見てあの人が居た道の後をずっと付いて行って、草原まで行ってみよう。と口の中でもごもご呟くとまた眠ろうとした。
しかし、また「リルファー私はここよ。」そう言って笑い声がしたのだった。
彼女は気持ちの良い夢からたたき起こされて苛立たしげにその方向を見た。すると驚いたことに彼女は自分の顔の丁度横に立って歩いている人の足を見たのだ。リルファーは怖くなって声にならないかすれた悲鳴を上げた。それを聞いてまたくすくす笑い声がした。リルファーは勇気を振り絞って固く閉じた目蓋を開けると、そこには一人の痩せた小柄なレザラクスが彼女の顔を覗き込んでいるのが見えた。そのレザラクスの髪の毛は赤くてすごく長くてリルファーの顔に垂れかかってきた。でも少しもリルファーはそれが嫌ではなくて、そのやさしい匂いにほっとしていた。
「あなたは誰?」
そうやっとリルファーが呟くとそのレザラクスは少し笑ってから答えてくれた。
「わたしはタルヒナー・ウルクバクよ。初めてこの世に生まれ出たレザラクスと呼ばれていたけどね。だから、私のことをタルヒナーと呼んでくれる人はいなかった。私はただ単にレザラクスと呼ばれたわ。名前だってあなたに初めて教えたのよ。あの汚らしい本にだって書かなかったし。」
そこで彼女は口を噤んだ。それからしばらく考え込んでから言った。
「あなたは一体いつまでそうやって這いつくばっているつもりなの? 奴らの言いなりになって。」そう激しく怒鳴りつけてから、笑いながらリルファーの手を握った。タルヒナーの手はとても暖かかった。そう感じている内に彼女は立ち上がっていた。他のレザラクスの死骸達の群の中に。
「有り難う、タルヒナー。私はリルファーよ。なぜかあなたはもう知っているみたいだったけれど。」
タルヒナーはリルファーよりもずっと小柄で色も浅黒かった。ただ髪の毛だけが赤く明るく光っていた。彼女は時折人を威圧するような鋭い目つきをした。だがそのあとすぐに人なつこそうな表情をしたりするのにリルファーはこれから気付いていくのだった。
「タルヒナー、私は鎖に繋がれてもう立ち上がれないのかと思っていた。でもどうして立てたのだろう。」
タルヒナーは自分の足首からぶら下がるリルファーのよりもずっと太くて長い鎖を見下ろしながら答えた。
「この鎖はそうしたくないと思いこませるためだけのちゃちなしかけよ。でも無理に取り外そうとしたらだめ。そんなことしたら・・・。」
彼女は周りのレザラクスに優しい眼差しを投げかけていた。「逆により重い桃色の鎖に取り憑かれてしまうわ。この鎖は私たち自身で出来ているのだから。私たちの肉で出来た鎖なのよ、これは。」
タルヒナーは最後の言葉を息と共に微かに押し出したので、リルファーにはほとんど聞き取れなかった。「私たちは自分たち自身を憎まれるべき者と思い、それにふさわしい呪われた肉の鎖を自ら望んで作りだし、それを自分たちに与えたのよ。それを素晴らしいものだと思ってね。
そして、今だって私はそれがとても素晴らしいと思っているのよ。あなたには分かるでしょ。リルファー?」
リルファーは突然その様に聞かれても何のことだかまったく分からなかった。だが、自分を見つめるタルヒナーの静かな笑顔は彼女を嫌悪させるものではなかった。
リルファーは黙って頷いた。彼女は自分の体が少し震えているのに気が付いた。立ち上がる事を体が忘れてしまったのに違いがなかった。
「あなたはまた、眠りたくなったんじゃない? 実際私たちに与えられているものはこの美しい鎖と眠ることだけなのだから。あなたはそれをいくら欲しがったって良いのよ。あなたが気持ちよく横になれるように手伝ってあげる。」
そう言ってタルヒナーはリルファーの手をそっと握ると軽く揺らした。すると、彼女の体の力がすっと抜けて床に静かに倒れ込んでしまった。また酷く背中の骨が痛んだ。さっき立っていたときは平気だったのに。その鈍くて鋭い痛みが何秒かおきになって、なんとか我慢できるぐらいになったとき、目蓋を開けるとそこにはタルヒナーの姿は無かった。きっと自分が眠るべき場所に帰っていったのだろう。彼女は自分の手首に生えた桃色の肉の鎖が透明に静かに光るのを見て安心すると、貪るように眠りに落ちていった。目が覚めるということは一体どういうことだったのだろうかと思いながら。