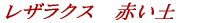
十三章 二節
次にまたリルファーが自分の意識がはっきりし始めたのを感じたとき、彼女はタルヒナーが起こしてくれたのと同じようにして立ち上がってみようと思った。自分一人の力だけで、それが十分出来るような気がしたのだ。頭を傾けてみるとやはり肉の鎖が手首に有るのが見えた。それは半透明で中に何かの液体が静かに脈打っているようだった。一見、殻で覆われているようだがその殻は明らかにしなやかで、時々虹色に鈍く輝いていた。
リルファーはその様子をうっとり眺めながら、自分がそんな綺麗なものに縛られ続けるだけなのなら、何も辛いように思う必要なんて無いんだ。と、自分に呟いて、その都度その宣言の暗い響きに驚いて怖がっていた。
タルヒナーはこの前なぜ私を立ち上がらせたのだろうか? それに私はどうしてその時肉の鎖の端が切れていたのかどうか確かめようとしなかったのだろうか、多分その時の間だけ食いちぎられたように床と離れていたのに違いがないけど。それで、食いちぎられた鎖の端から私の綺麗な体液がどんどん逃げていってしまったんだ。だから、今私はこんなに惨めに力も何もかも無くして床に縛り付けられているんだわ。
それとも、タルヒナーは本当に私の所に来たのだろうか、あれは何かの亡霊なのかもしれない。リルファーは自分のことを力無くクスッと笑った。亡霊は今の私自身。肉の鎖からどんどん力を奪い取られていくの。こんな無意味な亡霊からどんな力を抜こうっていうのかしら、私にはもう何にも残っていないのに。最も始めから自分から取り上げるものなんて持ってはいなかったと結論付けるのは彼女は怖かったのかもしれない。その事が分かりさえすれば、自分がなぜそこに繋がれなければならなかったのかもっと良く理解できたのかもしれなかったが、今は彼女は何も考えたくなかった。
だから、都合良くこう思うことにした。タルヒナーなんて始めから存在すらしなかったのだ、もし居たとしたってそれは私を騙すためだけの幻だっただけなんだ。それに本当に私がすでに騙されていたとしたら私は自分自身である肉の鎖を食いちぎって死んでしまっていたのに違いがない。
リルファーは安心してため息をついた。「良かった。私は今までだって肉の鎖を食いちぎったりしてなかったのだし、これからも絶対そんなことはするはずないわ。だって、そうだとしたら、こんなふうに思えるはず無いもの。」そう思うと、彼女は自分の未来が明るいものであるように感じた。こうやってすべらかな床と血管に守られて私は生きていけるわ。そう、どんな心配だっていらない。今までみたいには。
だが、そんな安らかさは誰かに乱暴に叩きのめされた。それは小さな空気の震えだったのだが、彼女には最初それが何なのかさっぱり分からなかった。ただ、その空気の震えの不愉快さに歯茎を食いしばってずっと耐えた。リルファーは自分がなんて忍耐強いのだろうかと感心した。レザラクスの塔に今も縛り付けられている教師達に今の自分の勇敢さを見せつけて笑いものにしてやりたいとさえ思った。しばらくしてさっきから聞こえていた恐ろしい音はどこかに逃げ出してしまい、彼女は安心してお腹の力を抜くと自分の尻の下の床がじっとりと濡れ始めたのを微かに感じた。長い間考え込んでからやっとそれが「おしっこ」と呼ばれていたものであることを思い出した。私は外の世界に居たときなぜそんなものをしょっちゅう垂れ流していたのだろうか? そうだ、多分地面と関わり合いを持つためだったんだ。だから、今私は床とこんなに親しげに密着している。それに気が付くと、リルファーはもう一度「おしっこ」をしてみようと思った。もっと床にくっつきたかったのだ。だが、一体自分がどうやってそれをしたのかもう思い出すことが出来なかった。
リルファーはその事が残念だったのだろう、声も出さずに長い間涙を流して体を震わせていた。自分の体の周りから尿が天井に向かって滴り落ちるのにも彼女は無関心だった。
そして、その震えがやっと収まったとき、またあの忌まわしい音が地面に響き始めた。
それは、静かに、静かに、それからふわふわ飛んで、地面に素早く身をふせる。それから、また静かに、を繰り返す音の固まりだった。そうだ、これは歌だ。リルファーは耳にもう少しだけ余分な神経を集中させた。すると、だんだんそれが言葉であることが分かってきた。それはこんなふうな意味だった。
「手を離して赤い綿毛、まだ水たまりに落ちない、落ちない、
水たまりに閉じこめられた空、は手を伸ばして、赤い綿毛。
ね、だから落ちないって言ったでしょ。空気の中に閉じこめられた赤い綿毛。綿毛には空気は固すぎるの。だから、綿毛は水の所には絶対行けない。空気の中に張り付けにされているの。だから、空気は自分の体を強ばらせて、他の何も寄せ付けないようにしているの。だから、赤い綿毛は水の中に落ちない、落ちない。」
リルファーは目を固くつぶってその長く続く苦しみに耐えようと無駄な努力を続けたが急にまたふっとその歌は止んでしまった。リルファーはまたおしっこができるかもしれない、ということを思い出して期待に胸を膨らませて目を開けた。
しかし、そこには空中に浮かぶ黒くて光る二つの目が彼女を真上から見下ろしていた。タルヒナー、タルヒナーがそこに居たのだ。リルファーは怖くて顔を必死に歪めた。そうするとちょうど笑っているような声が出た。「どうして、タルヒナーは天井にぶら下がってこっちを見て居るんだろう? 足が天井に縛り付けられてしまったのかしら・・。」
その時やっと自分がかつてした無意味な実験を思い出した。彼女が口から垂らした唾は真っ直ぐ、天井に落ちていった。ここには地面が二つある。床と天井と、その両方が地面なんだ。そして、今タルヒナーは天井側の地面に居た。タルヒナーはまるで呪われたものを見る目つきで冷静にリルファーのことを見上げていた。
そして、静かに口を開いた。「私はあなたのことを見て、今では唾を吐きかけてやりたいとさえ思うけど、それは無理ね。本当の地面はこちら側に有るのだもの。あなたはまだどうしてそんな鎖に繋がれているの? 私の言ったことをあなたは理解できなかったのかしら。とんだ大馬鹿だわ。」
リルファーは声を震わせながら小さな声で反論を始めた。
「だって、あなたは肉の鎖は自分自身だって言ったじゃない。もし私がそれを千切ってしまったら、私はすぐに死んでしまうわ。」タルヒナーは大声で彼女がもごもご言うのを遮った。
「自分自身だから、自分で殺すことだって出来るのよ。あなたに今みたいに思わせるのが奴らの策略だっていうことにあなたはまだ気が付いていないの?」
タルヒナーは誇らしげに自分の後ろにだらりと垂れた肉の鎖の端を掴みあげると、それを無造作に食いちぎって、その新しく出来た断片を無造作に吐き捨てた。彼女の口は自分の血で汚れていて、美しく輝いていた。さあ、あなたにだって出来るはずよ。そう彼女は示そうとしていたのだ。
リルファーはその恐ろしい様子から目を背けようと努力したがだめだった。だが、かろうじて、何も返事をしないことに成功して、首を固く縮め、髪の毛の中に顔を隠そうとした。
「分かったわ。リルファー、私はそちら側に行ってあげるわ。あなたにほんの少しさえ勇気が有ってくれさえすればそんなことはせずに済んだのに。あなたのせいで私はまたそちら側に行かなくてはならないのよ。あと百年は行かずに済まそうとしていたのに。そっちに行ったらまた多分、歌をしばらく忘れてしまう。そうなったら、あなたを殴りつけてその悲鳴で楽しませて貰うしかないわね。けど、本当はそれでは何の穴埋めにもならない。私が歌わなければならないという役割はどうしようも無くなってしまうもの。」
彼女は非常に苛立たしそうに言ったが、リルファーはまたしばらく歌を聴かなくて済むと思うとほっとした。殴られる方がずっとましな気がした。
そう思っているとすぐ近くに彼女の香りがした。タルヒナーはこちら側に来たのだ。一体何をするつもりなんだろうか? リルファーはほとんど無関心に近い態度で聞いた。
「あなたが、私に何をさせようとしたって無駄よ。あなたが私にあなたが見つけたちんけな偽物の自由とやらを見せびらかしたって何の役に立ちはしないわ。あなたは私のことは放って置いて向こう側で気違いの歌でもなんでも歌えばいいわ。それぐらいは許してあげても良いって言ってるのよ。あなたの歌が私にとってどんなに苦痛であったとしても私はそれに耐えるわ。私はあなたの歌を聴いているとおしっこがしたくなるから丁度良いのよ。」
それを聞いてタルヒナーは感心したように彼女のことを見下ろしていた。
「そう。有り難う、それならいいのよ。でも、私はあなたのことが気に入ってしまったの。だから、あなたにどうしても見せてあげたいものがあるのよ。この部屋に入れられている他のどんなレザラクスにも見せなかったものを。」
リルファーはそれを聞いてごくりと唾を飲み込んだ音が彼女に聞かれたのではないかと心配した。タルヒナーは続けた。「でも、ここではだめよ。ここには奴隷達が多すぎるもの。向こう側に行きましょう。大丈夫よ、私が手伝ってあげるから。不安に思う必要はないわ。あなたが一度立ち上がったときだって鎖はちゃんと千切れたりしなかった。少しぐらいなら延びるのよ。それに私が手伝えば鎖が切れないようにもっと長く延ばすことだって出来る。だから、ちょっとだけ我慢してね。」
タルヒナーはひざまずくと優しくリルファーの足首に生えた肉の鎖をなで始めた。リルファーはとてもくすぐったくって、笑いそうになった。そのちょっとだけ嫌な感じはレザラクスの塔で友達に寝ているときにくすぐられた感じととても似ていた。
しばらくした後、タルヒナーが彼女の手を握ると気が付いたときには、向こう側にいた。リルファーは、自分の肉の鎖がどうなったのか気になってそれをずっとたどると、天井までずっと延びていくのが見えた。あれが、私がさっきまで居たところか。それはとても狭い空間で、どんなに自分が縮こまっていたのかやっと気が付いた。その周りには汚れたぼろ切れの山が延々と張り付けられていた。一つ一つのぼろ切れには黒い枯れ草のような束がくくりつけられていて、その真ん中にめり込んでいるもの。それは顔の皮膚に違いがなかった。
そうだ、それがレザラクス達だったのだ。余りに恐ろしい分量の生きた死体達、その数は百人以上もしかしたら千人ぐらいはいるかもしれない。それが全員、天井に張り付けられているのだ。リルファーはそれを眺めていると久しぶりに嫌悪から吐き気を感じた。ぐらぐら絶え間なくゆらめく体を支えるために彼女は手近にあったテーブルに手をついた。彼女は少しして気分を落ち着ようと目を開くと、そこには奇妙な光の固まりがあった。その中で光は絶えずぐるぐるうごめいていて、恐ろしく反射し続けた。その中で世界がまるでねじくれて無くなってしまいそうだった。
彼女はゆっくり手を伸ばしてそれに触れるとそれはひんやりして冷たくて、少しだけ綺麗に震えた。それは彼女が天井に居たときにそれに触れることをどんなにか夢見ていた、水の入ったガラスのコップなのだった。彼女は外の世界にいたときのようにそれを手にとって持ち上げて飲み干したかったが、それが今ではどんなに掛け替えのないものか身にしみて分かっていたので、すぐにそっと手を離した。
そのコップの中の水はこの部屋の中で恐ろしく長い間、全く一ミリも蒸発することも無いことで、彼女たちに与えられている永遠の時間をはっきりと証明している唯一のものだった。
リルファーはそのコップの中の水に守られているとさえ感じ、それに触れたことにほっとため息をついた。そのコップの水を注意深く見ると、それを静かに揺らすものがあるのを感じた。自分自身の息とは別のもの。リルファーが振り返るとそこにはタルヒナーが居た。リルファーは自分が彼女の手をこちら側に来たときからずっと握りしめていたことにやっと気が付いて、気まずい思いで離そうとした。だが、タルヒナーは言った。
「いいのよ、このままで。離したって良いけど、そうしたらあなたはそのとたんまた天井に戻されてしまうわ。もうしばらくだけ我慢してね。」彼女は優しくリルファーの手を引いた。
「あの窓辺の所の床に座りましょう。日光が気持ち良いもの。」
ここの床、つまりさっきまでの天井には手のひらぐらいの黒いタイルが張り巡らされていて、タイル同士の間の溝は白く、何本も地面を引き裂いていた。それをリルファーは足の裏でたどりながら、素直に彼女に導かれて行った。
「さあ、ここに座りましょう。」そう言うようにタルヒナーは何も言わずにリルファーの手を引っ張った。彼女たちの目の前には恐ろしく巨大な窓があった。恐らく壁の全部が窓になっているのに違いがなかったが、今の彼女にはそれを確かめる余裕など無かった。彼女は窓の向こう側に茂る草の葉や森の影を見ることもなく、ただ白く鋭く光る窓の枠に指を触れていた。あの向こうに漂っている白い光は何度も私の中を通り過ぎて、私が何か思っていることを持ち去っていったのに、今は一体どこに行ってしまったのだろうか。でも、あの何の特徴もない木の葉や風の中にそれがないことだけは確かだ。
リルファーがうつろに考え続けていると、タルヒナーが自分の方に握っていない方の手をすっと差し出してきた。最初その手は軽く握られていたから、その中に自分に向けてのプレゼントか何かが隠されているのかと、リルファーは反射的に思った。
しかし、それはそんな楽しいものではなかった。握りつぶされた飴がその中に隠れていたのではなかった。リルファーは彼女の手のひらの中に想像していた赤い輝きを全く別のところで見つけた。タルヒナーはいつの間にか上半身の寝間着を脱ぎ捨てていた。なぜそんなことをするのだろう。タルヒナーは私とセックスしたいのだろうか。リルファーはレザラクスの塔でしていた、下らないその遊びのことを虚ろに思った。だが、その時彼女はタルヒナーの体をはっきり見た。彼女の胸の真ん中から半分側、丁度リルファーの方に差し出した手の方の上半身全部が赤く光っていた。その表面には小さな窪みがたくさんあって窪みの中は暗くて黒かった。タルヒナーは自分のその様子を全く見ようともせずに口を開いた。
「あなたに私がどうなっているか分からないでしょう?
リルファー、あなたには分かるはず無いわ、私が初めてプラックスに会ったときのことを。千年以上も前の事よ。私は苦しみの野の向こう側に住んでいた。丁度、人間達の住む森との間に町があったの。そこから私はたった一人でプラックス達の居るここに出掛けて行った。たまに人間達は私たちの住む町を素通りして、プラックスの町に旅していたからいったい何があるのか知りたかったのよ。でも、そこにはしょぼくれた坊主たちしかいなくて建っている物は汚い塔しかなかった。私はがっかりしてレザラクスの町に帰ろうとした。そしたら、私は苦しみの野の境目で捕らえられたのよ。坊主達の命令でね。
坊主達は私のことがどうしても必要だからなんとしても自分たちの所にいてくれと懇願した。生き延びるためにね。自分たちの国が凍えそうに寒くてそれで子供がいっさい産まれなくなってしまったんだ。私たちは君の中で暖まりたいと奴らは言った。私はそいつらを殴りつけて唾を吐きかけてやりたかったけど、そんなに私の肉が必要なのなら、お前らにくれてやる。そう言って、自分で皮を剥いで奴らの前に投げつけてやったの。だから、見て、私の体の半分を、あなたはこれを見て醜いと思うかしら。」
そう言って彼女は腕を開いて見せた、ほほえんでいるようだった。
リルファーは恐ろしくてたまらなかったが、静かに首を振った。
タルヒナーは満足して十分な沈黙を作り出すとまた喋った。
「奴らは一体どこまで気が狂ってるのかしら、奴らは私のせっかくくれてやった、皮を服にして暖まろうとせずに、私を惨めなどうしようもない内容の聖書の表紙にしたのよ。でも、かれらにとって掛け替えのない中心の装飾物にされたときから、私は彼らをコントロールする方法を身につけた。聖書の内容を書き換えてやったのよ。
彼らは本当にそれを喜んだわ。無尽蔵な知性を手に入れた。とか言ってね。私には知性のかけらも存在しないって事が分かってるのかしら。
これからが奴らの本当の面白いところ、出来るだけお楽しみを長持ちさせようとしたのね。彼らは本当に研究熱心なのよ。彼らがこんな腐った泥沼に住み続けている理由はたった一つだけ、そこではこの部屋があって、レザラクスの塔があって、白い草の部屋があるからというだけのこと。つまり、この辺りは時間が歪んでいるのよ。だから、彼らはそれを信仰しているという訳よ。そのおこぼれに預かろうと禿鷹みたいに人間達も飛んできて何か一緒に悪巧みしていたけど、最近はどうしたんでしょうね。多分自分の生命力の無い惨めさにやっと気が付いて絶滅してしまったのに違いがないけど。
その後、皮を剥いでしまった後、私の体はもう死んでしまっただろうと思っていたけど、私はそれをこの部屋の中で見つけたの。彼らは大事にとって置いたのよ。この部屋に入れておきさえすれば、何も腐らないということに気が付いていたのね。それから奴らは私の体を隅から隅まで調べて実験し尽くして、私の体の中の極端な生命力を利用する方法を発明したってわけ。その馬鹿げたことについては何も言うことはないわ。ただ、純粋なレザラクスは彼らによって刈り尽くされたことは確かよ。」
タルヒナーはそこまで言って愉快そうにひとしきり声を立てて笑った。リルファーは黙って、彼女の皮の自分で剥いだという痕をじっと見た、それは赤くてところどころ半透明に向こう側が透けて見えた。もしかするとタルヒナーが生きているところは、その透明にかき消された部分に有るんじゃないかとリルファーは思った。そこを触りさえすれば、どこか別の所に行けるんじゃないかしら。「触ってもいい?」彼女は聞いた。
タルヒナーは突然そう言われて、自分の気持ちの良い高揚が叩きつぶされたらしく、しばらく体を痙攣させて黙っていたが、やがていいわよ。とぽつりと呟いた。
リルファーは恐る恐るそこに手を伸ばし、触れた。その時彼女はとても熱いと感じたが、タルヒナーの傷跡の全部が瞬間的に銀色に瞬いたのを見て、とても驚いた。彼女は手を引っ込めようと少しもがいたが、すぐに手を離したいという気持ちもどこかに吸い取られてしまった。彼女は不思議な夢を見ていた。とても大きな白い部屋を天井の方から床を見下ろしているようだった。部屋の中には大きな汚い布の袋が一つだけ投げ捨てられていた。袋は時々体が痒いのか、身を引きつらせた。だが、そのすえた匂いでそれがプラックスであることが分かった。それは長い舌を出して床に生えた苔を舐め取ろうとしていた。多分手足が縛られていて、何日も食べ物を与えられていないのに違いがなかった。彼が味わうものは自分の吐いた僅かな胃酸だけだったのだろう、彼はうめき声を出そうとした。
だが、その声は彼女には聞こえなかった。もう一度彼は頭をもたげて、口を避けるほど開けて、咽を震わせた。その無音の声の醜さにリルファーは虫ずが走って、そんな奴は今すぐに死んでしまえばいい。と強く願った。リルファーは歯を食いしばると止めようもなく唇から唾液があふれた。そして、それはごみの袋のようなプラックスの顔の上にぴちゃぴちゃ落ちた。すると、彼は長い舌を延ばしてリルファーの唾液を美味しそうに舐め取って、懇願するような表情で彼女のことを見た。そのまだ若いプラックスは静かに口を開きひとしきり口をぱくぱく動かしてから、舌を延ばした。その舌には真っ黒い染みがいくつも規則的に並んでいるのが、リルファーにもはっきり見えた。その嫌悪感に気付いたとき、彼女の体を鋭く激しい痛みが襲って、彼女は夢から覚めた。
その痛みは苦くて恐ろしいものだったが、そのおかげでプラックスから逃れることができたので彼女は感謝した。夢から覚める時、彼女は優しい歌声を聞いた気がした。
リルファーはまだ赤く光る肌をしたタルヒナーの前に座り込んでいた。タルヒナーは目を開いてはいたが何も見えていないようだった。
「あの男は何? 恐ろしくて蛆虫みたいだった。」タルヒナーの目はやっとリルファーの方にゆっくり動いた。
「あれがこの国で一番の聖職、スクンエラよ。私は毎日あれに餌をやって蝿にならないように見張っているの。」
リルファーがまたなにかたずねようと口を開きかけたとき、タルヒナーは素早く彼女と繋いでいた手を振り払った。リルファーは気が遠くなっていくのを感じた。
「なぜなの?」そう問いかける暇もなく、また白く輝く光が彼女の思考を無慈悲に押しつぶした。長い間握りしめていた手が強ばってずきずきするのを大切に思いながら、その感じを忘れないでおこうと決心した。もうタルヒナーに会えないことには半ば気が付いていた。
それから、しばらくして彼女の所を彼女とタルヒナー以外の動くもの、よく分からない亡霊じみたものが訪れ始めた。