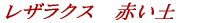
十章 染められた階段に落ちた弾丸
丁度その二月前、帰胎に向けた旅をいつ始めるべきか考えていたとき、まずは自分のスクンエラとしての仕事を出来るだけ完成させておくのが良いだろうと結論付けた、アンフィは白い草の部屋に向かった。何重にもその部屋を取り巻いている細長い回廊は蝸牛の殻の中をたどるように彼を中心に導いていった。回廊には壁はなく、数十本の柱のみしか立っていなかったので、気持ちの良い暖かい風が何度も吹き抜けていった。
廊下のすべすべした綺麗な白い石はすり減っていて足の裏に静かな快感を与え続けた。別にそんなにぐるぐると巡る、長い廊下に沿って歩かなくても、外側の周の廊下と内側の周の廊下は容易に飛び越せるぐらいの隙間しかなかったのだから、近道して行ってもかまわないはずだった。けれども、スクンエラはその廊下に沿ってゆっくり旋回して行かねばならないという決まりはとうになくなっていたのだが、いつもアンフィは近道はしなかった。その長い廊下を歩く内に自分の中でスクンエラとしての感覚が研ぎ澄まされていくのを感じていたからだ。近頃自分の後を継ぐことになった、イエルハブーンにもそのことを守るように言っていた。
五分ほど歩いてやっと中心にたどり着くと、そこには小さなみすぼらしい小屋が静かに座っていた。外の壁は廊下と同じ材質の白い貝殻の石で出来ているのだが、縦の方向に走る細かな襞が無数に刻み込まれていて、一見すると草を編まれたように見えたので白い草の部屋とそこは呼ばれているのだった。
その小さな小屋のどこに扉が隠されているのか普通の者には知ることは出来なかったが、彼がその襞の一つに触れると彼が体を横にしてやっと通れるぐらいの暗い隙間が開いた。また、彼がその扉に触れる場所はいつも違っていた。それでも必ず扉は開いた。つまり、彼が触れたところは全て扉になったのだ。そして、彼自身がその生きた鍵になっていた。
彼が白い草の部屋に体を滑り込ませると扉は音もなく自然に閉まった。建物の中は採光窓が無かったし、照明も無かったのだから、真っ暗になるはずだったが、いつもその中は緩やかな乳色の光に満たされていた。がらんとした部屋の中央には周り階段が一つだけあってそれが地下に続く道となっていた。彼は手すりに掴まりながら大儀そうに足をかばいゆっくり降りていった。階段の中央には幅が三メートルぐらいの太い柱が通っていた。
階段を降りていくときいつも彼はこれから淫らなことをするんだという期待とまた自分がなぜそんなことまでして、神の期待に応えなければならないのかと思うと自分が首を絞め殺された白い兎のように感じた。だが、彼はその哀れな兎を自分自身の足で出来るだけ優しく運んでいった。
それから、九十段降りたところが階段の終わりだった。アンフィの指先は階段の石段の感触と部屋の床の石の違いを敏感に感じ取った。いつもながら、すごくチクチクした人が歩くことを考えられていないかのような床だった。石の毛の絨毯と彼は自分で呼んでいた。その白い毛並みを踏みしめながら、緩やかなアーチ型の門の戸の前に立った。戸は白く濁った半透明の鉱物で出来ていたから、開かなくても中はうっすら見ることが出来た。
アンフィはその扉を見るといつも自分がレザラクスだったときに見た池に張った氷の上に投げつけられたチョコレートの破片を思い出した。
しかし、今そのチョコレートの屑を透かしてみても、中に見える物はただの白い光のみだった。白い光、本当はその部屋の色をそう言い表しては間違いになってしまうだろう。アンフィは自分の前にいたスクンエラがそう言っていたから初めて気付いたのだが、その部屋の中では彼らは色を見ることが出来ないのだ。それとも、その部屋には始めから色など無かったから、そういえるのかもしれないが。
天井から下りた、狂気に満ちた銀色の細い棒と、それに突き刺さった黒い小さな本と、その部屋にはたったそれだけしかなかった。
しかしながら、アンフィはこれからそれらが自分にもたらす苦痛に耐えきるために、戸を通してここから睨み付けていた。たとえ白い光に埋もれてその姿が全く見えなくてもかまわなかった。
「もう少しであの本に会わなくても良くなるっていうのに、私はまだ怯えているのか。ただ部屋に本が少し変わった形でぶら下がってるだけじゃないか。でも、私はそんな物にひれ伏さなければならない。」
アンフィはこれからたっぷり味会わされる神からの侮辱のことを考えるといつまで経っても、一向に中に入りたいとは思えなくなっていた。自分がスクンエラになってからよく今までそんなことに耐えてきたものだと彼は一人で笑った。
そのとても小さな音が部屋の中に響いたので、彼はそれに驚いて背中の方を素早く振り返った。そうだ、そんな音でさえ彼はそこでは聞いたことがなかったのだろう。
しかし、彼はゆっくりと口を開きその舌先にある黒い斑紋で石の戸にそっと触れた。戸はそうされることを待ちかまえていたかのように内側に音もなくゆっくり開いた。
「そうだったのか、この部屋の光は色だけではなく、どんな音だって吸収してしまってきたんだ。だから、私が何度となくこの中ですすり泣いたり、恐怖で大声を上げていたりしたとしても、そんなことは始めからなかったかのようにされていたのか。」
彼は音もなく呟くと、初めてその部屋に強い憎しみを覚えた。しかし、彼はその後強要される行為のおぞましい快感に全てを忘れた。
それをしながら、彼は赤土の本の部屋の中で一瞬天井の方を振りあえいだ。彼は床に這いつくばり、口からは何か透明な液体をはみ出させていた。それはただの彼の唾液であるはずはない。彼は白い光の空に浮かんでいる、一本の銀色の棒が地面にいる自分を指し示して延びているのを見た。そして、その槍のような尖った先にはまた透明な液体が潤んでもう少しでしたたり落ちそうだった。彼はそれがいつ落ちるんだろうと嬉しそうにほほえみながら待ちかまえていた。
銀の棒には細かな螺旋状の刻み目が無数に伸びていて、たまに虹色に光ったりしながら見る者の目を上へと導いていった。銀の棒はものすごく長くて数十メートルのか、それとも本当は普通の部屋と同じぐらいの天井から延びているのか彼にはよく分からなかった。
それに、そんなことはちっとも気にならなかったのだ。多分ぼんやり光が反射してかすんでいる辺りが天井なのだろうか、その銀の棒が天井の霧に消えてしまうまでの間に、小さな四角いしなびた箱がぽつんと浮かんでいるのが見えた。その黒い表紙の皮と黒いページの側面を彼は見つめた。
彼が待ちわびている透明な液体は、その本が突き刺さっている傷口から流れ出してきていた。赤土の本の流す透明な血はまた何度もしたたり落ちて、床を濡らした。
アンフィはまた両手を床に突きその貴重な液が床に染み込んで無くなってしまわない内に急いでそれに向かって舌を延ばした。
そして、彼の舌がそれに触れた瞬間、彼の中に言葉が浮かび上がってきた。彼は赤土の本をそうやってしか読むことが出来ないのだ。彼は舌の表面の黒い斑点の痙攣から、本から送り届けられた言葉を知ろうとした。
「得体の知れない川を渡り、眠りの中で赤土に足の裏を汚す。
それを払って逃げ出す者。それを撃ち殺すための銃弾は緑の花びらで出来ている。
花びらを死体で隠す者にその銃弾を渡すなら・・・」
彼はまた自分の体の中にその言葉が落ち込んでいくのを感じ、その苦しさにため息をもらした。彼自身の意識の皮が何度も剥ぎ取られて、それに赤土の本の言葉が写されていったのだ。
「レザラクス、皮を剥ぎ取られた者。自らの肉を服として着る。
限られた風は緑にそれをはためかせ、レザラクスに偽りの未来を与える。」
終わりまで読み終わった彼は、それは教則ではなくレザラクスの歌った歌であることを知った。初めて地面に降り立ったレザラクスは嬉しくて三十六の歌を世界に送った。その中の十二個をアンフィは知った。それもアンフィがスクンエラである、ここ数十年の間にその歌はもたらされたのだ。なぜ、自分の代になって新しい教則が読みとられることがほとんどなくなってしまい、初めて生まれたレザラクスの歌ばかりが増えていったのか、彼には不思議でならなかった。
そして、彼はそれを考える内に、それは人間達が自分たちの世界にほとんど訪れなくなったことと何か関係があるのではないかというところに行き着いた。
アンフィの前の代のスクンエラは人間は赤い羽根の綿毛の野に去った、と言った。
「苦しみの野。」
自分たちは遙か昔にそんなところから解放されたはずなのに、誰かそこに行って、人間達を救い出さなければならなくなるかもしれない。人間達はレザラクス達のもとを訪れなくなったから、そこに行かなければならなくなったのだろうか。それとも望んでそうしたのかもしれないな。確かにそうであるのならば、死に絶えて当然であると言えるだろう。
私たちはひょっとして死に憧れ、それを満たすために人間を見たいと思ってきたんじゃないだろうか。そういう、突拍子のない空想が彼の中に浮かんだ。
彼はゆっくり立ち上がって、もう一度銀のドリルに突き刺さった、赤土の本を見上げた。その本は目に見えないゆっくりしたスピードで回りながら彼の方に降りてきているはずだ。そして、銀の棒の切れ目に達したときやっとプラックスはその本の中身を直に自分の目で見ることが出来るとされていた。それにはまだ一万年以上はかかるのだろう。
「その時やっと分かる。スクンエラが許された、間接的にあの本を読む方法がちゃんと正しかったかどうかが。」
アンフィはそうではなく、たとえスクンエラの読んできた内容が違っていたとしても、舌を使って読む方法の方が赤土の本を本当に知ることが出来るのだと思いたかった。
すると、また赤土の本の見られたことのない活字から、神の唾液が静かに流され始めたのを彼は嗅ぎ取ると、それに備えて、腰を下ろした。
それを見ていると彼の中にある想像が生まれた。赤土の本は実はレザラクスの皮で出来ているのではないかというどうしようもない空想だった。だから、本の流す体液はレザラクスの匂いに似ているのか。アンフィは初めて神の唾液を舐めたときから、その匂いが意外なことに今までに嗅いだことのある匂いに何か似ているような気がして仕方がなかったが、「そうだったんだ。」と静かに呟いた。そして、また部屋に満ちた光の霧にその音はしっとりと吸収されていった。
そう思うと彼はその事をどうしても確かめてみたくなった。でも、どうやれば良いんだろうか・・アンフィは今にも本から出た唾液が銀の棒の先から何粒も落ちそうなのを無視して急に立ち上がった。そのためか彼は激しい目眩を感じたが、数秒待つとそれは止んだ。
立ち上がった彼の目の前にはちょうどその銀の棒の切っ先があった。アンフィはそれをそんなに間近で見るのは初めてだった。その小指ぐらいの大きさの頂点は何十枚ものメスの刃を寄せ集めて出来ているようで見ていてとても綺麗だった。彼はとても安らかな気持ちで舌を前に延ばすと銀の歯の先に集まった透明な滴に向かって激しく突き出した。
それでも意外なことに彼は何も痛みを感じなかった。
けれども、床にぽつぽつ降り始めた赤い粒達を見つけると自分の舌が傷ついたことは分かった。それはこの部屋で彼が初めてみた色といえるものだった。彼は静かに唇を閉じようとした。だが、彼は口をうまく閉じることは出来なかった。不思議に思って唇でまさぐると舌を挟んで上の方と下の方に冷たい銀の輝きを見つけた。
つまり、彼の舌を銀の棒が貫いていたのだ。しかし、彼はそれを全く不快になど思わなかった。いつまででも神の気違いじみた体をそうやって抱きしめることができるのなら、それも嫌なことではなかった。プラックスはただ、そうやって暖かみを感じられる場所を闇雲になって探し待っているだけかもしれなかった。
しばらくして新しい神の唾液が彼の舌の上に直接染み込んでいった。それは彼に激しい苦しみをもたらした。その苦しみの中で彼は自分のいつも聴いていた歌を歌う初めてのレザラクスの姿を見た。
そのレザラクスはほんの少しの間彼のことを見つめていたが、すぐに後ろを振り返ると歩き去ってしまった。彼女はどこかの草原にいるようだった。首からは長くピンク色の鎖のネックレスが見えた。しかし、それは彼女の髪よりも長く地面に引きずられていた。そんな長い首飾りなんてあるのだろうか。とぼんやり考えていると、彼女の何歩か後ろに鎖の切れ端が見えた。それを見てアンフィは彼女が自分でその鎖を食い千切ったに違いがないと思った。なぜなら、桃色の鎖の端は彼女の血で黒くなっていたからだ。そして、もう一度彼女はアンフィの方を振り返ると彼女の背丈よりも高い草の間に姿を消した。
彼女がその草のカーテンを閉じた瞬間、草が揺れて小さな赤い花が頭を出した。アンフィはその草の先にある小さな花をもっとよく見たいと思った。だが、強い風が吹いて草の壁をはためかせ、花びらの首から上を刈り取って宙に浮かべた。そして、その花びらは地面に落ちることもなく、ゆっくりふわふわ浮いて飛んでいってしまった。
それは、花などではなく綿毛だったのだ。小鳥の赤い綿毛の咲くところ。苦しみの野。
彼女は始め、そこからその草原を乗り越えてこちら側に来たのだし、また、向こう側に去ってしまった。なぜ、去ったのだろうか。
レザラクスとプラックスはたとえ最初はそこからやってきたのにせよ、そこに行くことはもう世界が終わりを遂げるときまでないはずだったのに。
それなのになぜ、一番始めのレザラクスはそこに去ったのだろうか。しかも、彼女は薄桃色の貝の鎖を食いちぎって、自分からそこに行ったのだ。ただ、彼女の気が狂っていただけなんだろうか。しかし、彼女の冷静で優しげな表情がそれを否定していた。そうだ、彼女は自分から望んでそこに行ったにせよ、すぐに連れ戻されて、その罰に皮をはがれたんじゃないだろうか。
これで、アンフィは自分の疑問が少し解けたような気がした。天井近くにある赤土の本を見上げると、赤い綿毛の咲く野にいた彼女と同じ香りがしている気がした。そして、彼女は彼に、自分は皮をはがれたのではなく、自ら望んで剥いでプラックス達に手渡した、ということを語った。
「プラックス達に着て貰うために。だって、彼らは震えていたもの。」
アンフィは赤土の本が一番初めのレザラクスの皮で出来ていることを知った。
プラックス達はその皮で本を作ったのだろう。逃げ出していた彼女の皮膚には赤い綿毛の野にある赤土がべっとりこびりついていた。だから、赤土の本というんだ。今は、しわしわになって、黒く縮れてしまっていたが、アンフィには元の美しい肌が見える気がした。
「やはり、プラックスとレザラクスは元は違う種類だったんだ。だが、なぜプラックスはそのレザラクスの皮をわざわざ本になどしたのだろう。」
それを考えるとアンフィは口に出すのも嫌になってしまった。彼らはそのレザラクスをより長く楽しみ続ける方法を考え出しただけなのだ。彼女を奴隷として、ただの生殖器の断片として、しかもそれを神として祭った。
それなら、それを貫く棒はプラックスのペニスという訳か。
彼はまだ舌を串刺しにされたまま、もごもごやっていた。ようやくその棒を引き抜くにはもう一度しゃがめば良いことに気が付いたアンフィは舌が千切られるような痛みを感じた。やっと神の体が落ち着くところを探り当てたのだからそのままでいてほしいとだだをこねているのだろう。
やっと舌の皮を剥がれそうになりながら銀の棒から舌を引き離すと、彼は赤土の本の部屋を後にした。螺旋階段を登りながら、後ろを振り返ると自分の舌からしたたり落ちた黒い血の跡が小さく点々とあった。
「スクンエラの舌の跡は彼らに削り取られた、傷の跡と言いたいのか?」
アンフィはろれつの回らない口でそう吐き捨てた。彼は神官衣の裾を裂くとそれを自分の人よりも倍ぐらいに長い舌に素早く巻き付けた。
「それならば、本が銀の棒の一番下まで下りきるまでの間がプラックスがレザラクスをつなぎ止める奴隷期間ということになる。」
だが、本当はそうではなく銀の棒に貫かれているのはプラックス自身であるようにも思えた。彼女は自分から進んでプラックスに皮を着て貰おうと差し出した、と言ってたじゃないか。彼女はなぜプラックスに皮を恵んでやったのだろうか、そのままでは凍え死んでしまうから、それを哀れんでのことなのだろうか。
「それなら、どうしようもない馬鹿じゃないか。自分が死んでまでそんなことをするなんて。」
どっちにしろ、今彼が関心があるのは、あの初めてのレザラクスが去った野原の向こう側は一体どんなだろうかということだけだった。また、絶対に死なないはずのレザラクスとプラックスの一番始めの者がすでに死んでいたということが、彼をうろたえさせた。
「本当に彼女が死んでしまったかどうかどうにか確かめる方法は無いだろうか。しかし、私はそんなことをしている暇なんて、残されていない。
私はまた若いレザラクスの体を必要としなければいけないのか。」
アンフィはせめて自分がスクンエラとして彼女の言葉を聞き取ることが出来たことで、罪が軽くなってくれれば良いがと思いつつ外に出る扉を開けた。自分がそこにスクンエラとして戻ることはもはやないということを半ば確信しながら。
「彼女は本当は殺されたんじゃないだろうか。
決して死ぬことのないプラックス、レザラクス。その一番最初の者が殺されていたとしたら。」
彼は今日あったことは誰にも話すつもりにはなれなかった。たとえそれがスクンエラという言葉を舐め取り、伝える者としての職務に背くことだとしても。
彼はさっき見た螺旋階段に落ちていた血の粒が、自分を撃ち殺そうとしている弾丸になったのを感じた。