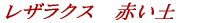
九章 アンフィ・ブラスツゥラ
「櫛をも通さぬ、固くなった草の毛を生やし、緑の息を吐く、繋がれている鎖は海岸に打ち上げられた、貝の薄桃色、レザラクスの色。」
レザラクス 第二十四の歌 赤土の本
アンフィ・ブラスツゥラは自分に残されている時間が刻一刻と少なくなっているのをはっきりと気付きながらも、とてもゆっくりした足取りで歩いていた。この様な西の端の砂漠の地方では昼間は暑すぎたので、彼は夜起きて歩くことにしていた。
誰も道連れはいず、彼一人だった。仮の神の子宮までの道のりはまだたっぷり残っていて、このペースでは一週間かかるのかもしれなかった。彼もまた他のこの国のプラックスと同じように、余り自動車に乗るのを好んでいなかった。車はとてつもなく重い物か急ぐ物に限って使われていた。
それは、この数十年人間達の世界から、どのような機械でさえ貢がれることが無くなってしまったのだから、当然だった。その燃料さえ、非常に貴重だった。一体、人間達はどうしてしまったのだろうか、本当に赤土の本に最近書かれたように、全て死に絶えようとしているのだろうか。
もしそうであるのならば、私たちは人間達を助けるために使いを出さねばならない、と赤土の本に書かれる予感がアンフィはしていた。
しかし、その文章が書かれる瞬間をアンフィは見ることが出来ない。たった一人しかいない、スクンエラの地位を彼はイエルハブーンに既に譲ったからだ。
「彼だったら、きっとうまく読むことが出来るに違いない。彼の舌に浮き出した斑紋、それはスクンエラにしてはひどく独特すぎたかもしれない。だけど、彼の舌の読みとる力は私よりもずっと敏感だ。
それとも、逆に敏感すぎて、危険かもしれないが。」
アンフィは既に灰色に染まり始めた髪の毛を長く、背中に括っていた。普通のプラックスなら、レザラクスから変わった時期にそんな鬱陶しいものを綺麗に刈り込んで捨ててしまうのが当たり前だったのだが、彼はそのまま伸ばし続けていた。誰かがその事をあからさまに非難するのなら、切ればよいと思っていたが、あえてそうする者は誰もいなかった。
レザラクスは髪の毛を切ってはならない、と赤土の本の教則に書かれていたが、プラックスの髪の毛についてはどこにも、一言も触れられていなかった。だからプラックスが髪の毛を刈り込むのは自分がレザラクスではなくプラックスになったのだということを示そうとしている以外の別の意味は本当は無かったのだ。
もっとも、赤土の本を直に読むことが出来る唯一のプラックスであるスクンエラに本の解釈を巡る論争を仕掛けるのは余りに馬鹿げていたから、誰も何も言わなかったのかもしれなかった。だが、また最近のプラックスの若い者の内にも自分のように毛を伸ばす者もいるとも聞いていたが今のアンフィにはそんなことはどうでも良くなってしまった。
アンフィは自分が六十年前にレザラクスだったとき、夜に歯を磨こうと鏡を覗き込むと舌の先っぽのところに黒いインクを舐めたような小さな染みを見つけた。アンフィはそれを一生懸命タオルに擦り付けたり、石鹸を擦り付けた手で洗ったりして取ろうとしたが、染みは無くなることはなく、逆に日が経つに連れ、どんどん広がってきて、また数も増した。別に特に痛みなどは無かったが、逆に異常に物の味を敏感に感じ取るようになって、世の中全ての物が不味く感じて仕方がなかった。
「そうだ。あの時の私はあの気味の悪いイモリの腹のような斑紋を自分の舌の上に見つけて、恐ろしくなって誰にも言わずに済まそうとしていたんだった。だから、誰と話すときも舌を見られないように口の隙間をほとんど開けずに喋っていた。まるで、常に自分自身を人形にして、腹話術をやってのけてるみたいだった。」
そうして、誰にも知られずにいれば知らない内にその奇妙な病気は治るはずだ、と自分に言い聞かせながら、一月ぐらいすると彼は不思議な感覚を感じ始めた。何かを舐めるとその物が元にあったところが感じ取れるようになってきたのだ。
やっと今になってアンフィはその事を考えると、自分が全ての食べ物が嫌いになってしまった理由が分かった気がした。じゃがいもを食べると土の中で生き埋めになった気がしたし、鶏肉を食べると自分が首を跳ね飛ばされたときの感覚をはっきり思い出したのだから、何も食べれなくなるはずだった。その時はただ食べることによって引き起こされる数限りない悪夢に訳も分からず悩まされるしかなかったのだ。
しかし、パンとミルクだけはその様な恐ろしい幻覚を彼に与えなかったので食べ続けることが出来た。そのような偏食を頑固に守り通そうとするアンフィにプラックスの教師達は憎しみを覚えたのだろう、様々な罰を与えて彼にそれを無理矢理食わそうとして笑っていた。
それからしばらくして、アンフィの舌が真っ黒く爛れていることが教師達にばれてしまった。はじめて彼がキスをした相手のレザラクスが驚いて告げ口したのに違いがなかった。そして、しかるべき措置が取られた。プラックスの神官医に診せられたのだ。彼はまず、嬉しそうな驚きの声を上げると、ガッチリとした開口器具で彼女の口を固定して、しげしげと魅入った。それから、仲間のプラックス達を診察室に呼び込むとみんなでがやがやと見物を始めた。
その相談の結果導き出された結論は彼がスクンエラであるということだったのだ。
「スクンエラ」彼はその呪わしい言葉にその後の一生を縛り付け続けなければならなかった。そして、その事は同時にアンフィがこの世で二十番目までのレザラクスであることを証明していた。
スクンエラであることは彼に様々な苦痛を与え続けてきたが、またもう一度、帰胎しさえすれば、レザラクスになってその事から逃れられる、また、プラックスになるまでのしばらくの間だけだが。アンフィは自分にやっと訪れた安息の時を思うとほっとしていた。
「しかし、その宿主になぜ自分はリルファーとかいう、訳の分からない少女を選んだのだろうか。」アンフィは不安に感じ始めた。帰胎するレザラクスを決めようとしていて、仮の神の子宮と連絡を取り合っていたときに、トワンス・ロフからの短い手紙に自分自身を食おうとした奇妙なレザラクスがいると書いてあったのだ。
「そうか、そうだった。それで私はそれを読んだだけで彼女が味わった自分自身の味を想像することが出来たのだった。しかし、そんな下らないことに簡単に魅せられてしまうとはスクンエラであるということは本当にどうしようもないものだな。」
彼はそう言って疲れたようにため息をつくと、休んでいる間にお茶を沸かすために灯した小さなたき火の上に、足で蹴って砂を被せて消した。その時のじゅっという音と共に彼の口の中に忍び込んできた、灰のかすが彼に極めて不快な感覚を起こさせたので、彼は何度も地面に唾を吐き掛けてそれを忘れようとした。
それから、重いリュックを背負うと歩き出そうとしたが、足が曲がったままいうことを聞かずに倒れ込んでしまった。帰胎が必要になるということはこんなにも体を弱らせてしまうんだということに彼はまた軽いショックを覚えた。
「私は若い肉、今まで嫌ってきたそんな物に頼らなくてはいけなくなってしまった。でも早いところ帰胎を済ませてそんなことはとっとと全て忘れてしまおう。」
彼は薪にしていた折れた枝の内一番丈夫そうなものを選ぶとそれに寄りかかりながら立ち上がった。やはり、イエルの言うとおりに自分の足で歩く事なんて選ばずに馬車を頼めば良かった。と後悔してまた、苦い唾を吐きながら。その唾は地面に落ちると自分が呪われていることにびっくりして生き物のようにねちねち音を立てた。
その音は彼がかつてスクンエラとして白い草の部屋にいた時に何度も聞いた音だった。彼がその呪われた舌を使って、赤土の本が突き刺さっている銀の柱から滴り落ちる透明な粘液を舐め取っていたときに聞いていた音がそれにとてもよく似ていた。