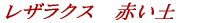
八章 二節
次の日の朝になると、自分の入れられている部屋のだいたいの様子が見えるようになってきた。といっても薄汚い小さなベッドとイスが一脚あるだけの狭苦しい部屋だった。案の定、今彼女がいる部屋には赤いガラスは無かった。それは、ただ彼女のためにガラスを取り外したのではなく、もともとその部屋は塔の五階よりも下にあったのだろう。
彼女は立ち上がるとまず、カーテンは閉め切ったままにして、窓を少しだけ開けた。
もし、外からコーラルの部屋を誰かが見上げたら、彼女の目が見えるようになったことがすぐにばれてしまうだろう。そうするとまた、何か嫌なことが起こりそうな気がしたのだ。だが、黙っていてもそれが神官の教師達に分かってしまうのは、時間の問題だった。多分、あの神の子宮の番人が昨日あったことを、洗いざらい話してしまっているに違いないからだ。
「でも、そうと決まったわけではない。彼は教師達が私のことをやっかい払いしたがっている、と言っていた。そうだとすると、私の目を見えるようにしたのは、そこから考えると、余計なことになるかもしれない。」
彼女は閉められた白いカーテンを少しだけ開いた。窓から右目一つだけ覗かせて外を見てみたくなったのだ。そこは異常に力強く、のしかかるように渦巻いている光の世界だった。そうだ、私はあれのことを空と呼んでいたんだ。彼女は世界で初めて、自分が空を見つけたんだ。そう、心の中で呟いた。「私以外には誰も空を見た人はいない。」と。
しかし、またその事が彼女をたまらなく怖がらせたのも事実だった。
彼女は天井のガラスを割ってから今までその部屋から外には出ていなかったが、今なら、久しぶりに自由に塔の中を歩けるかもしれなかった。だが、それは一度、プラックスに見つかるまでの間だけの話だ。ということは、行ける場所は極めて限られてくる。
彼女はどこに行こうか考えた。どこか一つの所に決めなくてはならない。彼女は自分がガラスを割るときに使った、あの赤茶色のぼこぼこした小さな石は一体どうなったのだろうかということが急に気になり始めた。赤ガラスのくずと一緒にゴミ捨て場に埋められたのだろうか。それとも、もしかすると、まだあの部屋に忘れられているかもしれない。机の下とかに転がってしまって。彼女は自分があの部屋にまた行くことを考えると、生き埋めにされるような息苦しさを感じたが、なぜか石があそこにまだある気がして仕方がなかったのだ。
「もしそうなら、あの石は私が見つけなくてはいけない。」
彼女は決心して、パジャマの上にぼろ切れのような緑の肩掛けをかけると廊下に出た。石で出来た廊下は耐えられないぐらい寒かった。他の女の子達は既に授業に出ているのだろう。かなり下の階から、笑い声やおしゃべりする声のこだまがさざ波のようにしんとした中に聞こえていた。教室は二階にあったので、ここはたぶん四階だろう。コーラルの病室は塔の中で誰も寄りつく用のない古い物置ばかりある、四階の部屋の一つを空けたのだ。
コーラルはプラックスの教師達が自分を塔から離れたところにある神官医の館に置かずに、その上、一階のレザラクス達の寮からも離れた所に自分を閉じこめていたことに目眩がするくらいの怒りすら覚えた。「でもちょうど良かった。おかげで上の階に行ける。」
彼女はつるつるした黒い岩で出来た、階段をゆっくり登っていった。塔の中央にある、薄暗い周り階段は登るごとに弱った彼女を苦しめ始めた。五階になると階段の周りの壁と床にガラスが貼られ始め、上に行けば行くほど赤みを増してきたのだ。今の彼女がそれを見ると、赤くどす黒い色が彼女がそこにいてはいけないことをはっきり証明しているような気がしたのだった。「私を守るためのもの。レザラクス全てを守るための。私はまだ、本当にレザラクスなのかしら。それとも、何か別のもの、あの赤茶色の汚らしい石ころと同じなのかもしれない。」
彼女の赤い螺旋状の苦しみは十六階まで行くとやっと終わった。その階まで彼女は前は毎日登ってきていたのだ。午後になったら、一人で勉強したいレザラクスはまた、のこのこやって来るのに決まっている。そして、自分がなぜこんな事に耐えられていたんだろう、と、朦朧と考えながら、コーラルは自分の牢だった部屋の戸を人差し指でそっと押した。やはり、鍵は掛けられていなかった。当たり前だ。レザラクスの塔では全ての部屋の鍵は決して掛けてはいけないことになっている。それとも、コーラルがここに再び、しかも、自ら望んでここに来る事なんて考えられなかったからかもしれない。
コーラルは音もなく開いたドアの中をそっと覗き込んだ。自分がそこで流した黒い血の固まりと赤いガラスの破片の山がまだ、そこで待ちかまえている気がしたからだ。
しかし、拍子はずれな事に部屋にはそんな異常なことが起こった証拠など何も残っていなかった。プラックスの神官長は番人たちに何一つ残すなと言って掃除をさせたのに違いがなかった。
「そうすると、石はここにあるはずないか。」
コーラルは落胆して部屋の中に入ると、とりあえずドアを閉め、イスに座った。部屋の壁を見るとまだ、黒い岩がむき出しになっていた。その表面には驚いたことに赤い筋が何本も走っていた。ちょうどチョークでいたずら書きしたみたいな線だった。コーラルはその線の色をじっと見る内にその線がどうして描かれたのか分かった。自分がなげた石がぶつかってあんな模様が出来たのだ。コーラルはその無数の数の線を見て、自分がそんなに異常な回数天井のガラスに目がけて石を投げつけていたことに驚いて、怖くさえ感じた。
「でも、あるのはこれだけか。多分あの線はどんなにこすっても消えなかったんだろうな。
それにしても、誰にも見つからずにここまでこれたこと自体幸運じゃ無いか。でも、裏庭に行って、ゴミ捨て場を掘り返すのなんて無理に決まっている。私はどうしてここに石があるのなんて思ったんだろう。」
そこまで考えるとやっと彼女は机の下を調べようと思っていたことを思い出した。しかし、そんなところが見逃されているはずもなく綺麗にちり一つも無いぐらいにふき取られていた。
彼女は落胆して、そこの天井にまだ赤いガラスがはめ込まれていたときにしていたことを思い出して、もう一度だけやってみようと、床に寝転がって天井を見た。
すると、やはり天井にも壁の線と同じように赤茶色の点々が無数にあるのが見えた。
「ふふ。なんか黒い空にうかぶ汚らしい星みたいね。ランニが見たのとは全然違ってるわ。でも、不思議ね。すごく濃い星もあれば、何百年も前に最後にまたたいたみたいに消えかかっている星もある。」
コーラルはもっとはっきり見てみようと立ち上がると、天井を見上げた。染みの一つがおかしな事に黒い影を持っていたのだ。そんなはずはないわ。コーラルは呟いたが、その後の言葉は消えてしまった。
天井の一つの汚れが膨らみを持っていて、それが日の光にきらり、きらりと光っていた。石は天井にあったのだ。黒い岩の隙間にねじ込まれるようにしてぶら下がっていた。
そして、コーラルはぼんやりそれを眺めていると、徐々にそれが緩まって来ているのが分かった。黒い岩は赤い石を嫌がって押し戻そうとしている。コーラルは手を伸ばしたって、そこには届くはずがないことは分かっていたからどうしようかと迷った。イスや机は床に貼り付けられて、動かせないし、放っておいたら床にひどくぶつかって粉々になるかもしれない。
コーラルは部屋を出てなにか探そうかためらっていた。しかし、今にも石は床に向かって最後の突進を始めそうに見えた。コーラルはふと思いついて肩掛けをはずすと床に置いた。これだと少しはクッションになるかもしれない。
石が落ちる瞬間、コーラルには真っ赤に熱くなった流れ星が自分に落ちてくるようにさえ感じた。しかし、床の肩掛けの上に落ちたときはとても静かで、ただコトリと一回言ったきりだった。石は全く割れずに彼女の手の中にあった。
考えてみれば、自分が何度も天井のガラスにぶつけたときも割れなかったんだから、そんなに心配することはなかったのではないだろうか。
その石は赤い鱗のようなものでびっしり覆われていて、そっと触れるとまだ暖かかった。
「あなたはずっと昔からそんな姿だったんでしょうね。でも、初めて私があなたを見たときから比べると、すごくすり減ってしまったわ。こんなに何回も投げつけたりしてごめんなさいね。」
顔に近づけて匂いを嗅いでみるとバターの匂いは消えていた。そして、今まで嗅いだことのない不思議な香りがしていた。まるで何かの甘い草のような。
すると、彼女のいる部屋の方に向かって誰かの歩く音がしていた。あの音は間違いなくプラックスの番人の履く、そこの平べったい靴の音だ。それに教師の足音もする。
コーラルを探しに来たのに違いがない。コーラルは自分がその石ころを探しに来たことを彼らに知られてしまうことがたまらなく嫌に感じた。別にそんなに怖がらなくたって、ポケットに入れておけば見つからないかもしれない。でも、あいつらは私を脱がして調べるかもしれない。それで私を裸にしておきながら、石は絶対に私が探せないところに隠すに決まってるわ。石は私の所に来たんだから、私がなんとかしなくちゃ。
コーラルは、廊下の角をその二組の足音が曲がってこちらに来るのを感じると、窓に急いで走った。それから、さび付いたガラス窓を力を込めて開けると、石を出来るだけ遠くにぎゅっと握りしめて、空に向かって投げた。
コーラルが振り返ると、教師のエグラムスと番人がすでに部屋の中にいて、なにやらにやついていた。「おや、目が見えないと聞いていたが、よくここまで来れたな。一体何をしていたんだ。もうここにはお前のためのものは何一つ無いのが分かってるだろう。」
エグラムスはコーラルの背後の窓が開けられていて、そこから激しく風が吹き込んでくるのに気が付いた。
「お前、こんなに死にそうに寒いっていうのに、どうしてそんなに窓を大きく開けている。 おい、ヘリトファー馬鹿みたいに突っ立ってないであの窓を閉めてこい。あのレザラクスは窓の閉め方を忘れたんだろう。」
ヘリトファーはその赤っぽいにきび面をコーラルの方にずんずん突き出してくると、コーラルの目を覗き込んだ。
「へえ。やっぱり見えるようになったみたいだ。めくらのレザラクスなんて初めて聞いたけど、それを治せる方がいるなんてそいつも初めてだな。
お前。せっかく治して頂いたんだから大事にしろよ。おい、聞いてるのか?」
ヘリトファーは風で髪がめちゃくちゃに顔にかかっても全く見向きもしない、コーラルを放っておいて窓を苦労してやっと閉め終えた。
ようやく吹き込む風が収まってエグラムスはほっとしたようだ。
「さて、これから、神官長の所に行って何をしていたのか白状して貰うぞ。頼むから行くまでの間に、私たちが理解できそうな理由を考えといてくれ。君は私たちの中で全くの謎なんだよ。」
コーラルはエグラムスの黒い目を一瞬だけ睨み付けると、こいつらになんて世界が終わるまで一言だって話すことはない、と思った。
しかし、ヘリトファーが激しく腕を掴んで引っ張るのでコーラルはそれに従った。
「まてよ。お前、窓を開けていた理由は、そこから飛び降りようと思っていたからなんて言うのだけは勘弁してくれよ。とくに教育神官長の前ではな。」
コーラルはその二日後、トワンス・ロフに連れられて、レザラクスの塔を出た。
トワンスは旅の間中ほとんど口を利かずに、コーラルの遙か先にまで一人で早足で歩き、あまりに距離が離れたのでコーラルが置いて行かれたのではないか。と不安になると、決まってこちらを振り返って待っていた。その青白くて痩せた、引きつった表情は、彼女を連れて旅すると言ったことを後悔しているのか、それとも満足しているのか全く分からなかった。不思議なことに彼は、白いマスクも神官衣も付けずにプラックスの農民のようなみすぼらしい格好をしていた。多分その格好が一番旅をしやすかったのだろう。
ただ、コーラルは必死に遅れないでついていく以外はなかった。地図も食べ物もほとんど持たずにこんな所を一人でさまよっていたら、夜になると必ずと言っていいほど聞こえる、エイフォンダのカラカラいう鳴き声に呪い殺されるに違いがなかった。
それは数少ないトワンスが教えてくれたことだ。夜中に砂だらけのチクチクした寝心地のとてもよいとはいえない灌木をベッド代わりに休んでいたとき、トタン板をこすり合わせるような、騒々しい陽気な音がした。彼女はとても驚いて飛び起きたが、少し面白くなってロフに聞いた。
「あれは何の音?何かの楽器みたい。」
彼は毛布にくるまり背中を向けて寝ころんだまま答えた。消えかかったたき火がオレンジ色に照らしていた。
「ああ。エイフォンダ・キシダという幻みたいな怪物さ。そいつの、のどの中の楽器の音だ。あのカラカラいう音で虫を痺れさせて動けなくなったところを食らいつく。まあ小さな足のある大きな蛇といったところだろうか。」
「ふうん。ちょっと面白い蛇ね、私も見てみたいわ。でも、私もその音で痺れてしまったりしないかしら。」コーラルは立ち上がったまま、辺りの闇を見回してみた。
「少し、変な匂いがしてきた。たぶんその蛇が一匹の虫の頭を食いちぎったときに出た匂いよ。そんな虫、本当に美味しいのかな。」
振り返ると、彼はいつの間にかあぐらをかいて座っていた。たき火をつついてから、枯れ枝を継ぎ足していたのだ。
「お前は異常に鼻が敏感だな。その虫が頭を食いちぎられた匂いが分かるのなら、あまりエイフォンダに近づかないことだな。そうしないと、お前の頭がなくなってしまうぞ。エイフォンダはレザラクスを好んで呪い殺すと言われているからな。」
コーラルはそれを聞いてから、夜になるとちぎった布きれを耳に押し込んで眠ることにした。今にも冷たくひんやりしたその蛇の肌が、毛布の中に忍び入ってきてのしかかってくることを夢見ながら。
死の胎児になったプラックスが自分の中に静かに入ってくるときというのはそれと同じ様な感じがするのではないだろうか。
コーラルはすり切れた毛布の中で、長時間サンダルで歩いて傷だらけになった足の裏を、やわらかいふくらはぎに当てていたわりながら、寒さに震えていた。それにいつになったらその仮の神の子宮につくのだろうか。コーラルは何日歩けばそこに着くのか全く教えられていなかったことに今更ながら気付いた。しかし、そんなことすら、彼に聞く気が起こらなかったのだ。
「そう言えば、私の先輩達も帰胎を受け入れられるようになったら、その子宮に行ったのに違いがないけど、その時は彼の様な案内がいたのかしら。
それに、私はまだ、帰胎を受け入れられるようになんて明らかになっていないのに、どうしてそこに行こうとしているのだろうか。」彼女は教師達の用意した予想もつかないような罰に静かに身震いした。
「ランニ。私はランニにちゃんとお別れを言ったのかしら。私は十年ぶりぐらいにあの塔から出られるから、何か楽しいところにでも行けると勘違いしてたんだ。
いいえ、ちがう。あの塔以外はどこだって楽しいと思いこんでただけなんだ。」
ただ、こんなしけた砂漠の中を飢え死にしそうになりながら、急かされて歩き続けるだけなんて。コーラルはエイフォンダの鳴き声を何とか防ごうと頭の上まですっぽり毛布を被り、両手で耳をぎゅっと固く押さえながら、少しでも眠っておこうと努力を始めた。
また、それから一週間ほど歩くと、ぼうぼうに生えた草の間から、細長い蛇が寝そべったような奇妙な建物が表れた。黒々とした岩の天井の天辺には見たこともない吹き出物みたいな小さな紫の実が沢山なっていた。彼女はそんな気味の悪い建物から一刻も早く離れたかったので、急いで森の中に抜ける道の方に走っていこうとすると、トワンスが大声で彼女に叫んだ。
「ここだ、コーラル。神聖なる仮の神の子宮とは。ここでレザラクス達が無数に犯され生まれ変わってきたんだ。君のための穴蔵だよ。さあ。早く戻ってこい。」
彼女は彼が産まれて初めて出したような大声を出しているのを見て、そのまま森の中に走り去ってしまいたいと思った。深い緑色の森の中でエイフォンダの化け物に食われる方がまだましに思えたのだ。そして、また少し走って彼が追いかけてこないか館の入り口の方を振り返った。驚いたことに彼は全くこっちに来ようとはせずに、今度は無言で大きく手を振っていた。何かの印を送っているかのように。そして、彼の大げさに振り上げた手の中に光る銀色の何かを見つけて立ち止まった。一体なんだろうか。ただの館の鍵なんだろうか。いいえ、多分違うわ。彼女はそれが何か知りたくて仕方がなくなったのだろう。一度は逃げだそうとした彼の方に悠然と歩き始めた。
黒くもつれた髪を森の光にたなびかせて、気持ちよさそうな薄笑いを浮かべながら。
一枚の岩の穴にはめ込まれた、ひどく厚ぼったい木の扉をくぐり抜けると中には薄暗くなま暖かい空気が彼女を待っていた。それに、何かずっと前に腐った野菜のような香りがしていた。
「ふふ。すぐになれるさ、それほど酷い所でもない。」
彼はまた背中を向けて歩き出した。床に敷かれた石は大トカゲの背中のように波打っていて、彼女はそのとがった先をピョンピョン飛び跳ねながら歩いた。そして、何度もその隙間に足をつっこんで転びそうになってよろけた。壁に手をついて立ち上がろうとするとその壁は恐ろしくすべすべしていて凍り付いているように冷たかった。コーラルは驚いて思わず声を上げた。
「何をおかしな声を出しているんだ、コーラル。次の角を曲がるからきょろきょろしていて見失うんじゃないぞ。」彼の固い革靴の底の音がうつろに響いていた。その音は彼女を不安にさせた。
「ははあ、分かったぞ、君が何を怖がっているのか。この建物は年々南北方向に縮まってきている。だから床が皺だらけで、壁がつるつるのままなんだ。
つまりこの建物はただの一つの鉄で出来た金属の固まりなんだよ。」
彼女は何のことかよく分からずにそれを聞いていた。彼女はただ、そのひび割れの底にたまっている黒い水に靴の中まで浸してしまったので、ひんやりして気持ちが悪くて仕方がなかっただけだった。
しばらくして、彼女は灰色の壁をした狭苦しい部屋に入れられた。そこでトワンスは上着を脱いでテーブルの上に投げ出すとただ、そこで待っていろと命令するとすぐに部屋を出ていった。
コーラルはその部屋に入った瞬間に、仮の神の子宮に漂っている匂いの原因が分かった気がした。それは甘い血の匂いだった。当たり前だ。そこは彼女たちの血が捧げられる場所だからだ。「だからこんなに静かなんだ。彼女たちはもう声を出す必要もない。」
コーラルが一人で呟くと息が白く浮いた。そして、ゆっくり目をトワンスの置いていったコートの方に移していった。その灰色のぼろ切れを着て彼はいつも歩き回っているのだ。旅の途中に何十回も浴びた熱い雨がそのコートの元の色を全く分からなくしていた。
しかし、そのコートの干からびた皮の一点だけが違っていた。とても明るく銀色に光っていたのだ。銀色の小さな細い針がポケットの口の所から顔を覗かせていた。そのきらめきから彼女は目が離せなくなってそっと近づいていった。それから、そのポケットの中に手を差し込んでみると、丸い金属の膨らみを感じた。彼女はその針で手を刺さないように気を付けながら、引きだした手を開いた。その手のひらに収まる平べったい銀の板には、見たこともない複雑な模様が彫り込まれていて、とても綺麗だった。ブローチか何かの装飾品に一見見えなくはなかったが、その端に細く延びる鋭い銀の針がその事を否定していた。こんな物を身につけたり、髪に挿したりしたら、すぐにその針が突き刺さってしまうだろう。
コーラルはその針がかつて自分に刺された物であることが分かった。それにその小さな板を、さっき彼が振って見せたのだということも。
「なぜ、私はこの銀の蜂が私を刺して目を見えるようにしてくれたのか分かったんだろう。そうだ。この模様だ。何かに似ているかもしれないと思っていたら、それは、赤いガラスを突き破った、私の投げ捨てたあの赤い石と同じ皮膚をしている。だから、私は分かったんだわ。同じ香りがするもの。そう、私の血の香り。」
彼女はその針の先を自分の血がうっすら覆っていたときの様子が目に浮かぶ気がした。「この針が私を刺したとき、私はその血を見ることは出来なかった。それならもう一度、まぶたをこれで刺したとしたら、また見えなくなるのだろうか、ふふ。そしたら、やっぱり私はその先に付く血の小さな玉を見る事なんて出来はしないのだわ。」
彼女はその銀の蜜蜂の針の先を顔のすぐ近くまで持ち上げて見ていた。まだ、しばらく外の世界を見ていなかった目ではそんな小さな物はかすんで見えたからだ。そうすると、針の先の部分には小さな穴が開いていて、何かの液がそこから押し出されたのだろう、ということに気が付いた。そうであるなら、その薬を入れるための隙間がこの銀の胴体のどこかにあるはずだ。彼女はその背中の複雑な模様を少し爪でひっかいてみた。しかし、開きそうな所なんて全く見つかりそうもなかった。コーラルは軽くため息を付くとそれをひっくり返した。
驚いたことに裏側は素晴らしく磨き込まれていて、指を滑らせるとすべすべしていた。今まで彼女はそれを握りしめていたのにそれに気付かずにいたことを全く変だとも思わずに、彼女はじっとそれを見た。その様に磨かれている理由をコーラルは何とか考えずに済まそうと努力をしたが、それは無駄だった。
あの塔にいたとき、彼女にトワンス・ロフがそれを押しつけたとき、彼は口づけをしたのだ。コーラルのまぶたに。つまり、彼はその蜂を口に含んで彼女を刺したのだ。裏側をじっと指でさすっていくと針先と同じぐらいの小さな穴が二つ開いていた。
もしそれに薬を入れて置くところがどこにもないとしたら、彼が目を見えるようにする薬を直に口に含んで、この奇妙な注射器でまぶたの中に流し込んだということになる。それとも、彼には薬すら使わずに自分の唾液だけで、彼女の目を治したんだろうか。
彼女はその注射器が自分の口の中に収まるのか試そうと口を大きく開いた。そして、縁の部分を舌で舐めると、少し消毒薬の匂いがした。それか、彼の体臭が本当はそんな匂いなのかもしれない。そう、うっとり思うと思い切ってそれを咽の奥まで押し込もうとした。
しかし、その瞬間それは彼女の唇の前から消えていた。
「おい。そんなところでやめておけ。それはプラックスの物だ。レザラクスに使うためのな。だから、君が口にそれを入れたりなんかしたら、きっと恐ろしいことになってしまうぞ。」
振り返ると、灰色に浮かぶ二つのトワンスの目がすぐ近くにあった。いつの間にか彼は部屋の中にいて、コーラルから銀の蜂を奪ったのだ。彼はそれを手の中で静かにもてあそびながら話し始めた。
「確かに、君がそれを口に入れようとしていたのは、正しい利用法だ。だが、この機械には君の目を見えるようにするような、そんな恐ろしい力があるわけではない。ただ、ちょっとした刺激を与えることが出来るというだけのことさ。」
「そう、やっぱり、私を刺した銀の蜂なのね。」
トワンスは灰色の無精髭の生えた顎を少ししかめてみせた。
「銀の蜂? そうか、うまいこというな。これはヒョシャンメクと呼ばれている注射器の一種だ。そうとは言え、今いったように正しく使いさえすれば、この中に薬を忍ばせる必要はない。この針が使われるべき者には必ず、印が浮き出ているんだ。
そしてそれがどういう印かといっても、一見何の変哲もない小さなほくろのようにしか見えない。」
彼は鋭く人差し指を彼女の目の前に突き出すと、コーラルは驚いて後ろによろめいた。
「はは。丁度君のまぶたにそれがあったんだ。どういう訳か私はそのほくろみたいな神聖な印と、ただのほくろを見分けることが出来るんだ。しかし、極たまにしか、それを使う機会などないがね。」
トワンスはいつの間にか木のイスの上にへたり込んでいるコーラルを見下ろして、また、冷ややかに笑い掛けた。
「そうさ。君は薄々気付いていただろうが、私は何度もこうして針を口に含んで君を刺した。ただ、それが恐ろしく長い年月に及んでいるから覚えていないだけの話だ。
つまり、それは君と私が今の体になる前、帰胎する前の私たちだったときのことだよ。私たちは全く気が付かない内に、何度も、いや永遠に同じ事を繰り返して生きてきているんだ。表面的には自分の自由な意志の力によってそれがされているように見えるがね。」
彼は、そのヒュシャンメクを握りしめたまま、コーラルに素早く背中を向けるとまた部屋から出ていこうとした。しかし、ふと思い出したかのように彼女の方を振り返った。
「私は君の目を刺したとき、君の目が本当に見えるようになれば良いと思ったがね。決められているかどうかなんて関係なく。
それから、君がここに来る間に話してくれた、君のあの部屋での様子を考えたんだが、それだって、このことと同じような事じゃないかと私は思うが。」
そこで話を切ると、言葉の効果を確かめようしたのか、彼女の顔を盗み見た。けれども、コーラルは何も感情を表に出さずに静かに言った。まるで、剥製であるかのような青白い頬をしていた。
「そうね。トワンス・ロフさん。私は今のレザラクスになる前の、レザラクスの時、多分石をあの部屋の中で天井に投げつけたのよ。だから、あの部屋の壁には恐ろしい数の赤い線引かれていた。私の前の私もあの部屋の神聖なガラスを割りたかったのかしら。それはどうか分からないけれど。」
呆然としている、コーラルを部屋に置いたまま、何か飲み物でも持ってきてやる。と、トワンスは呟くと、出て行ってしまった。
しかし、コーラルはまた嬉しいことも発見した。「ひょっとすると、あの石だって、同じ石だったのかもしれない。だから、私がまた、もう一度レザラクスになったとしたら、またあの石を握ることが出来るんだ。」
ただ、それはその石がちゃんとあの庭で数十年彼女を待っていてくれたらの話なのだが。
「きっとずっと待っていてくれるわ。あの馬鹿な園丁のプラックスにだって見つからずに。」
しかし、彼女の中に同時に漠然とした不安もよぎった。自分が本当に帰胎を受け入れてプラックスになり、そして、自分自身も若いレザラクスの中に潜り込まなければ、また、レザラクスにはなれないのだ。私はそんな恐ろしいことを本当に受け入れるのだろうか。また、そんなことを何百年もの間続けてきてよく平気だったものだとも思えた。
「そうか、平気なんかじゃないわよね。平気なんかでいられるほど私は普通じゃない。」
そうつぶやいて、トワンスの入れてくるはずの飲み物を待った。どうか私の好きなケシタリギクのお茶ではありませんように。と願わずにはいられなかった。
しかし、ドアの向こうで「おーい、コーラルこの戸を開けてくれ、お盆で手がふさがっていて空けられないんだ。」と、言う声がしたとき、間違いなくケシタリギクの甘い香りがしていた。コーラルはあの男の淹れたケシタリギクの白い花を思うと酷くうんざりした。ケシタリギクは病室で彼女が寝たふりをして、目をつぶっていたときにランニが黙って淹れておいてくれたお茶だったのだから。
それからの、数日間はコーラルにとって驚愕の毎日だった。トワンスは彼女を連れて、仮の神の子宮を案内して回り、そして、保育容器の中の小さな「死の子供」を彼女に見せたのだ。彼女は話に想像していたのとは違って、それを醜いとは思えなかった。むしろ、かわいくてとても好きになってしまったのだ。だから、そのためにコーラルはその数年後帰胎を受け入れたのかもしれなかったし、また、トワンスの勧めに乗って生物学者としての知識を仕入れたコーラルは、仮の神の子宮に戻って来ることを決めたのだろう。
そして、今やプラックスになることを奇妙にも遅らせ続けている唯一のレザラクスである彼女は、熱にうなされて何とか眠りにつこうとベットの中でもがいていた。
「そうだ、何に付いて考えてたんだっけ? ポンヘイトス・クヌズだわ。そうだ、あの木の木の葉は散るときに地面に落ちる前に透明になって消えてしまうという話だった。
でも、その木が実際にあるとしたら、蝶の羽みたいに鱗粉に覆われているのに違いがないってことをリルファーに教えてあげようと思っていたんだった。あの子は多分喜んでくれるわ。そんな、変な話が大好きだもの。」
コーラルは黒い虹の部屋で眠ろうとしているリルファーが、真っ暗な中で降りてくる黒い虹達に、顔を撫でられ続けているのを想像して身震いした。私はあそこに入れられなくて済んで良かったのだろうか、と思いながら。