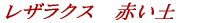
七章
「苦しみの野、気違いの野を越えて、私が舞い降りたのは、千切れた鳥の花、紙切れの赤い花。偽物、偽物の綿帽子の苦しみ。地面に舞い落ちた、綿帽子の種。」
初めて、地面に降りたレザラクスの歌った第一の歌。
リルファーはたった一人で膝の上で拾った糸くずを激しくいじくり回しながら、かすかな声で歌った。そして、ほんの少し前にトワンス・ロフが彼女の部屋に突然やって来て、ノックもせずに突然扉を開けて言っていた事を思い出そうとした。
彼は多分、「君の悪い夢にもついに終わりが来た。お客さんが来たんだ。」とかなんとか言っていたような気がした。私の夢の中に舞い降りた悪い夢の中の気味の悪い人。リルファーはその男が生やしているかもしれないカラスのような長い髪の毛の虹色のきらめきを目をつぶっていても見れそうな気さえした。その男の名前はアンフィ・ブラスツゥラ。リルファーの中に帰胎すると決められたプラックス、男の名前だ。リルファーは気持ちの良い歌の途中でわざと何度でもその言葉を挟みこんでみた。それはまるで魔法の言葉だった。苦々しく彼女を殺すためだけの言葉なのだからそれは当然だった。
終末の歌、私のためだけの歌、私を殺すためだけの歌、
そして、私を蘇らせる歌。確かにレザラクスである彼女は死に、プラックスである男に生まれ変わる。その代わりにアンフィ・ブラスツゥラは、男から女へと生まれ変わるのだった。不思議な生き物、そして唯一の呪われた生き物。神を侮辱するためだけの生き物。神は這いつくばって、レザラクスのヴァギナから流される血を喜んで舐めるのだろう。その血が毒入りだということに半ば気づいているはずなのに。
リルファーはコーラルから聞かされてきた、自分たちの世界のあり方について考えるうちに、いつもどうしようもない妄想にたどり着くことに自分自身で驚いていた。彼女の思考はなめし皮のようにコーラルの言葉によって鍛えられたのだった。
ただ、その皮が鍛えられるほどの強靭さを最初から備えていなかっただけの話だ。
彼女の心の皮膚が過激に擦られた末の炎症が妄想として、歌のように次から次へと心に浮かんだ。だが、コーラルはそれをまるで二度と取れない貴重な小魚の死体を大事にたもですくうようなそぶりで、聞き取ってノートに書き付けていた。ノートこそが彼女の本当のただ一つの親友なのだろう。
コーラルはまた、アンフィ・ブラスツゥラが、なぜ彼女のことを選んだのか分からない。といったことや、アンフィ達、つまり20番目までのプラックスは自分で帰胎するレザラクスを自由に選ぶことが出来るということなどを教えた。
「なぜ、私なのだろう。でも多分あの男、この偽の子宮の番人がアンフィに何か吹き込んだのに違いがない。」
リルファーはロフの事を少し思い出すだけで、彼のいつも口に含んでいる、ハッカを染み込ませた嫌な根の香りを鼻の中に感じて、常に自分に息を吹きかけられているような気までして、吐き気のする気分だった。
「私は何か奇妙な得体の知れない実験にただ使われる、肉の道具なんだ。それは、今熱心に私の呟いているのを聴いている、あなただって同じ事だよね?」
そうリルファーが少し笑いながらかすれた声でいうと、コーラルは驚いてノートから頭を上げた。彼女が今言ったことはコーラル自身も肉の道具だ。という意味なんだろうか。
それともコーラルが彼女を実験台にしていると非難しているのだろうか、どっちが正しいのか、コーラルには決めかねた。それでも、懸命に無表情を保ちながら、コーラルは話し始めた。
「あなたに言っておいてあげたいことがまだあったわ。
アンフィ・ブラスツゥラのことよ。私が彼のことを見たのは十年ぐらい前で、彼がまだ、帰胎する必要なんて、微塵も感じていなかった時の話よ。彼ら、20番目までのプラックスは私たちとは違って、帰胎するまでの間隔がひどく不定期だから、いつ弱り始めるのかなんて全く分からないの。帰胎するようになるまで、百年かかることだってあるの。
だから、彼は本当は不安に慄いていたように見えた。だからいつも濡れたような黒くて長い髪を腰の辺りまで垂らして、震わせていた。なんて、みすぼらしくて気味が悪い男だったのかしら。全く何も食べていないみたいに痩せていて、奇妙に細長い指先はいつも垢だらけでしわくちゃだった。そしてそこに黒くて小さな指輪を一つだけ常にはめていた。それを見ると自分がもうすぐ、レザラクスの生贄の白い尻が必要になるのかどうか分かるとか言っていたらしいわ。私はその事を直接聞いたんじゃなくて本当に良かった。聞いていたらきっと唾でも吐きかけたに違いないから。
それで、私があなたに言っておきたいのは、そんな彼が百万人もに唾を吐きかけられたような髪の毛をしているとかそういう話じゃなくて、もっと大事な話があるのよ。それは、彼が今唯一の赤土の本を読める者であるということなの。
本とは言っても、それは、目で読むことは出来ない本が赤土の本。彼は本当はどうやってそれを読むのかしら?
彼は私たちの間では「舐め取る者」という意味のスクンエラと呼ばれているけど、赤土の本の血を舐める事とそれを読むことは同じであるとも言われている。
それは、どういうことなのか分かっていないのよ。
結局赤土の本を直に見ることが出来るのはスクンエラだけなんだし、その本のある白い草の部屋の中は、彼しか見ることが許されていないのよ。
だけど、あなたは彼自身によって帰胎するときの宿主として選ばれたんだし、多分きっとその時には何か分かるはずよ。」
そう言ってコーラルはいとおしそうに少し目を細めてリルファーを見た。リルファーはそんなことを聞かされているうちにまた訳の分からない混乱した気分を覚えた。
「一体この女は何を考えているのかしら、私をレザラクスのままでいさせてくれると言ってみたり、また、その逆に私にそんな気違いみたいな男が入り込んでくることを本気で羨ましがったり。本当は私のそんな恐怖をかき立てて楽しんでいるだけなのかもしれない。」
そう思っていると、また、コーラルに考えを簡単に読まれてしまったのだろうか、コーラルは本当はあなたの恐怖を必要としているだけ、とでも言いたげな、わざとらしい明るい笑顔を作って見せた。
リルファーはそれを見てうんざりするほど醜いレザラクスだと思った。
コーラルは本当はスクンエラに本の血ではなくて自分の体液を舐めとってほしかっただけじゃないだろうか、とも思えた。しかし、そんなことを口に出した瞬間、自分のコーラルに僅かながら感じ始めた、気の置けない安らかな感じを全て駄目にしてしまう気がした。だから、リルファーは少しだけ話の内容を変えてみようと思った。
「私、そういえば、貴方がプラックスを受け入れる前、私ぐらいのレザラクスだった時のことはあまり聞いていなかった気がする。私にその時の事を教えてくれないかしら。」
コーラルは何も言わずにじっと彼女のことを見ていた。リルファーは自分の声がもしかして必要以上に震えすぎていたから、話をはぐらかそうとしているのがばれてしまったのかもしれない、また、そんな演技をしている自分が蔑まれて当然とも思えた。そんな事を考えさせるくらい、彼女の沈黙は長かったのだ。
それくらい彼女のことを傷付けておいて十分だと思ったのだろう、コーラルは薄くてピンク色の唇をゆっくり開いた。
「そうね、貴方に話してあげてもいいわね。同類同士なにか、参考になることもあるかもしれないし。でも、その前にお茶を入れてくるから、貴方はここで待ってて。」
コーラルは彼女に何も言わせない前に立ち上がると急いでドアを閉めた。確かにそれは重要なことを話す前の伝統的な意味での儀式なのだろう。
リルファーはなぜか、落ち着いた気分になってコーラルの入れた濃い目のお茶を少しずつ口に流し込んでいった。もし、この部屋に窓があって外が見えたら、赤い実を付けた小さな木が風に凍えているのが見れるかもしれない。と彼女は思った。そして、その実の自分自身が赤いということによる苦痛は想像を絶しているに違いがない。
しかし、唐突にその空想を遮って、コーラルは話し始めた。
「私が神官養成院に居た時の話をするわ。貴方はつい最近までいたから、もちろん分っていたでしょうけど、私たちがあそこを出される時がまちまちだった訳は、私たちが帰胎を受け入れることが出来る状態になるまでの期間が一定ではなかったから。
さっき言ってた二十人目までのレザラクス達ほどではないけれどね。それでも、私みたいに18まで、レザラクスで居続けるもいるし、貴方みたいに10歳かそこらでここに送り込まれるものまで、いろいろなのよ。
それで、晴れてプラックスになれた暁にはこの国のあちこちに散らばる寺院に送られ、そこで、暇つぶしをしながら年を重ねて帰胎をするものである、「死の子供」になる時を待つのよ。」
コーラルは、思い出したくもない日々にゆっくりと回想を巡らせていった。確かに一体何があんなに苦痛だったのだろうか。単純に論理的には理由をはっきりさせることは、出来そうになかった。
養成院の朝はどんなふうだっただろう。寒さで膝小僧がかさかさになった女の子たちが、巨大な木で出来た何列にも並べられた、真っ黒い机に座らせられていた。
いつも、コーラルは後ろの方の席に座っていたから、前を見ると黒い髪の毛の房になったきれいな群れと、椅子の下にぷらぷら揺れる、白い裸足の足先たちが、見えていた。今、目の前に居るリルファーだってそれと同じ種類の足をしている。
その足先たちを女の子たちのひそひそ話を聞きながら眺めていられる間は、まだ平気だ。しかし、薄暗い廊下から、重たい濡れた布をずるずる引き摺る音と、湿ったあえぎ声が聞こえるようになると、女の子たちはとたんに押し黙ってしまう。
その白い布が隠す肉の塊の主、教官役のプラックスが、神聖なる姿を私たちに汚されないように白い飾りを付けた覆面をして、その奥から、青くひび割れた瞳をして、私たちのことを哀れな家畜を眺めるようにうっとりと、見つめた。
そして、女の子たちはまずは、スクンエラにより解読された赤土の本の写しを、全員で静かに読み上げることから一日を始める。コーラルはその赤土の本が、苦々しいほど長くて、訳が分からない呟きだと思っていたが、それだって、本当は分かっている部分の数パーセントにしか過ぎなかったことを、この偽りの神の子宮に着てから知った。
「レザラクスの皮は偽りで出来ている、しかし、私たちプラックスはその偽りの皮を着なければ生き延びることが出来ないのです。つまり、より純粋な状態の物がこの世に姿を保つためには適度なる汚濁が必要なのです。」
このプラックスの神官、ゲシタクセルは、赤土の本のちょうど読み上げている部分が、古語めいていたり、詩のようで全く訳が分からない時には、レザラクスたちのために自分なりの解釈を聞かせてみせた。しかし、コーラルはそんないじけた扇動めいたありがたい教訓よりも元のままの音の響きの方がよっぽど良いように聞こえた。
「レザラクス、ゴレス、ケスト、ヤゲスト、ゴレスヌス、タレル・・。」
この部分は元はこんな感じだっただろうか、幼いレザラクスに聞かされる部分は教訓めいた、短い言葉で出来た物に限られていた。
「だから、リルファー貴方にこの間、聞かせたみたいなクザルイト・フレアのような話もたくさんあるのよ。また機会があったら、他のものも聞かせてあげるわ。」
もう一度コーラルはリルファーの緑色の目が真っ黒くもつれた髪の毛の中で頷くのを見た。ピンク色の肌が天井の採光窓からわずかに落ちてくる陽の光に反射していた。彼女は微かに笑ってるのだ。
コーラルは空になったお茶の器をリルファーから受け取って静かにテーブルに置いた。確かに自分がこんなほこりにまみれたテーブルを物置から探し出して気違いしか入れられない、虹の息の部屋に持ち込んだときは自分で自分のことを笑いたくなったものだ。しかし、コーラルは今、本当にそうしておいて良かったと、思った。最初、そのテーブルの足は誰かに乱暴に蹴りつけられたのか宙ぶらりんになって骨折していたのだが、コーラルは自分で金槌を持ってそれを直したのだった。
こんな人里離れた聖堂には修理屋など居るはずはない。継ぎはぎの部分の釘が不細工に何本も飛び出していたのだが、逆にそれが新しい義足の丈夫さを証明しているように思えた。美しい役立たずの杖と醜くても立つことの出来る義足。それは、プラックス達がレザラクスに与えた言葉にも似ているように感じて仕方がなかった。
なぜ、プラックスたちはクザルイト・フレアのような話を秘密にしてきたのだろうか?
単純に考えてみれば、それは自分たちに都合の良い解釈を考えるにはその象徴表現が複雑でありすぎたために、面倒くさくなって隠しただけかもしれない。しかし、本当はレザラクスの本来ある姿がその言葉からばれてしまうのではないか、と、本能的に感じ賢明にも閉じ込めたということも想像出来なくはなかった。
「賢明にも、か。」本当はレザラクスとプラックスは同一の生物種のオスとメスに過ぎないはずなのに自分たちが蔑み支配する人間たちとは一体何の違いがあるというのか。
ふと、見ると、リルファーが不思議そうな顔をして自分のことを見ていた。また、知らないうちにあまりにも長く黙り込んでいたからだ。
「ごめんね。神官養成院に居た時も、そうやって、みんな今の貴方と同じような不思議そうな顔をして、私のことを見ていたわ。だから、話している相手がそういう顔をしている時は私がその人をずっとほっといていたということを私は、学習したわ。
本当に習ったことはそれだけかもしれないわね。」
コーラルは自分で少しだけクスリと笑って見せた。
「で、どこまで話したっけ?」
「教官の神官が呪文のような言葉に酷い解釈しかつけなくてそれが、自分たちの秘密を守るためだというところ。」
コーラルはこれには少なからず驚いていた。自分が黙想していると思っていたことをほとんど喋っていてしまったのだ。でも、彼女にはそれも悪くないか、と思えた。
「そう、でも、考えてみれば、私が養成院から出た時と貴方が入ってきた時はちょうど入れ違いだったんだから、そんなに学校の様子には違いが無いがないはずよ。」
「でも、良いの、私は聞きたいのよ。みんな、貴方みたいに教官たちについて思っていることを言ってくれる人も居なかったし、私だって言う事はほとんどなかったわ。プラックスの事を私は嫌いって言ったらみんな私のことを気違いだと思うに違いがなかったから。でも、貴方の話を聞いていたら、私は間違ってなんかいやしないって事が分かってきたわ。だから、もっと話の続きを聞かせて。」
コーラルはこの女の子の初めて冷静に話す声を聞いた気がしていた。
「分かったわ。それで、私たちは朝の朗唱が終わった後、人間たちが自分たちのために作り出してきた、科学、生物学、歴史学、民俗学などについて習った。プラックスの教師たちにね。とても不思議な事だと思わない? 人間達は自分自身ではとっくにそんなものは必要ではなくなってしまっているのに。」
「人間て、どういう生き物? 姿は私たちに本当に似ているの?」
「確かにそっくりよ。よく見なければ全然分らないくらい似ているわ。でも、どこか違うわ。私たちみたいにプラックス、レザラクスと交互に生まれ変わって浄化されないからね。だから、彼らは一生男であり、女で有り続けるために豚みたいに腐って死ぬのよ。なぜ人間はそれに他の下等な生き物たちは私たちと違って死ななければならないと思う? リルファー。」
なぜか、コーラルは人間を初めて見た時の嫌悪感をリルファーの青白い顔とこげ茶色に干からびたパジャマの中に感じた。それは、彼女をうろたえさせたのだが、すぐに自分がそう感じたことも間違いではないことに気づいた。そうだ、リルファーは自分の体の中に死を持っているじゃないか。だから、私はリルファーのことが気になって仕方がないんだ。そう、コーラルが自分の中で結論付けるのを許すほど、リルファーの返事はじれったく遅かった。ようやくした声は哀れに震えていた。
「死ぬってどういうことなのコーラル? それは、そんなに嫌なこと事なの? 私たち以外の全ての生き物たちが死ぬのは彼らが本当に劣っているからなの? だから、私たちのところに貢物を持って足を引き摺ってやってくるの? 彼らは本当に私たちがいなければ、全員、気が狂って千切れた鳥の花の咲くところに行ってしまわなくてはならなくなるの?」 リルファーは熱に浮かされた小鳥のように、小声で呟き、聞き続けた。
「だから、人間たちのほとんどが、苦しみの野に行ってしまったから、私たちのところに来なくなったのよね、コーラル? 死ぬっていうことは、千切られた赤い鳥の綿毛の咲く、苦しみの野に行かなくてはならないことよね?
だから、私はこんなところは捨てて、苦しみの野に行きたいのよ。赤い綿帽子が見てみたいの。」
「そう、あなたの考えでは死ぬということはそこに行くことなのね。本当にそこに行きたいと願っているからこそ、そこに行けるのかも知れない。
それは、私の思っていたこととはかなり違うわ。私が思っていたのは彼らが死ななくてはならないのは、彼らは忘れることが出来ないからよ。生きている限りね。もっとも、何か病的な理由ではそうなるかもしれないけど。
だけど、私たちは帰胎する時に、生き物の中で最も醜いものの一つの記憶するということから、逃れる事が、出来るのよ。」
そう言い終わらないうちにコーラルは席を立ち、テーブルの上の茶碗を盆にのせ、部屋を出た。
その、ガチャガチャいう陶器のぶつかり合う音から、自分の動揺がばれてしまうかも知れないと思いながら。確かに彼女は最も醜いことである、死の所へ、行きたいと言っていたのだ。
コーラルは、すぐにでも自分の部屋に行って休みたいと思ったが、まだ、午後の仕事を続けなければならなかった。死の胎児たちの世話だ。死の胎児たち、なぜ、彼らには偽りの死しかないくせにそのように呼ばれるのだろうか。それとも、自分たちは望むことが何もないから、死ねないのかもしれない。神は望む者に死を与え、望まぬ者に忘却を教えたのだろう。
コーラルは、黒いごつごつした石の廊下に出来た、殆ど見分けることの出来ない水溜りの白い反射を見つけながら、そのつどそれを飛び越えて行った。そういえば、ここに来たばかりの時は、靴の中までその臭い水によく浸かったものだった。ということをコーラルは思い出していた。