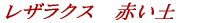
三章
トワンス・ロフは手を伸ばして、静脈の網目模様が浮き出た、リルファーの細い手首を取るとそこに刻まれた、12個の点線で作られた傷跡を無関心な様子で数えなおした。それは彼女の歯形に違いなかった。
彼女は自分自身を食おうとしたのだろうか? あの部屋の中には、この子にはおあつらえ向きの食事がすでに置かれていたというのにだ。髪の毛の部屋の流す黒い血を飲んでのどを潤すのをこんなに嫌う女がいるなんて、考えてもみなかったな。
こんな方法で自殺しようとするとんでもない阿呆はみたこともない。
トワンスはそこまで考えてから、その小さな括弧を描く点々の赤黒い染みから目を上げると、リルファー・ラグドザムの緑がかった目が、自分の事を見つめ続けていたことにやっと気付いた。それは道端に落ちた死んだ猫の目が、開いていても何も見ていないのとまったく同じだと考えることでトワンスは、自分の事を落ち着かせようとした。
「私は五番目の仮の神の子宮の守人のトワンス・ロフだ。君は本当ならレザラクスという苦しみに呪われた状態から、とうにプラックスへと生まれ変わっているはずなんだが、君がそれを嫌がったんだ。だから、当然のことながら、君は気を失ってこの虹の息の部屋に運ばれたんだ。君は学校で教えられていた通りになぜ、髪の毛の部屋の黒い雫を飲まなかったんだね?」
トワンスは自分の咽から発せられている言葉が、部屋の天井の薄暗いところまで、無意味に反響しつつ、煙のように消えていくのを待つしかなかった。彼女は言葉すら捨てたのだろうか?と、トワンスが不安に感じ、もう一度息を吸い込んで話しかけようとしたとき、彼女は静かに言った。
「トワンス・ロスさん。私たちは呪われてなんかいない、呪われているものがこの世にあるとしたら、それは私だけのはずよ。」
「ほう、なるほど、君だけが呪われている。それならそれでいい。」 リルファーには、木の皮の様な皮膚をしたこの男の目が少し笑っているようにさえ見えた。「ならば、どうしてプラックスになろうとしないんだね。君が死の胎児の姿になったプラックスを子宮の中に受け入れさえすれば、何の問題も無いじゃないか。私だってそうしたんだ。だから今はこのようにプラックスの姿でいられる。」
リルファーはベッドから初めて、肩を揺らして起き上がった。長く灰色がかった髪が蜘蛛の巣のように、ベールになって顔にかかった。
「私はあなたみたいになるんなら、死んだほうがましよ。プラックスのお爺さん。」
そう、彼女はつぶやくと彼に背中を向けて、すぐにまた横になってしまった。トワンスはそれを聞いて生まれてから初めて感じたような動揺を覚えたのかもしれなかった。唇を震わせながら言った。
「それなら、そのままでいればいい。だが、プラックスになる時期のレザラクスがそのままでいようとしても、生き延びられるはずはないのは分かっているんだろ。多かれ少なかれ、君の思うようになるさ。」そう言い捨てると、彼は神官衣をばたつかせて部屋を出ようとした。しかし、それに向かって彼女は言った。
「私を髪の毛の部屋の中から助け出した、あのレザラクスのふりをしたプラックスに会いたいわ。連れて来てよ。」
それを聞いて、トワンスは、少しの間黙って立っていたが、振り返ってから、鼻をならすと、「そうだな、お前がこの先どうなって行くのか、あいつとじっくり話し合え。そういえば、お前とあいつはそっくりじゃないか。」
そう、ぼんやり言うと、虹の息の部屋の15メートル上の天井の近くを常に流れている、青い雲のような光を見上げてから、彼は部屋を出た。そこにリルファーがいるのを忘れてしまったようなそぶりをして。神官衣が重そうに引きずられていく音が、遠ざかるのをリルファーは息を殺してじっと待った。
それから彼女は、ベッドに寝転びながら壁の天井の近くを通る、太くて青い何本もの光の虹の数を数えた。その部屋はまるで、煙突の中のような形をしていたが、別に息苦しくは感じなかった。どこからもライトによって照らされているわけでもないのに、床に近づくにつれて、白くて清潔な光に青く重苦しい光が変わるのだった。リルファーは、川に投げ捨てられた木の実が沈んでいく途中に、深くなっていくと青く変わるのとはちょうど逆のようだ。と思った。あの、トワンスが言っていたように、この部屋は私を閉じ込めるのにはちょうどいい場所なのだろう。黒い虹の息たちを眺めるのは、知らなかったけど気持ちの良い事だ。
少し目を閉じてから、もう一度ゆっくりまぶたを押し広げると、彼女はその虹が自分の目に映っている様子を自分で確かめることができないのを残念に思った。彼女の何より好きな風景は、鏡の中に映した自分の緑の目の中に反射する外の様子を見るときにだけ出来上がるのだ。しかし、今の彼女に与えられているものは、ベッドとシーツと枕と、自分の前には誰が着ていたかも、分からない古いベージュ色のパジャマだけだった。このパジャマを自分の前に着ていた女は、この世で最も薄汚い、髪の毛の部屋の中で、その毛先に付けられた粘液を舐め取って生きながらえて、そして、最後には、死の胎児を自分のヴァギナの中に受け入れたのだろうか。リルファーは自分の中に、その醜い蛭みたいな生き物が潜り込んでくるようすを想像して、かすかに吐き気さえ覚えた。
なぜ、プラックスたちは最後にはそんな恐ろしい姿になってまで、セックスをしたがるのだろうか。どうしてもリルファーが納得がいかないのは、それが唯一の自分たちの中にある神聖性を外に現す方法であるとされていることだった。確かに自分たちは、他のどんな生き物とも違っているわ。だけど、どうしてそれが神とやらに選ばれている証拠になるのだろうか。「プラックスたちは、他の人間の男という種族と同じように、精子を注入してから自殺すれば良いのに。」
プラックスは自殺しなくても良いように、レザラクスの中で生まれ変わるのだと、修道所の先生が言っていたのをリルファーは思い出した。「人間たちやその他のものは、年を取ると死ぬように出来ているが自分たちは違うんだ。」その頭の中にあるうつろな響きをもう一度小さな声でつぶやいた。「私たちは殺されない限り死ぬことはない、野蛮な人間たちの中では今も始終行われているはずの欲望による処刑、殺人行為の可能性からかけ離れたところに私たちはいるんだ。そのことがどういうことか、君たちにはよく考えてほしい。私たちが得てきたものをだ。」
リルファーはその教官のプラックスの薄白く塗られた唇、それにその中から常に発せられていた、家畜の鳥のような甲高い声を今また間近で聞いた気がした。
欲望による処刑、それは自分たちがペニスそのものになってヴァギナの中で溶け去ってしまいたいと願うこと以外の何ものでもない事に、リルファーは気付いていた。
リルファーは目の上の途方もない高いところでぐるぐる右回りにうごめきだした、青い霧から目を隠すためにシーツを引っ張るとすばやくかけた。でも、そうすると、自分の目の中の風景の中に最も映したくないものに、視線が行かざるを得なかった。1個、2個、3個。あの男の数えた通り、12個の歯形が自分の腕に見えた。「私はいつの間に自分を食べようとしたんだろう?あの部屋の中で、私は黒い露を飲まなかったんだ。だから、死にかけていた。そうか、私は死のうとしていたんだわ。それで、自分を食べて体を犠牲にして私は生き残ったのかもしれない。」
そのように、考えることは彼女には苦痛だったのだろう。もう一度目をつぶると、もっと考えたくないことから考えを反らせるためにだけ、眠った。
また元気になったら、髪の毛の部屋にまた閉じ込められることが間違いないということから。